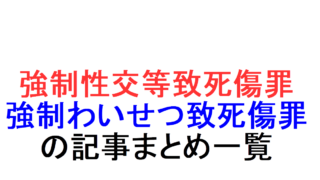同時傷害の特例(刑法207条)について、複数回にわたり解説します。
同時傷害の特例とは?
同時傷害の特例(刑法207条)は、
2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときに、暴行を加えた者全員に傷害罪の刑を科すことができるようになる規定
です。
端的に言うと、同時犯としての暴行による傷害についての処罰の特例を定めたものです。
(同時犯とは、2人以上の者が、意思の連絡なしに同時に又は同時に近い前後関係で、同一の客体に対して犯罪を実行する場合をいいます)
同時傷害の特例を適用した事例として、以下の裁判例があります。
大阪高裁判決(昭和61年12月10日)
裁判官は、罪となるべき事実として、
- 被告人両名は、以上の一連の暴行により、 Aに対し、左頬部・右頬骨部・右眼窩部及び鼻部表皮剥脱並びに皮下出血、左側頸部皮下及び筋肉内出血、左後頭部挫裂創、右頭頂部硬膜下血腫などの傷害を負わせ、そのころ、同所付近において、同人をして、右傷害を伴う外傷性くも膜下出血により死亡するに至らしめたが、いずれの暴行により致死原因たる外傷性くも膜下出血を生ぜしめたか知ることができないものである
と判示し、傷害致死罪に同時傷害の特例を適用しました。
同時傷害の特例は、検察官の犯罪立証の困難を救うための政策的規定である
2人以上の者が他人に暴行を加え、傷害の結果を生じさせた場合において、それが共同正犯の結果でない以上は、各人が自己の行為によって生じた結果についてのみ責任を負担するにすぎません。
したがって、数人の暴行のいずれかによって傷害の結果が発生したことは明らかであっても、検察官が、具体的にそのうちの誰の暴行によってどの傷害の結果が発生したかに関して因果関係の証明に成功しない限り、いずれの者も暴行ないし軽い傷害の限度で処罰されることとなります。
しかし、複数の者による暴行事案においては、
- 発生した傷害の原因となった暴行を特定することが困難である
- 共謀の立証が困難である
といった場合が多いです。
この検察官の犯罪事実の立証の困難というだけの理由で、同時犯としての暴行による傷害ないし重い傷害の結果について、だれにも責任を負担させることができないとするのは不合理な結果となります。
そればかりか、実際に傷害を加えた者の罪責を免れさすことにもなります。
そこで、このような検察官の犯罪事実の立証の困難を救うため、本条が政策的規定として設けられました。
参考となる判例として、以下のものがあります。
裁判官は、
- 同時傷害の特例を定めた刑法207条は、2人以上が暴行を加えた事案においては、生じた傷害の原因となった暴行を特定することが困難な場合が多いことなどに鑑み、共犯関係が立証されない場合であっても、例外的に共犯の例によることとしている
と判示しました。
大審院判決(昭和12年9月10日)
裁判官は、
- 互いに意思連絡なき2人以上の各暴行が、それぞれ同一の一定の期間にわたり、同一場所において、同一顧客に対し、相近接して数次に反復累行せられ、その所為が連続一罪たる傷害罪を構成する場合において、その傷害の軽重又は傷害を生ぜしめたる者を知ることを能わざるときは、刑法第207条の適用あるものとす
と判示しました。
これらの判例から、同時傷害の特例は、
- 傷害の原因となった暴行の特定ができない場合
- 共謀の立証が立証できない場合
の特例であると捉えることができます。
同時傷害の特例を適用するための検察官の立証方法
同時傷害の特例(刑法207条)を適用するにあたっての検察官に課される条件は
- 単に被告人及び他の者がそれぞれ被害者に暴行を加えた事実を立証するのでは足りない
- その暴行がいずれも傷害(あるいは死亡結果)を生じさせる程度であった事実を立証しなければならない
- その傷害がいずれの暴行によるかが明らかでない事実を立証しなければならない
の3点です。
自己の暴行が傷害を生じさせていないことの証明責任は被告人が負う(挙証責任の転換)
傷害罪に問われた被告人の主張としては、
- 自分に暴行事実がない
- 自分に暴行はあるが、相手の傷害事実はない
- 自分の暴行、相手の傷害はあるが、自分の暴行は当該傷害をもたらし得る暴行ではない
- 自分の暴行は傷害を生じさせ得る内容・程度であるが、相手の傷害はこれによるものではない
が考えられます。
①~③は、検察官が裁判で立証すべき事項であり、被告人は単に争うだけでなので、挙証責任は検察官にあり、被告人にはありません。
これに対し、④については、検察官ではなく、被告人が挙証責任を負うことになります(これを「挙証責任の転換」といいます)。
この場合に、被告人は、相手の傷害が専ら他の者の暴行によること、あるいは、相手の傷害のうち、 自己の暴行による傷害はその一部であることを主張することとなります。
この点について、参考となる判例として、以下のものがあります。
裁判官は、
- 検察官は、各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであること及び各暴行が外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況において行われたこと、すなわち、同一の機会に行われたものであることの証明を要するというべきであり、その証明がされた場合、各行為者は、 自己の関与した暴行がその傷害を生じさせていないことを立証しない限り、傷害についての責任を免れない
と判示し、検察官と行為者(被告人)がそれぞれが証明の責任を負うべき範囲を明示しました。