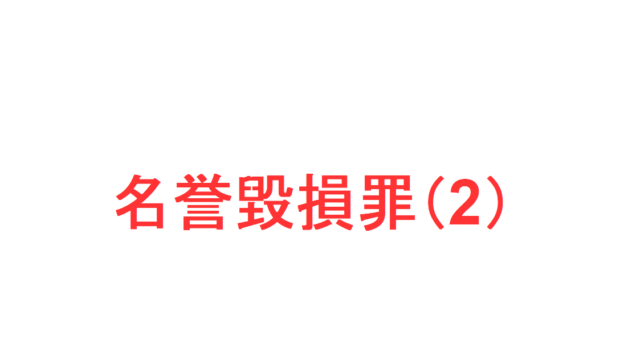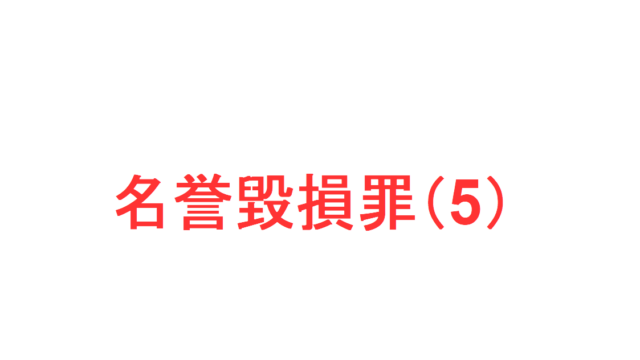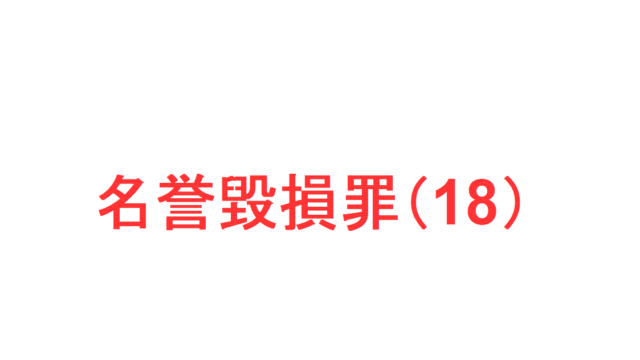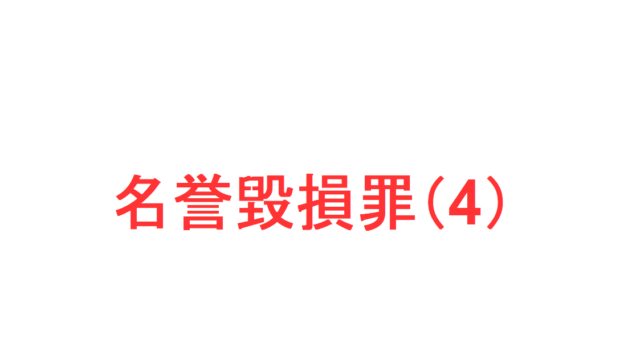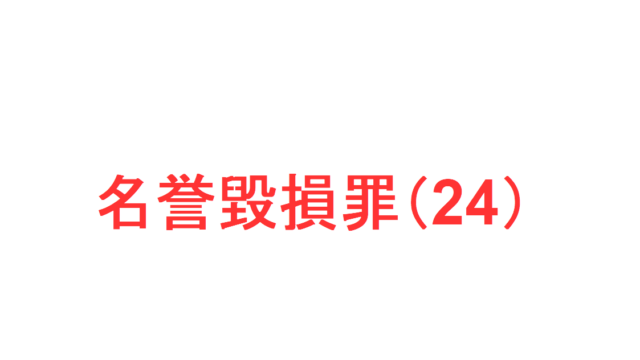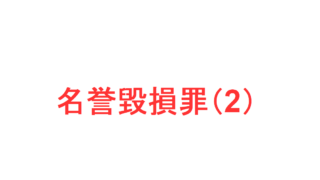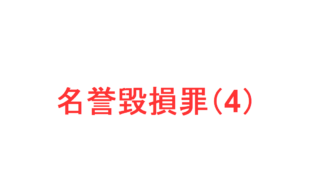前回の記事の続きです。
名誉毀損罪の行為(公然と事実を摘示して人の名誉を毀損すること)
名誉毀損罪(刑法230条)の行為は、
公然と事実を摘示して人の名誉を毀損すること
です。
公然とは?(公然性)
名誉は、「社会的評価」であるから、名誉毀損行為は、社会的評価を害する現実的危険を持ったもの…つまり、
社会に向かって行われる「公然」のもの
でなければなりません。
「公然」とは、
不特定又は多数人が認識できる状態
をいいます。
この点を判示した以下の判定があります。
大審院判決(昭和3年12月13日)
裁判官は、
- 人の名誉を毀損すべき事実を記載したる文書を郵便により多数の人に配布したるときは、現に配布を受けたる者が特定せるも刑法第230条にいわゆる公然たるを妨げず
- 公然とは、社会性を有し秘密にあらざる行為なるを指称し、いやしくも多数若しくは不特定の者に対し、他人の名誉を毀損するに足るべき文書を配布したるときは、これを受ける者の範囲に多少の制限あり、また宛名人が特定せると否とに関せず、名誉毀損罪は成立し、たとえその配布の方法が郵便によりたるとするも、真にこれを秘密に付することを要求し、他に発表するを厳禁したるにあらざる以上、これを公然というを妨げるものとす
と判示しました。
大審院判決(昭和6年6月19日)
裁判官は、
- 刑法第230条にいわゆる公然とは、秘密に非ざる行為なるを指称し、いやくも人若しくは不特定人に対し、他人の名誉を毀損すべき事実の摘示を為したるときは名誉毀損罪は成立し、たとえその多数人が特定せる範囲の者なる場合といえども、その行為はこれを秘密ということを得ざるをもって、これを公然というを妨げざるものとす
と判示しました。
裁判官は、
多数人の面前において人の名誉を毀損すべき事実を摘示した場合は、その他数人が特定しているときであっても、刑法第230条第1項の罪を構成する
と判示しました。
不特定とは?
不特定とは、
- 誰でも見聞し得た場合
- 摘示の相手が特殊の関係により限定された者でない場合(大審院判決 大正12年6月4日)
をいいます。
不特定に向かって摘示された名誉毀損行為は、被害者の名誉を害する現実的危険の発生が認められます。
限られた数名の者に対して摘示した場合であっても、その場所の通行・出入りが自由であって、相手方たる数名の者は、たまたまそこに居合わせたに過ぎないのであれば、不特定の要件を満たします。
この点を判示した以下の判例があります。
大審院判決(大正12年6月4日)
田の畔でその場に居合わせた数名の者に名誉を害する事実を摘示した事例です。
裁判官は、
- 田畝の傍らに巡査某ほか数名居合わせたる場合において、その一人の私行に関する悪事を公害する行為は、公然事実を摘示し、人の名誉を毀損したるものとして刑法第230条第1項を構成するものとす
と判示しました。
大審院判決(大正12年12月15日)
葬儀の際、遺族その他の者が自由に出入りし得る僧侶等の休憩所で、住職ら数名に対して名誉を毀損する事実を公言した事案です。
裁判官は、
- 葬儀の際、僧侶等の休憩室において、数人に対し、他人の名誉を毀損すべき事実を陳述するは公然、人の名誉を毀損する行為なり
と判示しました。
大審院判決(昭和6年10月19日)
公衆数名が居合わせた裁判所の公衆控所で他人の悪事をロ外した事案です。
裁判官は、
- 被告人が、A、B、Cほか公衆数名の居合わせたるK裁判所公衆控所において、高声にて告訴人Tの悪事を口外したる行為は、公然、事実を摘示して人の名誉を毀損したるものにして、刑法第230条第1項の犯罪を構成すること言を俟たず
と判示しました。
東京高裁判決(昭和28年6月29日)
被害者の家の出入口土間において道路の通行人にも容易に聞き取れる状況で怒鳴った事案です。
裁判官は、
- 被告人が被害者K方出入口土間において、Kに対し原判示のように怒鳴った言葉がK方北側道路の通行人にも容易に聴き取れる情況にあったことは、原判決の援用する検証調書の記載及び各証人の供述、供述調書の供述記載によって充分に認められるところであるから、被告人の発した言葉は、不特定多数の者が聞き得る状態にあったことが明らかである
- 名誉毀損罪における「公然」とは、不特定又は多数の者の見聞し得る状態にあることを言い、現実に見聞した者が皆無であることも妨げないものであって、同罪
 は、かかる名誉に対する危険の状態の発生をもって足りるとするいわゆる危険犯であるから、本件の被告人がKに対して怒鳴った言葉は、たとえ現実には付近に居合わせたKの家族数名が聞いたに過ぎなかったとしても、被告人が公然右Kの名誉を毀損したものと言わなければならない
は、かかる名誉に対する危険の状態の発生をもって足りるとするいわゆる危険犯であるから、本件の被告人がKに対して怒鳴った言葉は、たとえ現実には付近に居合わせたKの家族数名が聞いたに過ぎなかったとしても、被告人が公然右Kの名誉を毀損したものと言わなければならない
と判示しました。
東京高裁判決(昭和51年5月13日)
被告人の自宅から「カバ」「チンドン屋」「キョロ」「法律違反者」などと軽蔑的発言をした侮辱罪(刑法231条)の事案です。
裁判官は、
- 刑法231条にいう「公然」とは、音声等が不特定又は多数人の視聴に達せしめ得る状態であれば十分であると解されるところ、原判決の挙示する各証拠を総合、判断すれば、被告人の原判示所為が「公然」となされたものであることは明らかである
- 被告人がKに対する軽蔑的言辞を発した場所が被告人方自宅の内部であったとしても、近隣の居住者らが各自宅においてそれを聴取しているものである以上、本件は刑法231条の公然性の要件を十分満たしているものと解するのが相当である
と判示し、侮辱罪が成立するとしました。
「認識できる状態」とは?(状態認識可能性)
「公然」とは、「不特定又は多数人が認識できる状態」をいいます。
不特定又は多数人が「認識できる状態」であればよいということには、
- 現実に摘示事実の内容が認識・了解されたことを要しない
- 事実摘示の直接の相手方は特定少数人であっても、伝播して間接に不特定多数人が認識できるようになる場合も含まれ得る
という二つの意味合いがあります。
①②につき、以下で説明します。
① 現実に摘示事実の内容が認識・了解されたことを要しない
不特定又は多数人が「認識できる状態」であればよいとは、
現実に摘示事実の内容が認識・了解されたことを要しない
という意味合いがあります。
参考となる以下の判例があります。
大審院判決(明治45年6月27日)
裁判官は、
- 新聞紙、雑誌の如き公刊の文書によりて他人の名誉を毀損する罪は、名誉毀損の記事を掲載発行し、公衆の閲読し得べき状態に置くによりて成立し、右記事が公衆の閲読を経たることを必要とせず
と判示しました。
大審院判決(大正6年7月3日)
裁判官は、
- 公然の事実摘示とは、単に不定多衆の見聞し得べき状況において事実を摘示するをもって足れりとし、摘示の当時見聞者の皆無なることを妨げざるは明白
と判示しました。
② 事実摘示の直接の相手方は特定少数人であっても、伝播して間接に不特定多数人が認識できるようになる場合も含まれ得る
不特定又は多数人が「認識できる状態」であればよいとは、
事実摘示の直接の相手方は特定少数人であっても、伝播して間接に不特定多数人が認識できるようになる場合も含まれ得る
という意味合いがあります(伝播性の理論)。
参考となる以下の判例があります。
大審院判決(大正8年4月18日)
裁判官は、
- 公然たることは、必ずしも事実の摘示を為したる場所に現在せし人員の衆多なることを要せず
- 関係を有せざる2、3の人に対して事実を告知したる場合といえども、他の多数人に伝播すべき事情あるにおいては、これを公然と称するに妨げなし
と判示しました。
自宅において2名の者に対し、また、Y宅において5名の者に対し、問われるままに、Yが放火犯人だと述べた事案で、名誉毀損罪の成立を認めた事例です。
裁判官は、
- Xが、確証もないのに、YにおいてX方庭先の燻炭囲の菰に放火したものと思い込み、X方でYの弟Aおよび火事見舞に来た村会議員Bに対し、またY方でその妻C、長女Dおよび近所のE、F、Gらに対し、問われるままに、「Yの放火を見た」、「火が燃えていたのでYを捕えることはできなかった」旨述べたときは(その結果、本件ではYが放火したという噂が村中に相当広まっている。)不定多数の人の視聴に達せしめ得る状態において事実を摘示しYの名誉を毀損したものとして名誉毀損罪が成立する
としました。
この判例に対しては、学説では、判例に賛成する見解と、判例を批判し、事実摘示の直接の相手方が不特定多数人でなければならないとする見解とが対立しており、今日では後の立場が有力となっています。
その理由は、
- 法の文言が、公然性を摘示行為の態様として規定していること
- 伝播の可能性を理由に公然性を認めれば、相手方の意思によって犯罪の成立が決まること
- 情報を直接に社会的に流通させることが名誉毀損罪の処罰根拠であり、伝播性の理論は表現の自由に対する不当な抑制になること
が挙げられます。
学説では、不特定多数人の認識できることが行為の危険性を基礎づけるのである以上、伝播可能性は具体的であることが必要であって、当の言説が実際に不特定または多数人に伝播するであろうことを積極的に推認させるような具体的事情があることを要すると解すべきであるとするものがあります。
学説の見解に沿う裁判例として、名誉毀損の内容が不特定又は多数人に伝播するおそれが有るか否かを検討し、これが認められないときは、公然性は否定すべきと述べた以下の裁判例があります。
東京高裁判決(昭和58年4月27日)
裁判官は、
- 人の名誉を毀損するに足りる事項を記載した文書が、直接には、それ自体で多数とは言い得ない特定人に対して郵送された場合にあっては、法の趣旨に従い、当該文書の性質、内容、相手方との関連、その他具体的諸事情を総合して、社会通念により、その記載内容が不特定又は多数人に伝播するおそれが有るか否かを検討し、これが認められないときは、当該所為の公然性はこれを否定すべきものである
と判示しました。