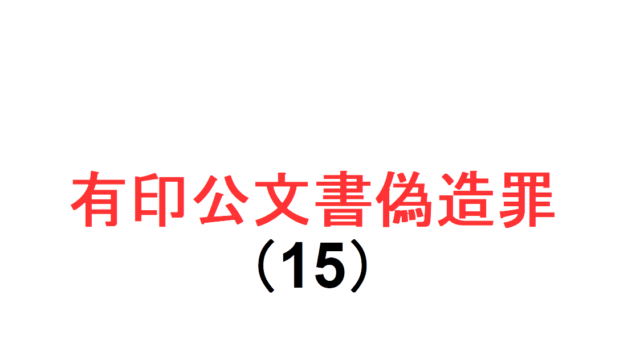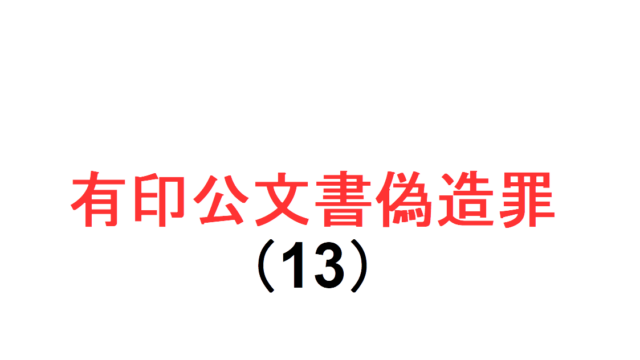有印公文書偽造罪(11)~「『文書の社会的機能』『偽造文書の行使態様』を考慮して文書偽造の成立が認められた裁判例」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、有印公文書偽造罪(刑法155条1項)を説明します。
「文書の社会的機能」「偽造文書の行使態様」を考慮して文書偽造の成立が認められた裁判例
文書偽造とは、「一般人が真正な文書であると誤信するに足りる程度の形式・外観を備えている文書を作成すること」をいいます(詳しくは前回の記事参照)。
ここにいう真正な文書の外観は「文書の形式」や「文書の内容自体」から判断されるところ、
- 文書の社会的機能
- 偽造文書の行使態様
をも考慮に入れて判断される場合があります。
文書を直接手にとらて見れば容易に見破られるような改ざんを施した文書を作成した行為について、行使態様を考慮して有印文書偽造罪の成立を認めた裁判例として、以下のものがあります。
大阪地裁判決(平成8年7月8日)
自己名義の運転免許証に、他人の運転免許証の写しの氏名、生年月日欄等を切り取ったものを該当箇所に重ねて置くなどし、その上からメンディングテープを全体に貼り付けて固定し、これをイメージスキャナー等の電子機器を通してディスプレイに表示させ相手方に呈示した行為について、有印公文書偽造・同行使の各罪の成立を認めた事例です。
裁判所は、
- 当該文書の形式・外観が、一般人をして真正に作成された文書であると誤認させるに足りる程度であるか否かを判断するに当たっては、当該文書の客観的形状のみならず、当該文書の種類・性質や社会における機能、そこから想定される文書の行使の形態等をも併せて考慮しなければならない
- これを、本件で問題とされる運転免許証についてみると、運転免許証は、自動車等の運転免許を受けているという事実を証明するためのみではなく、広く、人の住所、氏名等を証明するための身分証明書としての役割も果たしており、その行使の形態も様々であり、呈示の相手方は警察官等の公務員のほか、広く一般人であることもあり、また、必ずしも相手方が運転免許証のみを直に手に取って記載内容を読み取るとは限らず、免許証等入れのビニールケースに入ったまま、しかも、相手に手渡すことなく示す場合もあるし、その場面も、夜間、照明の暗い場所であったりするし、時間的にも、瞬時ないしごく短時間であることさえある
- さらに、近時は、相手方の面前で呈示第使用されるだけではなく、身分証明のために、コピー機やファクシミリにより、あるいは、本件のように、イメージスキャナー等の電子機器を通して、間接的に相手方に呈示・使用される状況も生じてきている(このような呈示・使用が偽造文書行使罪における行使に該当することはもちろんである。)
- したがって、運転免許証の偽造の程度を云々するに当たっては、このような行使の形態をも念頭に置いた上で、前記の判断をするのが相当であると考えられる
と判示しました。
札幌高裁判決(平成17年5月17日)
無人自動契約機のスキャナーを通して端末画面に偽造文書を表示させた行為について、行使態様を含めて公文書偽造・同行使罪の成立を判断するのは処罰範囲を不当に拡大するとして同罪の成立を否定した原判決を破棄し、同罪は文書の社会的機能、行使態様を含めて判断すべきであるとして同罪の成立を認めた事例です。
裁判所は、
- 原判決は、改ざんした自衛官診療証には修正テープ等の痕跡が明瞭であって一般人が真正文書と誤信しないし、スキャナーを介した行使態様を含めてその判断をするのは処罰範囲を不当に拡大するとして、公文書偽造・同行使罪の成立を否定したが、本件文書の社会的機能として身分証明用にスキャナーを介して呈示することが広く行われており、偽造文書にあたるかどうかは、文書の社会的機能、行使態様をも考慮して判断するのが相当であり、スキャナーを通して画面に表示される本件文書には修正テープ等の痕跡が分からない上、被告人も、その旨認識認容して本件犯行に及んでいるから、処罰範囲を不当に拡大することもない
と判示し、公文書偽造・同行使罪の成立を認めました。
東京地裁判決(平成22年9月6日)
公安委員会から交付を受けていたビニール製ケース入り駐車禁止除外指定車標章の有効期限欄や発行日欄の数字記載部分に、元の記載と異なる数字が印字された紙片を置いて密着させた上、ビニール製ケースとの間に挟み込むようにして同紙片を固定した事案です。
裁判所は、
- 犯行態様は模倣性が高く、精巧な
偽造とはいえないまでも、警察官等がフロントガラス越しに確認するという駐車禁止除外指定車標章の通常の用法を考慮すれば、この程度
の偽造であっても公文書たる同標章の信用を害するのに十分なものである
旨判示し、公文書偽造罪の成立を認めました。
東京高裁判決(平成20年7月18日)
国民健康保険被保険者証の白黒コピーを改ざんしたものをファクシミリにセットし、その画像データを送信して、端末機の画面に表示させて相手方に呈示した行為について、
- 改ざん物の色合いや大きさ等(A4大の紙に保険証を原寸大でコピーし、これに数字等が印字された紙を貼り付けて改ざんし、保険証部分を切り取っていないもの)の客観的形状からみて、これを電子機器を介するのでなく肉眼等で観察する限り、保険証の原本であると認識することは通常は考え難く、このような物を作出した時点では、いまだ公文書である本件保険証の「原本」に対する公共の信用が害されたとは評価できず、原本の偽造を遂げたとすることはできない
としつつ、
- その写しについては、一般人をして真正なコピーであると誤認させるに足りる形式、外観を備えた文書である
として、国民健康保険被保険者証の白黒コピーを改ざんしたものの写しについて、文書偽造罪、偽造文書行使罪が成立するとしました。
【参考】文書の偽造の概念に関する説明
以下の記事で、文書の偽造の概念に関する説明をしています。
文書偽造・変造の罪(9)~偽造の概念①「偽造内容の真否と文書偽造罪の成否」を説明
文書偽造・変造の罪(10)~偽造の概念②「偽造の程度(偽造文書は、一見して真正文書と誤信されるようなものでなければならない)」を説明
文書偽造・変造の罪(11)~偽造の概念③「偽造罪の既遂時期」を説明
文書偽造・変造の罪(12)~偽造の概念④「『文書の名義人』と『文書の作成者』は区別される」を説明
文書偽造・変造の罪(13)~偽造の概念⑤「『文書の名義人』と『文書の作成者』は区別される」を説明