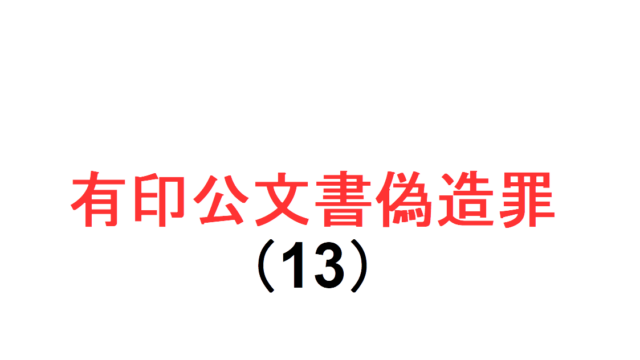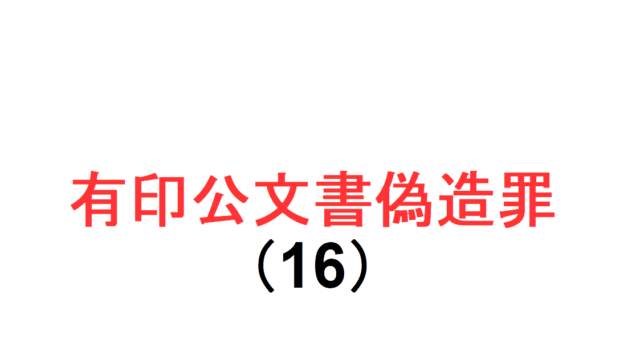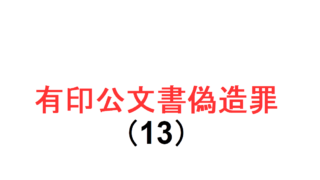有印公文書偽造罪(12)~「偽造と変造の区別」「コピーの場合は、原本に変造の範瞬に属する程度の改ざんを加えてコピーを取った行為でも、変造ではなく偽造に当たる」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、有印公文書偽造罪(刑法155条1項)を説明します。
偽造と変造の区別
既存の文書に手を加えてこれを利用してこれを改ざんした場合に、
- 文書の偽造(文書偽造罪)になるのか?
- 文書の変造(文書変造罪)になるのか?
が問題になります。
この点の考え方をまとめると以下のようになります。
預貯金通帳について
郵便貯金通帳について、
- 貯金者の名義を改ざんするのは偽造となる
- 貯金受入れ又は払戻しの年月日のみを改ざんするのは変造となる
- 貯金金額のみを改ざんすれば変造となる
と解するのが通説です。
この点、東京高裁判決(昭和52年11月21日)は、郵便貯金通帳の金額を改ざんした行為を変造と評価しています。
運転免許証について
運転免許証について、住居変更手続を済ませたように装うため裏面備考欄の住所変更記載部分を変更するのは変造であるとした裁判例があります(東京地裁判決 平成19年2月16日)。
顔写真がある証明書について
外国人登録証や、運転免許証などの顔写真がある証明書について、顔写真を剥ぎ取り、他人の顔写真を張り替えたときは公文書偽造罪が成立します。
このような証明書は、特定人に対し発行されたもので、顔写真は文書の重要事項に属し、 これの張り替えは別の文書を作出したと同視できるためです。
この点を判示した判例として、以下のものがあります。
外国人登録証明書に貼付してある写真を恣に剥ぎとり、他人の写真を貼り代えた場合には、公文書偽造罪が成立するとしました。
特定人に交付された自動車運転免許証に貼付してある写真をほしいままに剥ぎとり、その特定人と異る他人の写真を貼り代え、生年月日欄の数字を改ざんし全く別個の新たな免許証としたときは、公文書偽造罪が成立するとしました。
コピーの場合は、原本に変造の範瞬に属する程度の改ざんを加えてコピーを取った行為でも、変造ではなく偽造に当たる
コピーの場合は、原本に変造の範瞬に属する程度の改ざんを加えてコピーを取った行為でも、変造ではなく偽造に当たります。
公文書の改ざんコピーを作成することは、原本とは別個の文書を作り出すものなので、文書の変造は論理的に成立の余地がなく、文書の偽造に当たると解されるためです。
この点を判示した以下の判例があります。
営林署長名義の売買契約書の売買代金欄を改ざんした事案です。
裁判所は、
- 行使の目的をもつて、ほしいままに、営林署長の記名押印がある売買契約書の売買代金欄等の記載に改ざんを施すなどしたうえ、これを複写機械で複写する方法により、あたかも真正な右売買契約書を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を備えるコピーを作成した所為は、その改ざんが原本自体にされたのであれば未だ文書の変造の範ちゅうに属するとみられる程度にとどまっているとしても、刑法155条1項の有印公文書偽造罪に当たる
と判示しました。
【参考】文書の偽造の概念に関する説明
以下の記事で、文書の偽造の概念に関する説明をしています。
文書偽造・変造の罪(9)~偽造の概念①「偽造内容の真否と文書偽造罪の成否」を説明
文書偽造・変造の罪(10)~偽造の概念②「偽造の程度(偽造文書は、一見して真正文書と誤信されるようなものでなければならない)」を説明
文書偽造・変造の罪(11)~偽造の概念③「偽造罪の既遂時期」を説明
文書偽造・変造の罪(12)~偽造の概念④「『文書の名義人』と『文書の作成者』は区別される」を説明
文書偽造・変造の罪(13)~偽造の概念⑤「『文書の名義人』と『文書の作成者』は区別される」を説明