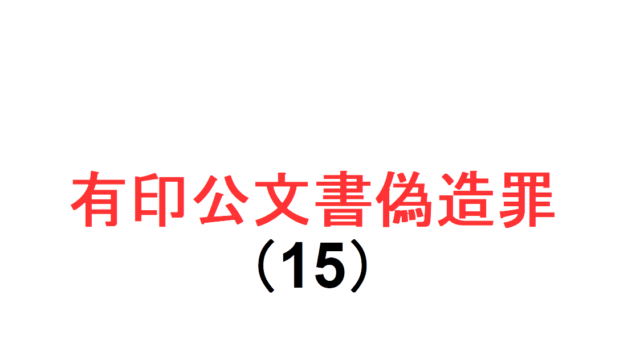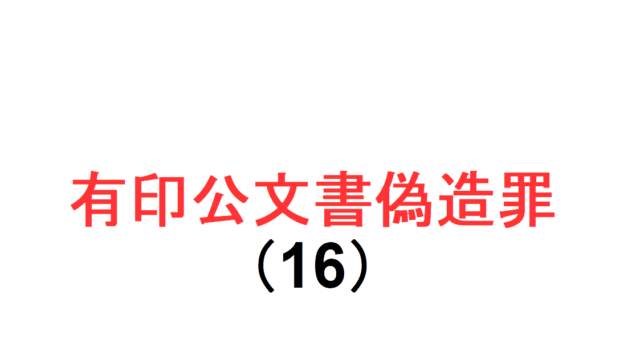有印公文書偽造罪(13)~「公務所、公務員の印章・署名とは?」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、有印公文書偽造罪(刑法155条1項)を説明します。
公務所、公務員の印章・署名とは?
有印公文書偽造罪は、刑法155条1項に規定があり、
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する
と規定されます。
「公務所若しくは公務員の印章」とは?
刑法155条1項の条文中にある「公務所若しくは公務員の印章」とは、
- 公務所、公務員の人格の同一性を表彰するために、物体上に顕出された文字又は符号の影蹟(つまり印影)
と
- それを顕出させるに要する文字若しくは符号を刻した物体(つまり印顆)
の双方をいいます。
有印公文書偽造罪の成立を認めるに当たり、公務員の印章は、その本来の性質が、公印でも、私印でもよく、また、職印でも、認印でも差し支えありません。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(昭和9年2月24日)
裁判所は、
- 行使の目的をもって公務員の印象を使用し、公務所又は公務員の作るべき文書を偽造するにおいては、たとえこれに公務所の印章又は公務員の自署なき場合といえども、刑法第155条1項の犯罪を構成するものとす
- 刑法第155条第1項にいわゆる公務員の印章とは、公務員が職務上使用する一切の印章を示称し、その印章が認印たると職員たるとを問わざるものとす
と判示しました。
「公務所若しくは公務員の署名」とは?
刑法155条1項の条文中にある「公務所若しくは公務員の署名」は、
- 自署であると記名であるとを問わない(大審院判決 大正4年10月20日)
- 作成者が誰であるかを表示するものはすべて含まれ、公務員の署名のほかに、公務所の署名もある
とされます。
参考となる以下の判例があります。
大審院判決(明治43年5月13日)
裁判所は、
- 郵便局(※当時は国営)に備え付けある受付時刻記入用の日付印を不正に使用し、その影蹟(えいせき)の空間に(※判子を押すための空欄箇所に)、年月日の数字を記入したる所為は、郵便局の公印を不正に使用したるものに非ずして、郵便局の署名を偽造しその受付時刻証明書を偽造したるものなりとす
と判示し、郵便局の日付印を用いて受付時刻証明書を偽造した行為について、有印公文書偽造罪が成立するとしました。
公務員の印章、署名を「使用」するとは?
刑法155条1項の条文中にある公務所、公務員の印章、署名を「使用」するとは、
- 公務所、公務員の真正の印顆を無権限で押捺すること
又は
- 正当に押捺された印章、署名を無権限で使用すること
をいいます。
有印公文書偽造罪の成立を認めるに当たり、印章、署名は、どちらか一方が使用されれば足ります。
なお、自動車検査証の上部欄外などに記載されている「公印省略」という朱色方形の形象は、有印公文書偽造罪にいう押印には当たらないとした裁判例があります(東京高裁判決 昭和53年12月12日)。
「偽造した公務所、公務員の印章・署名」とは?
1⃣ 刑法155条1項の条文中にある「偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して…」にある「偽造した公務所、公務員の印章・署名」とは、
- 権限を有しないものが、ほしいままに作成した公務所、公務員の印顆又は物体上に顕出した公務所、公務員の印影又は署名
を意味します。
2⃣ 有印公文書偽造罪の成立を認めるに当たり、必ずしも偽造した印顆を押捺する必要はなく、一般人をして、作成名義人である公務所、公務員の印章と誤認させるに足りる類似した印影を文書に表出させればよいです。
この点を判示したのが以下の判例です。
裁判所は、
- A法務社岸和田支局またはB地方法務新聞宇治山田支局各名義の各船舶登記証書を作成した場合においても、A法務社岸和田支局なる印の「社」およびB地方法務新聞宇治山田支局之印なる印の「新聞」という各文字の処を殊更に不鮮明に押捺し、各その形式外観によって、一般人をしてA法務局岸和田支局またはB地方法務局宇治山田支局が権限により作成した公文書たる登記証書であると誤信せしめるに足りるものと認められるときは各公文書偽造罪が成立する
と判示しました。
3⃣ 赤鉛筆で印影を描いた場合でも、有印公文書偽造罪に当たることがあります。
この点を判示したのが以下の判例です。
赤鉛筆で印影を画いた事案で、その印影が有印公文書偽造罪の偽造に当たるとした事例です。
裁判所は、
と判示しました。
4⃣ 使用する印章、署名は、行為者みずから偽造したものであると、他人が偽造したものであるとを問いません。
印章は、一般人に公務所の印章であると誤信させるものであれば足ります。
また、行為者みずから公務所・公務員の印章・署名、公記号を偽造し、これを使用して公文書を偽造したときは、
又は
は、有印公文書偽造罪に吸収されます。
参考となる判例として、以下のものがあります。
大審院判決(昭和8年9月27日)
裁判所は、
- 偽造したる公務所の印章使用による公文書偽造の成立するには、一般世人をして公務所の印章なりと誤信せしむるに足るべき類似の印顆を押捺して、その影蹟(えいせき)を文書に表顕せしめ、これを使用して文書を偽造するをもって足りるものとす
- 印章偽造行使に対し、刑法第166条を適用せざりしは、その偽造行使は、登記済証偽造行使罪中に包括処罰せらるべきにして、別に同条の適用すべきものに非ざる
と判示しました。
大審院判決(大正12年4月23日)
裁判所は、
- 行使の目的をもって他人の印章を不正に使用し、権利義務に関する他人名義の文書を偽造する行為は、刑法第159条第1項に該当するほか、同法第167条の罪名に触れるものに非ず
と判示しました。