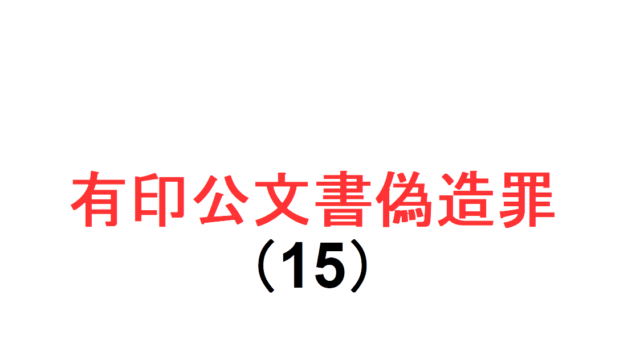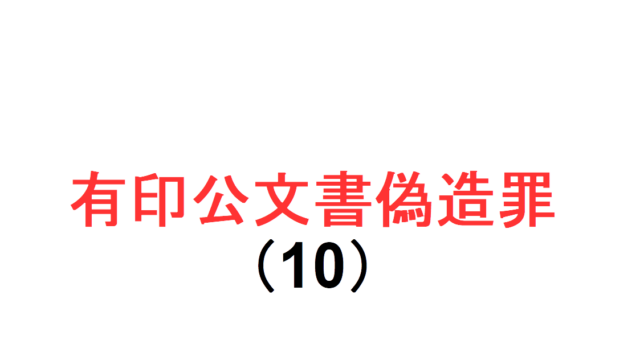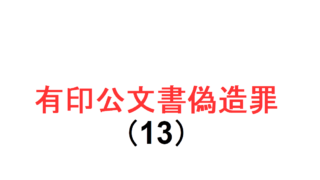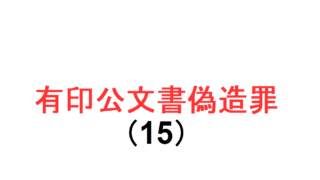有印公文書偽造罪(14)~「文書偽造罪の罪数の考え方」「公文書偽造罪と偽造公文書行使罪との関係(牽連犯)」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、有印公文書偽造罪(刑法155条1項)を説明します。
文書偽造罪の罪数の考え方
文書偽造罪の本質を作成名義の真正に対する公の信用の保護に求めるならば、作成名義ごとに一罪が成立するというのが論理的です。
しかしながら、文書には様々な内容、形態のものが存在するため、すべてを1つの基準で割り切ろうとすると、不合理な結果になり得ることは否めず、画一的な基準で判断することはできません。
文書偽造罪の罪数を定める標準について、判例・学説の見解は分かれており、以下の①~⑦の考え方に整理することができます。
- 冒用された文書の作成名義の数を標準とするもの(大審院判決 明治42年3月11日)
- 文書の物体自体の個数を標準とするもの(大審院判決 大正6年3月10日)
- 文書作成の意思の個数を標準とするもの(学説)
- 文書の内容である事項の数を標準とするもの(大審院判決 昭和10年1月31日)
- 侵害される法益の数を標準とするもの(大審院判決 明治43年7月1日)
- 総合判断説(文書の作成名義を主眼としつつ、文書の物体自体の数、文書の内容である事項の数及び侵害される公共的信用の意味にも着目して総合的に判断)
実際の裁判では、作成名義の数を主眼としつつ、文書の物体自体の個数や、文書の内容である事項の数、侵害される公共的信用の意味等にも着目して、総合的に判断しているといえます。
文書偽造罪の罪数に関する判例・裁判例
文書偽造罪の罪数について、参考となる判例・裁判例として以下のものがあります。
大審院判決(大正8年6月27日)
公文書と私文書が1通の書面に併存する場合に、両者を偽造すれば公文書偽造罪と私文書偽造罪の両罪が成立するとしました。
大審院判決(昭和11年3月30日)
公文書と私文書が1通の書面に併存する建物の証明願いに、申請家屋は申請者の所有である旨の区長の証明奥書を受けた上、証明願い部分の紙片を取り外して他の証明願いに差し替えたときは、公文書偽造にのみ当たるとしました。
大審院判決(昭和7年2月25日)
郵便貯金通帳の受入れ又は払戻しに関する記載は、おのおのその受入れ・払戻しに関する事項を証明するもので、「受入れに関する記載」と「払戻しに関する記載」は、それぞれ一個の公文書をなし、各記載ごとに公文書偽造罪が成立するとしました。
【補足説明】
郵便貯金通帳の受入れ・払戻しの各欄の記載は、それぞれ独立した公文書としての性質を有するので、複数の公文書が併存しているとみられます。
※ 郵政民営化前は、郵便貯金通帳は公文書であった
郵便貯金通帳の各欄は、その表紙の記載と相まって意味を有するものなので、表紙の記載を改ざんする行為は、同時に、各欄の記載に対する偽造ともみられます。
郵便貯金通帳の表紙を偽造した場合(文書偽造罪が1個成立)は、同時に、郵便貯金通帳の受入れ・払戻しの各欄の偽造したものとなり(さらに文書偽造罪が複数成立)、各文書偽造罪は観念的競合の関係になります。
公文書偽造罪と偽造公文書行使罪との関係(牽連犯)
公文書偽造罪(刑法155条)と偽造公文書行使罪(刑法158条1項)との関係について、偽造文書の作成とその行使との間に、手段結果の関係があるので、両罪は牽連犯となります。