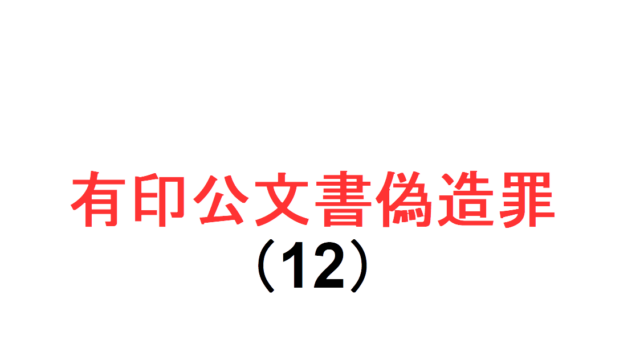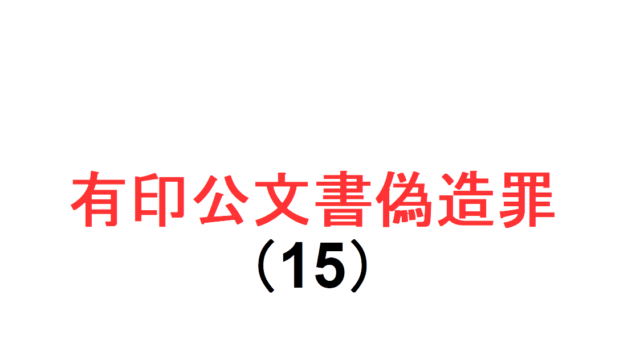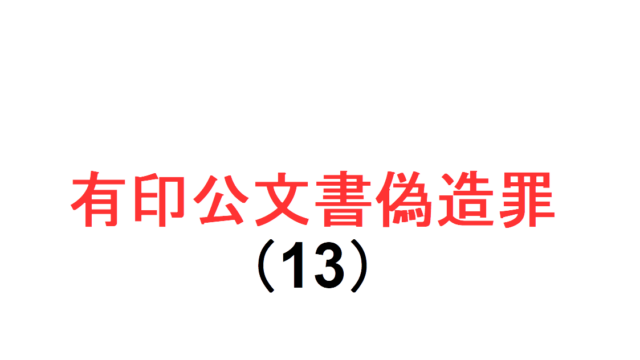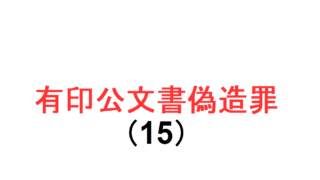有印公文書偽造罪(16)~「虚偽公文書作成罪の教唆を共謀したが、共犯者の一人が公文書偽造罪の教唆を行った場合、共謀者両名とも公文書偽造罪の教唆の責任を負う」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、有印公文書偽造罪(刑法155条1項)を説明します。
虚偽公文書作成罪の教唆を共謀したが、共犯者の一人が公文書偽造罪の教唆を行った場合、共謀者両名とも公文書偽造罪の教唆の責任を負う
AとBが虚偽公文書作成罪(刑法156条)の教唆の共謀をしたところ(刑務所の医師を買収して虚偽の診断書を作成させる)、共謀者の一人Bが公文書偽造罪(刑法155条)の教唆行為(他人に依頼して刑務所勤務の公務員に偽造の診断書作成を依頼)をした場合でも、故意を阻却せず、AとBの両方は公文書偽造罪の教唆の責任を負います。
これは、公文書の無形偽造罪と有形偽造罪とは構成要件を異にしますが、その罪質を同じくするものであり、かつ法定刑も同じためです。
※ 有形偽造とは、文書の作成権限がない人が他人名義の文書を作成することをいいます。
※ 無形偽造とは、文書の作成権限がある人が事実でない内容の文書を作成することをいいます。
この点を判示したのが以下の判例です。
裁判所は、
- 原判決の挙示する証拠によって第一審相被告人Aが第一審相被告人Bを教唆し同人をして原判示の如き岡山刑務所医務課長C名儀の診斷書一通を偽造せしめた事実を認定することができるのであるから原審が右診断書を公文書と認定したのは正当である
- 刑法第156条の公文書無形偽造偽造の罪を教唆することを共謀した者の一人が、結局、公文書有形偽造教唆の手段を選び、これによって目的を達した場合には、共謀者の他方は事実上公文書有形偽造教唆に直接関与しなかつたとしても、その結果に對する故意の責任を負わなければならない
- 公文書が偽造のものであることを知らなかつたとしても、虚偽内容のものであると考えて行使した場合には偽造公文書行使罪の故意犯が成立する
と判示しました。
裁判所は、
- 同一の公文書に関する有形偽造と無形偽造とは、罪質を同じくし、その間の認識の齟齬は、実行せられた偽造の結果に対する故意の責任を阻却するものでなく、かつ両者その法定刑を同じくするから、刑法38条2項の制約を受けるものではない
と判示しました。