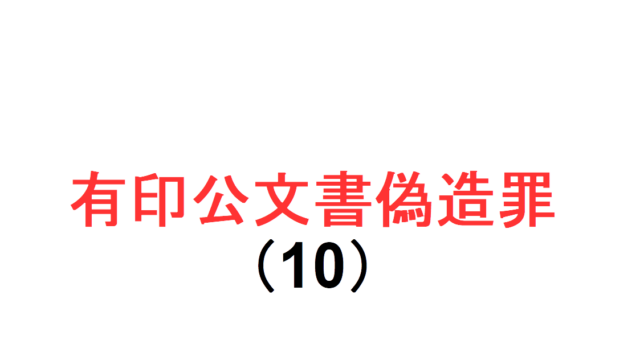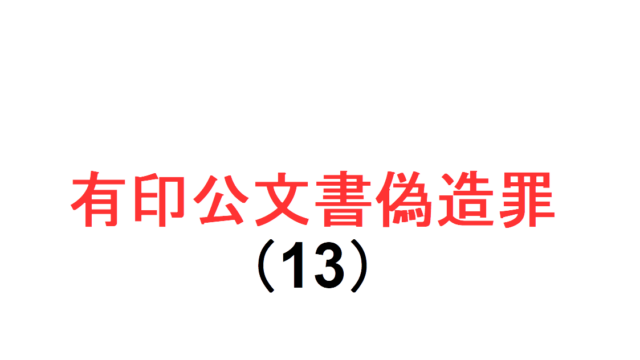有印公文書偽造罪(3)~主体②「主体(犯人)が『補助公務員』である場合の本罪の成否の考え方」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、有印公文書偽造罪(刑法155条1項)を説明します。
主体(犯人)が「補助公務員」である場合の本罪の成否の考え方
官公庁が巨大化して事務量が増加するとともに、情報化社会の中で市民から各種証明書や膳抄本等の交付が大量に求められる今日、公文書を作成するごとに作成権者ないしは代決権者の決裁を逐一仰ぐことはできないことは明らかで、補助公務員にその事務を委ねざるを得ない実情が行政実務に存在します。
そこで、補助公務員の作成権限の有無が問題となります。
この問題の考え方は以下のとおりです。
代決権を有しない補助公務員の場合に、名義人又は代決者の事前の決裁を受けずに、一定の手続に従って公文書を作成することが許されているときは、内容の正確性を確保するなど、その者の授権を基礎付ける一定の基本的な条件に従う限り、その作成手続に一部違反があっても、基本的には補助者としての権限に基づく文書の作成であるから、公文書偽造罪は成立しません(最高裁判決 昭和51年5月6日参照)。
上記のような権限も有しない補助公務員の場合には、名義人又は代決者の決裁を待たずに虚偽の内容の公文書を作成したときは、公文書偽造罪が成立します(最高裁判決 昭和26年10月26日、最高裁判決 昭和27年12月25日、最高裁決定 昭和34年6月30日参照)。
なお、補助公務員が、その職務上起案すべき公文書につき虚偽の内容を記載して、情を知らない作成権限者に署名押印等をさせた場合は、虚偽公文書作成罪(刑法156条)の間接正犯が成立します(最高裁判決 昭和32年10月4日参照)。