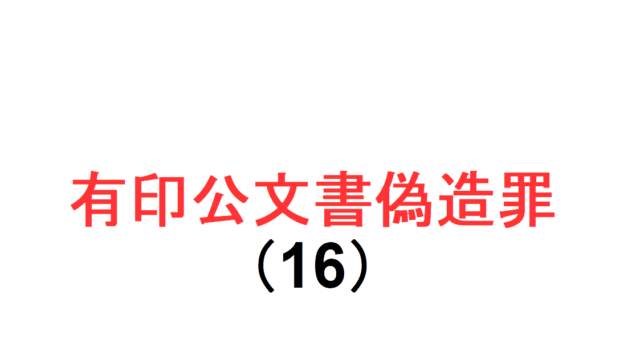有印公文書偽造罪(4)~「文書の作成権限のある者に対し、その者が文書を作成するとの認識がない状態にあるのを利用して文書を作成させた場合には、文書偽造罪の間接正犯が成立する」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、有印公文書偽造罪(刑法155条1項)を説明します。
文書の作成権限のある者に対し、その者が文書を作成するとの認識がない状態にあるのを利用して文書を作成させた場合には、文書偽造罪の間接正犯が成立する
文書の作成権限のある者に対し、その者が文書を作成するとの認識がない状態にあるのを利用して文書を作成させた場合には、文書偽造罪の間接正犯が成立します。
「間接正犯」は、
他人を道具として利用し、他人に犯罪行為をやらせ、犯罪を実現する者
いいます(間接正犯の説明は前の記事参照)。
上記のような場合には、文書作成の権限者が当該文書を作成するという意思を欠いており、文書作成の権限者を道具として利用し、文書偽造の犯罪を実現する状態であるため、文書偽造罪の間接正犯が成立することになります。
文書偽造罪の間接正犯の具体例として、
- 文書作成の権限者の文盲を利用した場合(大判明43 ・10・7 録16輯1647 頁)
- 署名者に他の文書と欺いて署名させた場合(大判明44・5・8 録17輯817頁、大判大5・5・8 録22輯705頁)
が挙げられます。
文書作成権限者に「盲判」を押させ場合の公文書偽造罪の成否
文書作成権限者に盲判を押させ場合は、公文書偽造罪の間接正犯が成立するか、虚偽公文書作成罪の間接正犯が(刑法156条)が成立するかについては、議論があります。
盲判については、押した者が文書の性質を全く認識していない場合があり、そのようなときには文書偽造罪が成立します。
これに対し、学説では、盲判をした者が、文書の作成意思そのものはある場合については、虚偽公文書作成罪が成立する場合があり得るが、公文書偽造罪は成立しないとするものがあります。
参考判例として以下ものがあります。
大審院判決(大正11年11月30日)
帳簿に虚偽の記載をし、これを情を知らない村長に正当な記載と誤信させて捺印させた行為について、有印公文書偽造罪の成立を認めました。
裁判所は、
- 原判決において、京都市a区の役所の外国人登録事務の一係員たる被告人Aが、外国人登録証明を受ける資格のない者に同証明書を交付する目的で、不正の同証明書交付申請をことさらに正当のものとして受理した上、情を知らない他の同係員の手により同区長作成名義の同証明書を調製せしめ、かつ同区長の職印を冒捺させて、同証明書を偽造した事実を認定し、これを刑法155条の偽造罪に問擬(もんぎ)したことは、相当といわなければならない
と判示し、有印公文書偽造罪が成立するとしました。