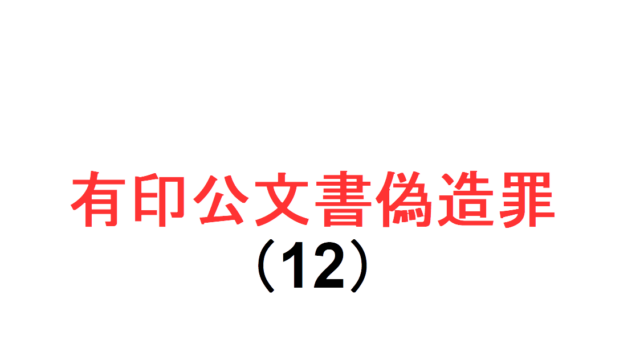有印公文書偽造罪(5)~客体①「『公文書』とは?」「写真やコピーによる文書の写しも文書性が認められる」などを説明
前回の記事の続きです。
この記事では、有印公文書偽造罪(刑法155条1項)を説明します。
有印公文書偽造罪における「公文書」とは?
有印公文書偽造罪の客体は、
- 公務所若しくは公務員の作成すべき文書(公文書)
- 公務所若しくは公務員の作成すべき図画(公図画:こうとが)
です。
この記事では、有印公文書偽造罪の客体である「公文書」について説明します。
「公文書」とは、
公務所、公務員が、その名義をもって、その権限内で、所定の形式に従って作成すべき文書
をいいます。
「文書」とは、
文字又は文字に代わるべき可読的符号を用い、ある程度永続すべき状態において、物体上に記載された意思又は観念の表示のこと
をいいます(大審院判決 明治43年9月30日)。
公文書偽造罪は、私文書偽造罪と異なり、「権利、義務若しくは事実証明に関する文書」であることの要件はない
私文書偽造罪(刑法159条)の「文書」は「権利、義務若しくは事実証明に関する文書」に限定されます。
しかし、公文書偽造罪(刑法155条)の「文書」には、構成要件上そうした限定はありません。
判例(最高裁決定 昭和29年4月15日)は、
- 公文書偽造罪にいう公文書とは、公務所又は公務員がその名義をもってその権限内において所定の形式に従い作成すべき文書を指し、実生活に交渉を有する事項の証明又は権利義務に関する内容を有することを要するものではない
としています。
出勤簿などの「公務所の用に供する文書」は必ずしも公文書ではない
官公署の出勤簿などの「公務所の用に供する文書」は、必ずしも公文書ではなく、そのような文書を偽造しても、公文書偽造罪ではなく、私文書偽造罪が成立する場合があります。
「公務所の用に供する文書」とは、刑法258条の公文書毀棄罪の条文中に記載されており、最高裁判決(昭和38年12月24日)は、
- 刑法258条にいわゆる「公務所の用に供する文書」とは、その作成者、作成の目的等にかかわりなく、現に公務所において使用に供せられ、または使用の目的をもって保管されている文書を総称するものと解すべきである
と判示しています。
大審院判決(昭和9年10月22日)は、
- 村役場備え付けの印鑑簿は、それぞれ独立した私文書である
と判示しています。
写真やコピーによる文書の写しも文書性が認められる
判例によれば、文書は原本に限られるわけではなく、写し(ただし、手書きの写しではなく、写真やコピーによる写しをいう)も、原本と同一の意識内容を保有し、証明文書としてこれと同様の社会的機能と信用性を有するものと認められる限り文書に含まれるとされます。
そのような写しの内容が公務所・公務員が作成すべきものであれば公文書とされます。
この点を判示したのが以下の判例です。
公文書の写真コピーの作成が有印公文書偽造罪にあたるとされた事例です。
裁判所は、
- 行使の目的をもって、虚偽の供託事実を記入した供託書用紙の下方に真正な供託金受領証から切り取った供託官の記名印及び公印押捺部分を接続させ、これを電子複写機で複写する方法により、あたかも、公務員である供託官が職務上作成した真正な供託金受領証を原本として、これを原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を有する写真コピーを作成した所為は、刑法155条1項の公文書偽造罪にあたる
と判示しました。
公文書の電子コピーの作成が有印公文書偽造罪にあたるとされた事例です。
裁判所は、
- 行使の目的をもって、ほしいままに、京都府A工営所長の記名押印のある同所長作成名義の土石採取許可証原本の出願日、許可年月日、採取場所、採取期間等の各欄の記載に改ざんを施したうえ、これを電子複写機で複写する方法により、あたかも真正な右許可証原本を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を備える電子コピーを作成した所為は、刑法155条1項の有印公文書偽造罪にあたる
と判示しました。
広島高裁岡山支部判決(平成8年5月22日)
改ざんした公文書をファクシミリで送信した公文書の写しも公文書となるとしました(詳しくは文書偽造・変造の罪(24)の記事参照)。。
公務所・公務員がその権限により作成すべきものであれば、私法上の法律関係に関するものも公文書に当たる
公務所・公務員がその権限により作成すべきものであれば、公法上のものに限られず、私法上の法律関係に関するものも公文書に当たります。
具体例として、
- 貯金局名義で発行された郵便貯金通帳(当時、郵便事業は国営であった)(最高裁判決 昭和24年4月5日)
- 村長が村有財産の処分に際して作成した領収証(大審院判決 昭和10年12月26日)
が挙げられます。
外部文書だけでなく、内部文書も公文書に当たる
公文書は、官公署外に宛てられた外部文書だけでなく、地方公共団体の内部部局において決済伺いのため作成される稟議書のような内部文書も公文書に当たります。
この点、広島高裁松江支部判決(昭和30年7月13日)は、
- 地方公共団体の会計事務(就中部局における支出)に関して作成される「禀議書」は法規慣例に基き、当然作成すべき書面であるから、その形式および内容の真正につき、法律によって保護を受けるに値し、文書偽造の罪の客体たる公文書に該当する
と判示しています。
職務に関して作成したものではない文書は公文書に当たらない
公務所、公務員が作成したものでも、その職務権限内において職務に関して作成したものといえない文書は有印公文書偽造罪における公文書に該当しません。
例えば、村役場の書記の退職届書は、村役場書記の肩書を用いて作成されても、単に肩書表示の身分を辞退する意思表示であるにすぎず、その身分に基づく職務の執行について作成されたものではないから、公文書とはいえません(大審院判決 大正10年9月24日)。
公務員の肩書を付しても、政党の機関紙である新聞紙に掲載された「祝発展、佐賀県労働基準局長某」という広告文はその公務員名義の事実証明に関する私文書となります(最高裁決定 昭和33年9月16日)。
職務に関して作成したものではない文書でも、一般人をして、公務所・公務員の職務権限内において、その職務に関して作成されたものと信じさせるのに足りる形式、外観を備えているときは、公文書とみられ、公文書偽造罪が成立する
ただし、その文書が、一般人をして、公務所・公務員の職務権限内において、その職務に関して作成されたものと信じさせるのに足りる形式、外観を備えているときは、公務所、公務員の権限に属しない事項に関するものでも、公文書偽造罪の成立に関しては、公文書とみられ、公文書偽造罪が成立します。
これは、公文書としての要件を具備していなくても、一般人が公文書としての要件を具備しているものと誤信せしめられる程度の形式、外観を備えている限り、文書の真正に対する信用を害するに足りるためです。
この点、最高裁判決(昭和28年2月20日)は、作成権限がない大分県議会事務局名義の工事委託書について、
- 偽造公文書が一般人をして公務所または公務員の職務権限内において作成せられたものと信ぜしめるに足る形式外観を具えている以上は、その作成名義者たる公務所または公務員にその権限がない場合においても、刑法155条の偽造公文書というを妨げないものである
と判示しました。
また、東京高裁判決(平成18年10月18日)は、作成権限がない町議会事務局長名義の町議会議事録について、公文書偽造罪の成立を認めています。
文書の作成名義人は必ずしも実在することを要しない
文書の作成名義人は必ずしも実在することを要しません。
判例は、公文書については、私文書と異なり、名義人の実在は不要としています。
例えば、
- 偽造した公文書の作成当時、文書名義人に使った公務員がすでに死亡していた場合(大審院判決 大正元念10月31日)
- 偽造した公文書の作成当時、名義人である公務員が公務員の資格を失っていた場合(大審院判決 大正8年3月30日)
に、形式・外観において一般人に実在の公務所名義の公文書と誤信させるときは公文書偽造罪の成立を認めています。
また、実在しないが、実在する公務所と類似の公務所名義の文書を作成した場合にも、公文書偽造罪の成立を認めています。
例えば、判例は、
- 実在しない「南方派遺隼9145部隊長名義」で軍人身分証明書を作成した場合(大審院判決 昭和19年2月22日)
- 実在しない「司法局別館人権擁護委員会会計課名義」で証明書を作成をした場合(最高裁判決 昭和36年3月30日)
- 実在しない「大阪法務社岸和田支局、津地方法務新聞宇治山田支局名義」で船舶登記証書を作成した場合(最高裁決定 昭和31年7月5日)
に公文書偽造罪の成立を認めています。