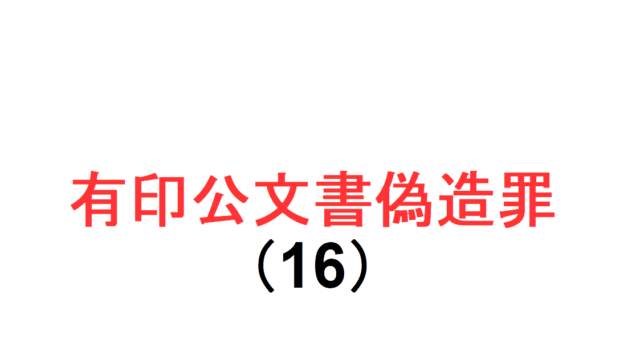有印公文書偽造罪(6)~客体②「『公図画』とは?」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、有印公文書偽造罪(刑法155条1項)を説明します。
有印公文書偽造罪における「公図画」とは?
有印公文書偽造罪の客体は、
- 公務所若しくは公務員の作成すべき文書(公文書)
- 公務所若しくは公務員の作成すべき図画(公図画:こうとが)
です。
この記事では、有印公文書偽造罪の客体である「公図画」について説明します。
「公図画」(こうとが)とは、
公務所、公務員が、その名義をもって、その権限内で、所定の形式に従って作成すべき図画
をいいます。
「図画」にも、有印公文書偽造罪(5)の記事で説明した「文書」の定義がそのまま当てはまります。
ただし、「文書」が発音的符号が用いられているものをいうのに対し、「図画」は象形的符号が用いられているものをいう点に違いがあります。
「公図画」について公文書偽造罪の成立を認めた以下の判例があります。
日本専売公社時代のたばこ「光」の外箱は専売品であることを証明する公図画であるとした判決です。
裁判所は、
- 日本専売公社の製造にかかる製造たばこ「光」の外箱は、刑法第155条第1項にいう「公務所の作るべき図画」にあたる
と判示しました。
土地台帳に付属する地図は法務局の図画であるとした判決です。
裁判所は、
- 本件変造にかかる「大沼郡東尾岐村字限地図」が公務所たる福島地方法務局高田出張所の署名のある公図画であるとした原審の認定判断は相当である
と判示し、有印公文書変造罪(刑法155条2項)が成立するとしました。