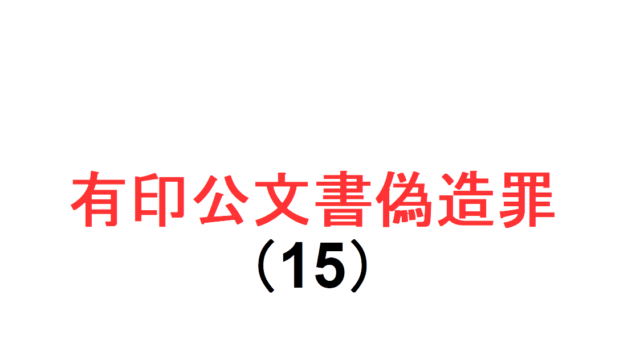有印公文書偽造罪(8)~客体④「一体となっている一つの文書に、複数の公文書や私文書が併存する場合の公文書偽造罪の成立の考え方」「個別文書、全体文書、複合文書の概念」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、有印公文書偽造罪(刑法155条1項)を説明します。
一体となっている一つの文書に、複数の公文書や私文書が併存する場合の公文書偽造罪の成立の考え方
有印公文書偽造罪の客体は、
- 公務所若しくは公務員の作成すべき文書(公文書)
- 公務所若しくは公務員の作成すべき図画(公図画:こうとが)
です。
この記事では、一体となっている一つの文書に、複数の公文書や私文書が併存する場合の公文書偽造罪の成立の考え方を説明します。
一体となっている一つの文書に、複数の公文書が併存している場合
一体となっている一つの文書に、複数の公文書が併存することがあります。
例えば、郵便貯金通帳の受入れ・払戻しの各欄の記載は、それぞれ独立した公文書としての性質を有するので、複数の公文書が併存しているとみられます(大審院判決 昭和7年2月25日)。
※ 郵政民営化前は、郵便貯金通帳は公文書であった
郵便貯金通帳の各欄は、その表紙の記載と相まって意味を有するものなので、表紙の記載を改ざんする行為は、同時に、各欄の記載に対する偽造ともみられます。
郵便貯金通帳の表紙を偽造した場合(文書偽造罪が1個成立)は、同時に、郵便貯金通帳の受入れ・払戻しの各欄の偽造したものとなり(さらに文書偽造罪が複数成立)、各文書偽造罪は観念的競合の関係になります。
一体となっている一つの文書に、公文書と私文書が併存している場合
一体となっている一つの文書に、公文書と私文書とが、併存、合体していることがあります。
例えば、かつての印鑑証明は、私人の証明願いの用紙に、公務員が、奥書として、その事実があったことを証明する旨の文書を加え、署名・押印しており、この奥書部分が独立した公文書となるというのが判例です(大審院判決 明治43年6月23日)。
この場合に、私人が記入する印鑑証明の証明願い部分と、公務員が記入する証明部分の双方を偽造すれば、私文書偽造罪と公文書偽造罪の二罪が成立します。
上記私文書偽造罪と公文書偽造罪の関係は、場合により、観念的競合となり(大審院判決 明治43年6月23日)、あるいは私文書偽造罪と公文書偽造罪との牽連犯となります(大審院判決 昭和2年11月1日)。
【参考】個別文書、全体文書、複合文書の概念
個別文書、全体文書、複合文書の概念を説明します。
一般的な個別・独立した文書を「個別文書」といいます。
「個別文書」に対し、個々の独立した文書的表示内容を多数包含しながらも、その全体が1つの文書をなしているものを「全体文書」といいます。
「全体文書」の例として、
- 商業帳簿
- 預貯金通帳
が挙げられます。
「全体文書」に対して、1通の用紙又は密接に結合した数通の用紙上に2つ以上の種類の異なった文書が併存するものを「複合文書」といいます。
公文書と私文書の複合文書の例として、
- 「印鑑証明」 … 印鑑証明願部分(私文書)と、奥書として市町村長の印鑑証明書が示されている部分(公文書)が公文書と私文書の複合文書となる
- 「交通違反の取締りに当たる警察官が作成する交通事件原票」 … 交通事件原票は警察が作成する公文書であり、「本件違反をしたことは相違ない、事情は次のとおりである」旨の不動文字が記載されその下に被検挙者の署名欄が設けられた部分については私文書であり、公文書と私文書の複合文書となる
が挙げられます。