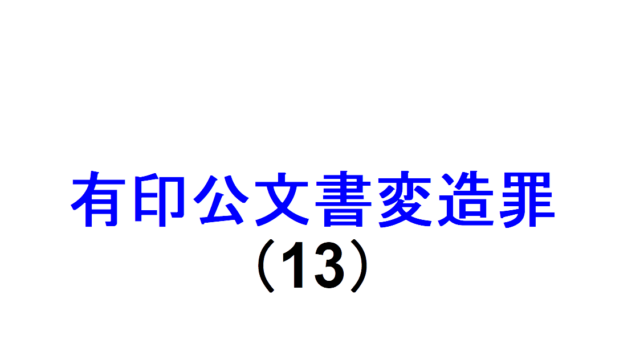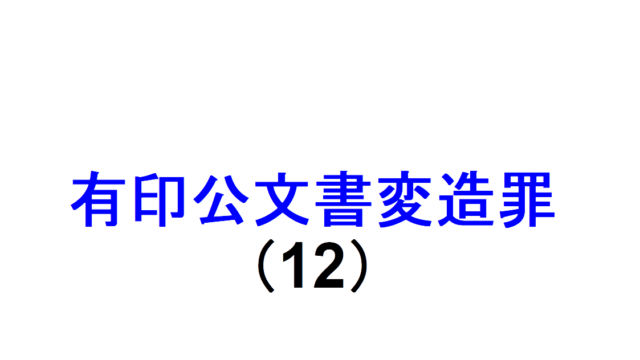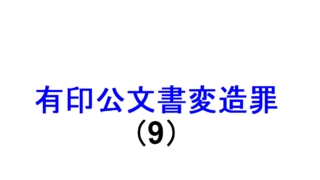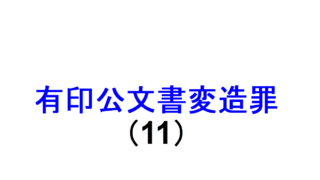有印公文書変造罪(10)~「『行使の目的』とは?」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、有印公文書変造罪(刑法155条2項)について説明します。
「行使の目的」とは?
有印公文書変造罪は、刑法155条2項に規定があり、
第1項 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する
第2項 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする
と規定されます。
有印公文書変造罪は、第1項の有印公文書偽造罪と同様に、「行使の目的」をもってなされることを要します。
偽造・変造罪は目的犯であり、偽造・変造文書の作成についての認識があることに加えて、
行使の目的という主観的違法要素
の存在が必要とされています。
偽造・変造文書や虚偽文書は、人が認識可能な状態に置かれることによって、初めて公共の信用を害することになるので、「行使の目的」は法益侵害結果を主観的要素の形で取り込むものとされます。
「行使の目的」とは、
他人をして偽造文書・虚偽文書を真正・真実な文書と誤信させようとする目的
をいいます。
「行使の目的」の「行使」とは、
偽造文書・図画(とが)を真正な文書・図画として、虚偽文書・図画を内容真実な文書・図画として「使用」すること
をいいます。
「使用」とは、
人に文書の内容を認識させ、又は、認識可能な状態に置くこと
をいいます(最高裁判決 昭和44年6月18日)。
利害関係人であれば、文書の名宛人に使用する目的に限らず、広く効用に役立たせる目的があれば足り、自ら使用する目的か否かを問いません。
文書の本来の用法に従って当該文書を使用する目的でなくとも、何人かによって真正・真実な文書として誤信される危険があることを意識している以上、行使の目的があるものといえます。
行使の目的は、未必的なもので足ります。
- 文書偽造罪における行使の目的は、必ずしもその本来の用法に従ってこれを真正なものとして使用することに限るものではなく、真正な文書としてその効用に役立たせる目的があれば足りるものである
としています。
裁判例
有印公文書変造罪において、「行使の目的」ついて言及した以下の裁判例があります。
有印公文書変造罪において「行使の目的」があるとされた事例です。
裁判所は、
- 変造に係る原本自体を他人に対し行使する目的がなかったとしても、その原本と同一作成名義、内容でその原本自体の存在に取引上疑問を抱かせない、いわゆる写真コピーを作成することにより、これを介して右改ざんに係る原本を真正な文書として他人に対し主張しようとする意図がある以上、行使の目的を持って原本を変造したものと認めることができる
としました。