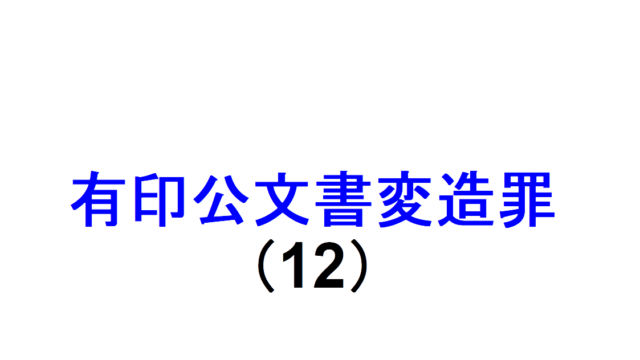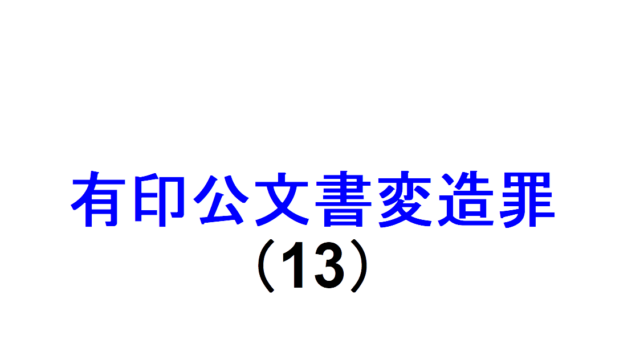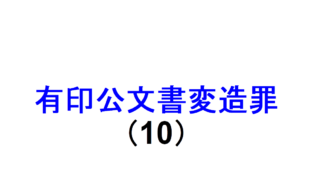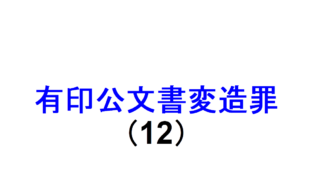有印公文書変造罪(11)~「変造の方法」「文書変造罪と文書毀棄罪の区別」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、有印公文書変造罪(刑法155条2項)について説明します。
変造の方法
文書の変造は、
文書の作成名義人でない者が、真正に成立した文書の内容に変更を加えることで、非本質的部分に不法な変更を加え、新たな証明力を有する文書を作り出すこと
です。
(なお、「文書の変造」に対し、文書の本質的部分に変更を加えて、新たな証明力を有する文書を作り出す行為は、「文書の偽造」となります)
文書の変造の方法に制限はありません。
文書の変造といえるためには、文書の非本質的部分に変更を加え、既存の文書に新たな証明力を作り出すものでなければなりません。
本質的か非本質的かの区別は、変更前のものと文書として同一性を有するかどうかを基準とし、同一性を有する場合は非本質的部分の変更としての変造に当たると解されています。
おおむね、文書の種類・形式が文書の本質的部分に対応し、内容のうち余り重要でない部分が非本質的部分に当たるといえるとされます。
文書の本質的部分に変更を加え、既存文書と同一性を欠く新たな文書を作出した場合には、文書の変造ではなく、偽造となります。
文書変造罪と文書毀棄罪の区別
変造は、文書の内容を変更して新たな証明力を作出することをいうので、新たな証明力を作出しないで、その文書の効力の全部を消滅させるのは、文書毀棄(刑法258条、刑法259条)となります。
文書変造罪と文書毀棄罪のどちらが成立するかが争点となった裁判例として以下のものがあります。
釧路地裁帯広支部判決(昭和35年11月14日)
運転免許証に貼付してある人物写真の眼の部分を剥ぎとり、その写真が何人を撮影したものであるかを不明瞭ならしめた行為は、私用文書毀棄罪(刑法259条)に当たり、公文書変造罪にも当たらないとしました。