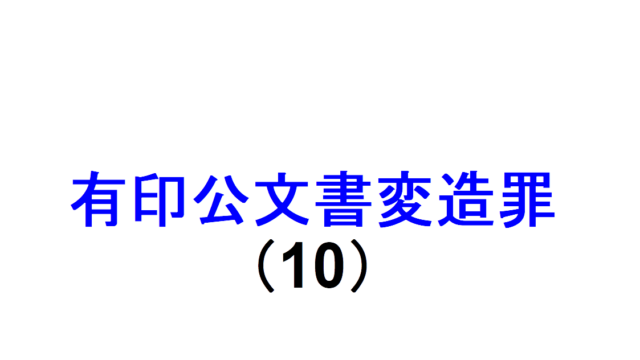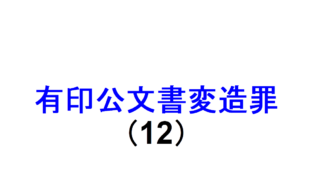有印公文書変造罪(13)~「偽造・変造と擬律」「電磁的記録の偽造・変造は、電事的記録不正作出罪で処罰される」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、有印公文書変造罪(刑法155条2項)について説明します。
偽造・変造と擬律
文書の偽造と変造とは罪質を同じくし、判決において、そのいずれに当たるかの判断を誤っても、処断刑の範囲も異ならないことから、上告審において判決を破棄する理由とはなりません。
事例として、公文書の内容に改ざんを加えた上そのコピーを作成した場合についての最高裁決定(昭和61年6月27日)は、
- 文書の変造ではなく文書の偽造に当たると解すべき場合に、被告人の行為が有印公文書変造罪に当たるとした第1審判決及びこれを是認した原判決は、刑法155条の解釈を誤ったものというべきであるが、有印公文書の偽造とその変造とは、その罪質及び法定刑を同じくし、その行使もともに同法158条1項に当たりその法定刑も同じであるから、右の誤りは、判決に影響を及ぼさない
としました。
電磁的記録の偽造・変造は、電事的記録不正作出罪で処罰される
「文書」ではなく、「電磁的記録」の偽造・変造は、電事的記録不正作出罪で処罰されます。
電事的記録不正作出罪(刑法161条の2)は、人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者を処罰するものです。
電事的記録不正作出罪は、昭和62年の改正により供用罪とともに新設されたもので、情報化社会の著しい進展に伴い、文書偽造の罪では賄いきれない有害行為を立法的に解決し、もって電磁的記録に対する公共の信用の保護を図る罪とされます。
ここでは、電磁的記録に関する偽造に類似した行為は「不正作出」という単一の概念の下に理解されており、偽造と変造という区別が存在しません。
これは、文書と異なり、その作成過程に複数の者が関わることや、一定のシステムの下で用いられることにより本来の証明機能を果たすことなどから、文書と同様の作成名義を観念することが困難であるため、偽造、変造、虚偽作成などの概念の代わりに「不正作出」という概念が用いられているものです。