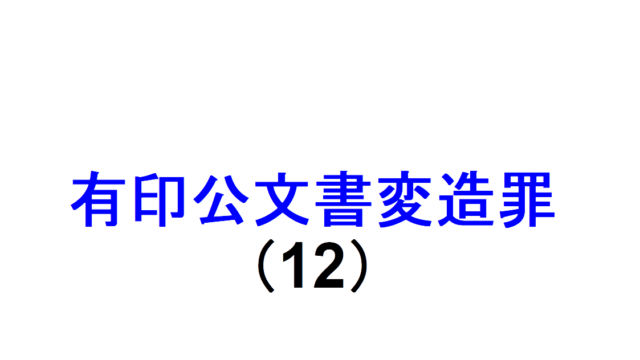有印公文書変造罪(3)~客体①「文書変造の客体の概念」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、有印公文書変造罪(刑法155条2項)について説明します。
変造の客体(すでに成立している他人名義の真正文書)
文書変造の客体は、
他人名義の文書、つまり、すでに成立している他人名義の真正文書
でなければなりません。
※ 真正文書とは、「文書の名義人」と「文書の作成者」が一致している文書(作成者の意思に基づいて作成された文書)をいいます。
権限がない者が未完成の文書を外形的に完成させる行為は偽造であって変造ではない
文書変造の客体は、「他人名義の文書、つまり、すでに成立している他人名義の真正文書」です。
したがって、権限がない者が未完成の文書を外形的に完成させる行為は偽造であって変造ではありません。
大審院判決(昭和14年7月3日)は、輸出用綿糸購入票の記載事項の一部(所属組合名、工場名、購入委託者名等の記載)が欠け、作成名義人たる日本織物工業組合連合会の記名捺印がなされている場合につき、文書を偽造したものとしており、変造とはしていません。
最高裁判決(昭和24年9月1日)は、被告人と原審相被告人Aとが転出証明書の偽造を共謀し、偽造文書の素材に供する目的で氏名住所不詳者から転出証明書用紙を買い受け、これに年月日、氏名、数量、転出先等を記載して本件転出証明書の偽造を完成した事案について、文書変造であるとの主張に対し、「被告人らが買入れた転出証明書用紙にすでに一部偽造の箇所があったにしても未完成部分にさらに虚偽の事実を記入し偽造文書として通用し得る程度に偽造を完成したのは文書偽造の範疇に属するものと解するを相当とする」としています。