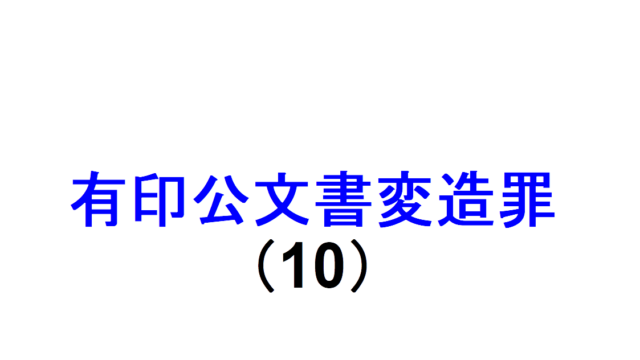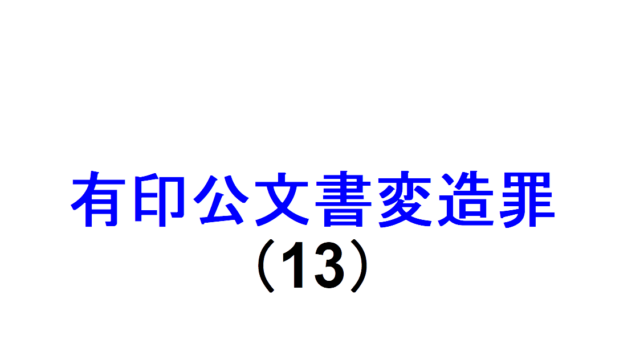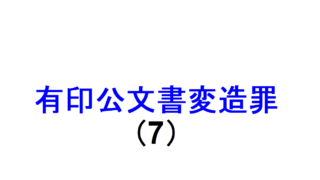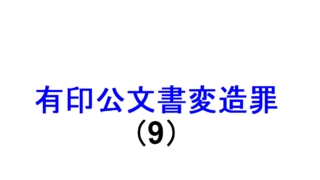有印公文書変造罪(8)~「変造の種類(『広義の変造』と『狭義の変造』)」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、有印公文書変造罪(刑法155条2項)について説明します。
変造の種類(「広義の変造」と「狭義の変造」)
「変造」の概念は、
- 広義の変造
- 狭義の変造
の2つの考え方があります。
以下でそれぞれの考え方について説明します。
①「広義の変造」の概念の考え方
広義の変造の概念における「変造」は、
真正に成立した文書(真正文書)の非本質的部分に不法に変更を加え、新たな証明力を作り出すこと
をいいます。
※ 真正文書とは、「文書の名義人」と「文書の作成者」が一致している文書(作成者の意思に基づいて作成された文書)をいいます。
広義の変造においては、不真正文書の非本質的部分に変更を加えただけでは、文書に対する信用を新たに害するものでないので、変造にはならなりません。
※ 不真正文書とは、「文書の名義人」と「文書の作成者」が一致していない文書(作成権限がない者が他人の名義で作成した文書や、作成権限がある者が虚偽の内容で作成した文書)をいいます。
有形変造と無形変造
文書偽造罪の構成要件として規定されている広義の偽造の中には、
- 有形偽造(権限なく他人名義の文書を作成すること)
- 無形偽造(文書の作成権限を有する者が内容虚偽の文書を作成すること、虚偽文書作成ともいう)
があります。
同様に、文書変造罪の構成要件として規定されている広義の変造の中には、有形偽造と無形偽造に対応した
- 有形変造(変造が作成名義人でない者(作成権限がない者)によってなされる場合)
- 無形変造(変造が作成名義人(作成権限がある者)によってなされる場合)
があります。
無形偽造としての無形変造は、
- 文書を作成する権限を有する者が、既存の自己名義の文書の非本質的部分に変更を加え、新たな証明力を作り出すこと
- 作成権限を有する者が既存の文書を虚偽の内容に変更すること
をいいます。
無形変造については、刑法は公文書の場合のみ例外的に処罰の対象としています(刑法156条)。
偽造文書と虚偽文書
有形偽造・変造によって作成された文書を
偽造文書
といいます。
無形偽造・変造によって作出された文書を
虚偽文書
といます。
②「狭義の変造」の概念の考え方
狭義の変造の概念における「変造」とは、
真正に成立した文書(既存の真正文書)に変更を加えること
をいいます。
有形変造と無形変造
作成権限がない者(作成名義人でない者)が行う場合を
有形変造
と呼びます。
作成権限がある者(作成名義人)が行う場合を
無形変造
と呼びます。
一般に「変造」と呼ばれるのは、有形変造のことです。
未完成の文書に手を加えて完成させる行為は、偽造にはなっても、変造にはならない
未完成の文書に手を加えて完成させる行為は、偽造にはなっても、変造にはなりません。
文書の本質的な部分に変更を加え、既存文書と同一性を失うにいたれば、変造ではなく、偽造又は虚偽文書作成となる
通常、文書の変造は、有形偽造の一種としての変造であり、
作成名義人でない者が、真正に成立した文書の内容に変更を加えること
をいい、
非本質的部分に不法な変更を加え、新たな証明力を有する文書を作り出すこと
に限られます。
文書の本質的な部分に変更を加え、既存文書と同一性を失うにいたれば、変造ではなく、偽造又は虚偽文書作成となります。
完全に失効した文書又は無効となった文書に加工を加えて新たな文書を作出することは、変造ではなく偽造となる
完全に失効した文書又は無効となった文書に加工を加えて新たな文書を作出することは、変造ではなく偽造となります。
文書の一部を削除した場合、効用の全部又は一部を喪失させただけで、新たな証明力ある文書を作出していない場合は、文書の「毀棄」となる
文書の一部を削除した場合、効用の全部又は一部を喪失させただけで、新たな証明力ある文書を作出していない場合は、文書の「毀棄」となり、新たな証明力を作出したときは「変造」となります。
「毀棄」は文書の効力を毀滅させるにとどまるのに対し、「変造」はそれにより新たな証明力を作り出す点で異なります。
虚偽の内容の文書のコピーは、変造ではなく偽造となる
虚偽の内容の文書のコピーを作成すれば文書偽造罪が成立します。
したがって、真正文書に加えた変更の程度が小さくとも、文書のコピーを作成すれば原本と別の文書が作出されることになり、変造ではなく偽造となります。
最高裁決定(昭和61年6月27日)は、行使の目的をもって、ほしいままに、営林署長の記名押印がある売買契約書の売買代金欄等の記載に改ざんを施すなどした上、これを複写機械で複写する方法により、あたかも真正な売買契約書を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を備えるコピーを作成した所為は、その改ざんが原本自体にされたのであれば未だ文書の変造の範瞬に属するとみられる程度にとどまっているとしても、155条1項の有印公文書偽造罪に当たるとしています。