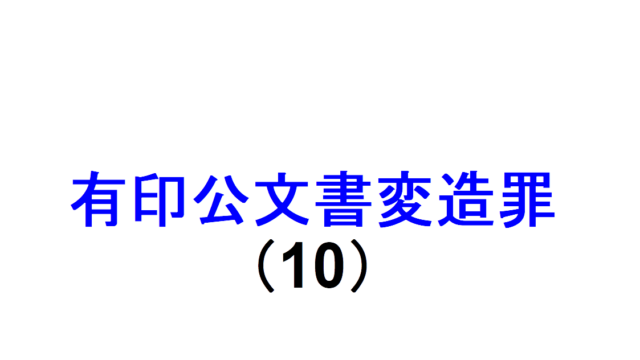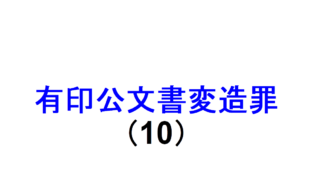有印公文書変造罪(9)~「偽造と変造の区別」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、有印公文書変造罪(刑法155条2項)について説明します。
偽造と変造の区別
「文書の変造」は、
作成名義人でない者が、真正に成立した文書の内容に変更を加えることで、非本質的部分に不法な変更を加え、新たな証明力を有する文書を作り出すこと
に限られます。
「文書の変造」に対し、文書の本質的部分に変更を加えて、新たな証明力を有する文書を作り出す行為は、「文書の偽造」となります。
したがって、
- 何が文書の本質的部分か
- 全く別個の新たな証明力を作り出したかどうか
が問題となり、文書の本質的部分に変更を加えたり、全く別個の新たな証明力を作り出したりした場合には、「文書の変造」ではなく「文書の偽造」ということになります。
参考となる以下の判例があります。
大審院判決(大正3年11月7日)
他人に下付された外国旅行券の人名及び渡航地の変更が偽造とされた事例です。
裁判官は、
- 既存の正当なる文書中、作成名義若しくはその他重要なる点を変更しために、その変更前の文書と全然別個独立なるものと為すときは、文書の偽造にして変造に非ず
- 他人に下付せられたる外国旅行券中、その下付の人名及び渡航地に変更を加えたる所為は、旅行券の偽造をもって論ずべきものとす
と判示しました。
以下で、
- 文書の変造とされた判例・裁判例
- 文書の偽造とされた判例・裁判例
を挙げます。
① 文書の変造とされた判例・裁判例
文書の変造とされた判例・裁判例として、以下のものがあります。
なお、「文書の変造」か「文書の偽造」かは、微妙な判断となる事例も少なくありません。
しかしながら、偽造と変造は、同一構成要件の内部における相違であり(例えば、有印公文書偽造罪・変造罪は両方とも刑法155条内に規定されている)、その限界が多少曖昧であっても大きな不都合は生じないとも解されています。
売買契約書の売買代金欄の改ざんは変造になるとした事例です。
この判例は変造についての判例ではなく、裁判官は、
- A 営林署長の記名押印がある売買契約書2通の各売買代金欄等の記載に改ざんを施すなどしたうえ、これらを複写機械で複写する方法により、あたかも真正な右各売買契約書を原形どおりに正確に複写したかのような形式、外観を有するコピー2通を作成したというのであるところ、これらコピーは、原本と同様の社会的機能と信用性を有すると認められるから、被告人の右各所為は、いずれも刑法155条1項の有印公文書偽造罪に当たると解するのが相当である
としたものですが、
- 公文書の改ざんコピーを作成することは、たとえ、その改ざんが、公文書の原本自体になされたのであれば未だ文書の変造の範ちゅうに属するとみられる程度にとどまっているとしても…
とも述べており、売買契約書の売買代金欄等の記載を改ざんする行為は変造にとどまることを前提とした決定となっています。
大審院判決(明治44年11月9日)
有効な借用証書の金額のそばに別個の金額を記入することは変造になるとした事例です。
有効な借用証書の金額のそばに別個の金額を記入した場合について、有効な証書の記載を利用して本来の証明力のほかに新たなる証明力を生じさせたもので、証書の効力に変更を来すにすぎないとして、変造であるとしました。
大審院判決(昭和11年4月24日)
私立大学の学生証に記載されている学生の氏名を抹消し、別人の氏名を記入した場合について、文書変造罪の成立を認めました。
東京高裁判決(平成22年9月30日)
勾留状の勾留期間延長欄中の日付の数字の改ざんは変造になるとした事例です。
勾留状のうちの裁判官記載に係る勾留期間の延長欄中の「延長期間平成21年11月9日まで」の「9」の字をボールペンで「8」に書き換え、被告人の勾留延長期間が同月8日までであるように改ざんした事案です。
裁判官は、
- 勾留延長の裁判書は、同じく勾留状に記載されてはいても、勾留の裁判書自体とは別個独立に保護すべき公共的信用性を有するものと解すべきである
- そうすると、被告人の改ざん行為は、勾留延長の裁判書の変造というべきである
と判示しました。
岡山地裁倉敷支部判決(平成18年8月25日)
預金通帳の日付欄、お預り金額欄、差引残高(円)欄の改ざんは変造になるとした事例です。
裁判所は、
- 既存の預金通帳に、ワードプロセッサーを使用して、同通帳の日付欄に「17.05.27」、同お預り金額(円)欄に「*16,616,424」、同差引残高(円)欄に「*16,617,424」とそれぞれ印字した行為が、預金通帳の変造である
としました。
岡山地裁判決(平成2年4月25日)
現況調査報告書写しの土地占有者欄、所有者欄の改ざんは変造になるとした事例です。
※ 現況調査報告書…裁判所から派遣された執行官が実際に競売物件を訪れ、調査した結果をまとめた書類
裁判所は、
- 執行官作成名義の現況調査報告書写し(複写機によるコピー)の、土地占有者欄及び当事者目録の所有者欄に各記載されている自己の氏名の直近余白に『△△四代目〇〇会××組」のゴム印を押捺し、執行官が、現況調査報告書中に競売物件の所有者兼占有者である被告人が△△四代目〇〇会××組組員である旨を記載したかのような外観を作出して公文書である現況調査報告書写しの変造を遂げた
とし、公文書偽造罪が成立するとしました。
名古屋地裁判決(昭和54年4月27日)
健康保険被保険者証の資格取得年月日欄、交付年月日欄の改ざんは変造になるとした事例です。
健康保険被保険者証の「資格取得年月日欄に記載されていた『昭和53年4月28日』の『5』をカッターナイフ等で削り消し、その跡へ『4』とゴム印で押捺し、交付年月日欄に記載されていた『昭和53年5月10日』の『3』を右同様の方法で消し、その跡へ『0』とゴム印を押捺して資格取得年月日を昭和43年4月28日に、交付年月日を昭和50年5月10日に変更した行為を、健康保険被保険者証の変造としました。
福井地裁判決(昭和50年2月25日)
運転免許証の免許条件等の欄の改ざんは変造になるとした事例です。
福井県公安委員会作成の同委員会の記名押印のある被告人に対する普通自動車及び自動二輪運転免許証1通の免許条件等の欄に記載されていた「審査(普一)未済」の文字をタバコの火で焼いて抹消し、あたかも右条件が付されていない免許証であるかのように改ざんした行為を普通自動車運転免許証1通の変造としました。
奈良地裁葛城支部判決(昭和48年11月13日)
自動車検査証中の「自動車登録番号又は車両番号」欄の改ざんは変造になるとした事例です。
車両に備え付けてあった奈良県知事交付にかかる自動車検査証中、「自動車登録番号又は車両番号」欄に記載してあった「ナ六八八一」の部分を水につけて消し、同部分に黒のボールペンを使用して「サ八六九九」と記入した行為を、同知事の署名のある同知事作成名義の公文書1通の変造としたとしました。
名古屋地裁判決(昭和47年6月16日)
運転免許証の免許種類欄の改ざんは変造になるとした事例です。
普通自動車及び自動二輪車各運転免許が真正に表示された基本の運転免許証につき、その免許種類欄中、大型自動車免許の有無を示す大型欄に記載された「0」の文字を「1」に改ざんし、よって普通自動車および自動二輪車各免許に加え、大型自動車免許も表示されているかの如く外観を整えた行為が、文書の偽造となるか変造となるか」について、裁判所は、
- 社会的通念を考慮すると、異種複数の免許が表示された免許証も、文書偽造罪における文書としては1個であると解するのが相当であること
- 本件の如く、既存の免許の表示に加え、異種の免許を併記することは、免許証の内容を全く改変させるものではなく、既存の内容を拡張的に変更させるものにすぎず、同一性を失うものではなく、新たに文書を作成したものではないことからすると、本件行為は、権限なく免許証に変更を加えたものであって、文書の変造に当たる
としました。
大阪高裁判決(昭和43年6月10日)
賃貸借契約証書中の賃貸料に関する条項の改ざんは変造になるとした事例です。
賃貸借契約証書中の賃貸料に関する条項の末尾に「賃貸料は2年間毎に更新する事」と書き加えたことを私文書変造罪に該当するとした原判決を是認しました。
裁判所は、
- 当該文言は、少くとも事実上、賃貸人並びに賃借人双方の間の賃貸料に関する権利義務について変動を生じさせる可能性を有するものとして私文書変造罪を構成するというべきである
としました。
東京地裁判決(昭和41年12月12日)
診断書の加療期間の改ざんは変造になるとした事例です。
医師作成の診断書の「約一週間」とあるのを、「一」の字に、万年筆で「二」を書き加えて、「約三週間」と改ざんした行為について、加療期間がさらに約3週間を要する旨を証明する診断書を変造したとしました。
広島地裁福山支部判決(昭和41年5月11日)
自動車運転免許証の自動車等の限定欄の改ざんは変造になるとした事例です。
裁判所は、
- 被告人は、昭和38年7月1日広島県公安委員会から軽自動車運転免許証の交付を受けていたところ、右免許証の自動車等の限定欄に「軽自動車は四輪及び三輪の車以外の車に限る」との限定が記載してあるため、軽二輪自動車しか運転できないことに不便を感じ、同40年8月頃、被告人の肩書住居地で、行使の目的をもつて、広島県公安委員会の作成名義で、同委員会の記名及び押印のある前記自動車運転免許証の自動車等の限定欄に、かねて所携の福山交通安全協会発行の不透明な用紙でできている準会員証を、ほしいままにのりでそのほぼ全面に貼りつげ容易に剥がれないようにして前記限定欄の文言を隠ぺいし、もって、既存の運転免許証を利用し、自己が自動車等の限定のない軽自動車免許を取得したような外観を呈する自動車運転免許証1通を変造した
としました。
東京地裁判決(昭和37年8月10日)
外国人登録証明書の居住地の地番欄の改ざんは変造になるとした事例です。
裁判所は、
- 東京都新宿区長の公印がある同区長発行にかかる自己の外国人登録証明書の居住地の地番欄の「東京都新宿区a町bのc」なる記載をインクで斜線を引いて削除し、その上部に右事務室にあった右会社のゴム印を押捺して「横浜市鶴見区d通りfのg」と記し、もって自己の居住地の表示を改ざんして有印公文書である右外国人登録証明書1通を変造した上、同37年5月21日、都内新宿区戸塚町2丁目191番地戸塚警察署において、警察官Aに対し、右証明書を真正なものとして呈示して行使したとした
とし、有印公文書変造罪、変造有印公文書行使罪が成立するとしました。
和歌山地裁判決(昭和35年1月11日)
町長から税務署長宛に送付された通知書の相続開始年月日の改ざんは変造になるとした事例です。
裁判所は、
- 昭和31年6月25日頃、a県b郡C町所在のC税務署において、行使の目的をもつて、かねて同県d郡e町長から右C税務署長宛に送付されてあった同30年10月26日付けAに関する相続税法第58条による通知書の記載のうち、Aの死亡による相続開始年月日として「昭和30年7月11日』とあるを、ほしいままにペンで「7」を抹消して「10」と書き直して右年月日を「昭和30年10月11日」と変更し、もつて右e町長B作成名義の右公文書を変造したうえ、同日同税務署において、これを真正に成立したもののように装ってC及びDの相続税申告書及び被告人起案の申告是認決議書に添付して同税務署長に提出して行使したものである
としました。
② 文書の偽造とされた判例・裁判例
自動車運転免許証の氏名欄等の改変は偽造になるとした事例です。
裁判所は、
- 被告人は昭和34年12月8日付け神奈川県公安委員会がAが発行した小型自動四輪運輪免許証1通をほしいままに、同免許証の氏名欄の「A」、生年月日欄の「大正15・11・19」、本籍欄の「栃木県真岡市ab」、住居欄の「c町de」の各記載部分をインク消しで抹消し、その該当欄に氏名「B」、生年月日「昭和11・5 ・14」、本籍「神奈川県中郡c町fJ、住居「c町gh」と、それぞれ万年筆で記入し、さらに写真欄のAの写真を剥ぎ、自己の写真に鉄筆を用いて「神奈川県」の打ち出し印が押された如く型をつけたうえ、これを同欄に貼りつけ、神奈川県公安委員会の記名押印ある自己宛の小型自動四輪運転免許証1通を作成した
として、有印公文書偽造罪の成立を認めました。
自動車運転免許証の写真、生年月日欄の改変は偽造になるとした事例です。
裁判所は、
- 特定人に交付された自動車運転免許証に貼付しある写真及びその人の生年月日の記載は、当該免許証の内容にして重要事項に属するのであるから、右写真をほしいままに剥ぎとり、その特定人と異なる他人の写真を貼り代え、生年月日欄の数字を改ざんし、全く別個の新たな免許証としたるときは、公文書偽造罪が成立すると解すべきである
と判示しました。
外国人登録証明書に貼付してある写真の張り代えは偽造になるとした事例です。
裁判所は、
- 特定人のために発行された証明書に貼付しある写真をほしいままに剥ぎとり、その特定人と異なる他人の写真を貼り代え、全く別個の新たなる証明書としたるときは、公文書偽造罪が成立すると解すべきである
と判示しました。
一部偽造の箇所のある転出証明書用紙の改変は偽造になるとした事例です。
- 被告人らが買入れた転出証明書用紙にすでに一部偽造の箇所があつたにしても、未完成部分にさらに虚偽の事実を記入し偽造文書として通用し得る程度に偽造を完成したのは文書偽造の範疇に属するものと解するを相当とする
- しかるに、所論のごとく文書変造を認めんとするには、真正に成立した文書を基本とすべきであるという点から見ても、所論の見解の正当にあらざることを知るに足るであろう
と判示しました。
村長の記名捺印のある家庭用米穀配給通帳に記載してある世帯主の姓名の名の部分の改変は偽造になるとした事例です。
裁判所は、
- 被告人は、A村村長Bの記名捺印ある世帯主被告人の家庭用米穀配給通帳中に、「世帯主、CCXX」と記載してあったその「××」の部分を指先ですり消し、そのところにインキ等を使って、亡弟の名「△△」の字を書き込み、あたかも世帯主〇〇△△に交付せられた通帳のように改ざんしたというのである
- およそ、家庭用米穀配給通帳は各世帯ごとに交付せられるものであって、右通帳における世帯主の氏名の記載はその通帳を特定するためには極めて重要な記載であって、世帯主甲名義の通帳と同乙名義の通帳とは、たとえ通帳自体は同一物が利用せられ、従ってその通帳の作成名義者は同一であっても、全く別個の通帳と認めざるを得ない
- されば、原判決が前示被告人の所為をもって村長Bの作成にかかる世帯主被告人名義の通帳を利用して世帯主〇〇△△名義の新なる通帳を作成したものと解し、これを公文書偽造罪に問擬(もんぎ)したのは正当であって、右は公文書変造の罪にあたるものであると主張する論旨はあやまりである
と判示しました。
岡山地裁判決(平成25年8月28日)
損害賠償請求訴訟に関する判決書に関し、判決言渡日、事件番号、被告の住居地及び氏名について虚偽の文言を記載した紙片を貼り付け複合複写機を用いて複写した行為が偽造に当たるとした事例です。
裁判所は、
- 検察官は、判示第22の事実について、主位的に有印公文書変造、同行使罪に、予備的に有印公文書偽造、同行使罪に該当するとして公訴事実を構成する
- 公文書の改ざんコピーを作成することは、たとえ、その改ざんが、公文書それ自体になされたのであれば未だ文書の変造の範ちゅうに属すると見られる程度にとどまっているとしても、もとの文書とは別個の文書を作り出すのであるから、文書の変造ではなく、文書の偽造に当たるものと解すべきである
- したがって、主位的訴因の有印公文書変造、同行使罪は成立せず、判示のとおり、予備的訴因である有印公文書偽造同行使罪が成立する
と判示しました。
東京地裁判決(平成25年7月9日)
預金通帳の取引履歴の改変は偽造になるとした事例です。
普通預金通帳の写しを切り貼りしてその内容をスキャナーでパーソナルコンピュータに読み込んだ上、画像加エソフトを用いて画像加工を行い、「年月日」「お取引内容」「お支払金額(円)」「お預かり金額(円)」「差引残高(円)」につき虚偽の内容を記載した同通帳写しを作成して、同通帳の取引履歴写しを偽造したとした行為について、裁判所は、
- 検察官は、預金通帳の各欄に虚偽内容を記載したコピーを作成した被告人の行為が無印私文書の変造に該当するとして訴訟している
- しかし、預金通帳の取引履歴は、表紙及び表紙裏の記載によって証明される預金ロ座の存在を前提に、各葉に記載される各取引番号ごとに個別の取引内容及びその時点の預金残高を記録する独立した証明文書である
- そして、本件においては、存在する原本に改ざんを加えたのではなく、原本としては存在しない内容の別個の文書(文書の体裁により金融機関が作成したと推認させるもの)を無権限で作り出していること、また、上記各行における取引の有無や残高の金額は、この証明文書としての意見内容の基本的な事項であることからすれば、本件における被告人の行為は、各取引履歴欄ごとに文書の偽造に該当するというべきである
と判示しました。
神戸地裁判決(昭和43年7月9日)
自動車運転免許証の写真の改変は偽造になるとした事例です。
公安委員会の記名押印のあるAに対する第一種普通運転免許証の免許事項欄が透明のビニール製被覆で覆ってあるのを利用し、かねて軽便カミソリで切り開いてあったビニール製被覆の下端部より自己の写真を挿入して免許証の写真欄に貼付してあった共犯者の写真の上に重ね合わせ、あたかも自己が当該運転免許証の交付を受けたような外観を整えた行為について、公安委員会作成名義の自動車運転免許証1通の偽造を認めました。
県知事の記名押印のある軽自動車届出済証の車名欄の改変は偽造になるとした事例です。
県知事作成にかかる同知事の記名押印のあるAの軽自動車届出済証の車名欄に「シルバービジヨン」とあるのをインク消しで消して、ペンで「ジエツト」と記入し、もって同知事の記名押印を使用して同知事の作成すべきAの軽自動車ジエツトの届出済証1通を作成した事案です。
裁判所は、
- 従前届出のものと異なる新たな軽自動車につきその届出済証を作成したものであって、その作成名義については従前のものをそのまま使用した場合であっても、全く新たな軽自動車届出済証を作出した以上これは変造ではなく、偽造である
としました。
納税証明書の重要な記載部分に変更を加えた行為について、公文書偽造罪が成立するとした事例です。
すでに甲税務署から交付を受けて所持していた同署長大蔵事務官A名義のBの昭和29年度分の本税納付税額が金2万3000円であることの納税証明書を使用してBに関する部分をすべて書きかえ、有限会社C(代表取締役D)の昭和29年度の本税納付税額23万800円である旨の同署長名義の納税証明書とした事案です。
裁判所は、
- 文書の変造というのは権限なしに真正な他人名義の文書に変更を加えることであるが、その文書の本質的な部分に変更を加えて別個のあらたな文書が作り出されるときは、もはや変造の域を脱し偽造と解さねばならないこと論を侯たないところである
とした上で、
- 納税証明書の作成名義に手が加えられておらず同じであるけれども、その証明すべき内容が前後で全く異なっており、文書の持つ重要な部分である証明の対象が全く別人となっているとして、これはもはや別個の新たな納税証明書の作出といえ、変造ではなく偽造である
としました。
東京高裁判決(昭和30年11月12日)
自動車運転免許証の免許の種類等に新たな記載をし、全く別人の写真の貼り替る行為は偽造になるとした事例です。
裁判所は、
- 文書偽造罪は他人の作成名義を偽り、新たに文書を作成した場合にのみ成立するものではなく、たとえ既存の真正なる文書を変更する場合であつても、その重要なる部分を変更し、そのため変更前の文書とは別異の証明力を具有する文書となすときは変造をもって論ずべきではなく、偽造であると解するのが相当である
とした上で、
- 公安委員会から下付された同委員会の押印ある自動車運転免許証について、その「免許の種類」「免許年月日」等の各欄に、それぞれ従前とは別異の新たなる記載をし、その写真欄貼付の写真を剥がして全く別人の写真に貼り替えたものである
として、
- 自動車運転免許証の性質に鑑みると、その重要なる部分に独立の事項の記入又は変更を加えることで、一つの新たなる証明力を具有する文書となすものであり、偽造罪を構成する
としました。
外国人登録証明書に貼付された写真を剥ぎ取り、他の人の写真と貼り替える行為は偽造になるとした事例です。
裁判所は、
- 外国人登録証明書は原判示の通り発行時の写真を剥いだ後に被告人Aの写真を貼ったもので、右写真の貼り代えは文書の性質上その重要部分の変更にあたるものとして、起訴状にある如く外国人登録証明書の単なる変造とみるべきではなく、原審認定の通り、その偽造に当たるものと認むべきものではあるが、それを変造というも偽造と解するも、畢竟、法律上の見方の相違に過ぎないものというべきであり、何ら訴因に変更がないのでこの点につき判決に影響すべき訴訟手続規定の違背があるとする論旨は採用の限りでない
と判示しました。
東京高裁判決(昭和28年12月15日)
資材譲渡申請の品目数量の改変は偽造になるとした事例です。
裁判所は、
- 資材譲渡申請の公文書としては、その品目数量は記載内容中最も重要にして中心的な部分であるから、初めA事務官から交付を受けた各申請書につき、その品目数量の記載部分をほしいままに切り取ってこれとは全く異る品目数量を記載した文書を新たに添付し、もって元来真正に成立した公文書とはその外形および記載内容共に全て別個のものとなる程度まで変革を加えた以上、これらは単なる変造の域を超えて全然独立な公文書を偽造したものと解するを相当とする
と判示しました。
広島高裁判決(昭和28年11月7日)
国庫金送金通知書の金額欄、重要な名宛人の記載の変更する行為は偽造になるとした事例です。
裁判所は、
- 被告人は判示国庫金送金通知書の金額欄の記載を変更したばかりでなく、極めて重要な名宛人の記載をも抹消して全然新な名宛人を記載してこれを変更したのであるから、その作成名義並に国庫金送金通知書たる性質に変りはなくとも、変更前のそれとは全然別個の新な証明力を有する国庫金送金通知書を作成したものというべきである
- 従ってこれは同通知書の変造ではなくてその偽造にほかならない
と判示しました。