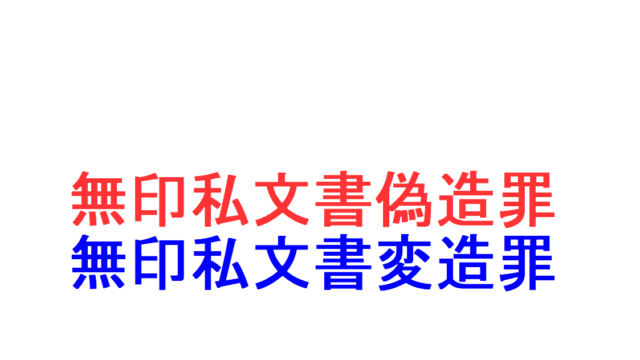無印公文書偽造・変造罪(2)~「無印公文書偽造罪、無印公文書変造罪とは?」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、無印公文書偽造罪、無印公文書変造罪(刑法155条3項)を「本罪」といって説明します。
無印公文書偽造罪、無印公文書変造罪とは?
無印公文書偽造罪、無印公文書変造罪は、刑法155条3項に規定があり、
第1項 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する
第2項 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする
第3項 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する
と規定されます。
本罪は、行使の目的をもって、公務所若しくは公務員の印章、署名を使用せずに、
- 公務所・公務員の作成すべき文書、図画(とが)を偽造すること
又は
- 公務所・公務員の作成した文書、図画を変造すること
を罰するものです。
「行使の目的」とは?
「行使の目的」の意味は、有印公文書偽造罪の場合と同様です(詳しくは有印公文書偽造罪(9)の記事参照)。
「公務所若しくは公務員の印章、署名」とは?
「公務所若しくは公務員の印章、署名」の意味も、有印公文書偽造罪の場合と同様です(詳しくは有印公文書偽造罪(13)の記事参照)。
公務所・公務員の「作成すべき」文書、図画とは?
公務所・公務員の「作成すべき」文書、図画とは、
公務所・公務員が、その職務上、公務所・公務員としての資格において作成することのできる文書、図画
をいいます。
「文書」の意味は、有印公文書偽造罪(5)の記事参照。
「図画」の意味は、有印公文書偽造罪(6)の記事参照。
公務所・公務員の「作成した」文書、図画とは?
公務所・公務員の「作成した」文書、図画とは、
公務所・公務員の作るべき文書、図画のうち、現に公務所、公務員が作成したもの
をいいます。
判例
公務所の署名は記名を含むとされていることから(大審院判決 大正4年10月20日)、実際上、無印公文書に当たる文書はまれです。
無印公文書偽造罪に関する判例として以下のものがあります。
大審院判決(明治42年6月28日)
旧国鉄の駅名札を偽造した行為について、無印公文書偽造罪が成立するとした事例です。
裁判官は、
- 帝国鉄道が手荷物の発送につき使用したる駅名札は、旧刑法に在りてはその第203条にいわゆる官の文書に該当し、現行刑法においてはその第155条第3項にいわゆる公務所の作るべき文書に該当す
と判示しました。
裁判所は、
- 物品税証紙は刑法第155条第3項の文書に該当する
としました。
裁判所は、
- 物品税表示証紙は刑法第155条第3項の公文書にあたるものと解するのが相当である
としました。
村長名義の借入金申込書に添付すべき必要書類として作成された「村議会議決書(写)」と題された文書は、村議会議決書の写しである旨を表示した無印公文書に該当するとした事例です。
裁判官は、
- 村の助役および書記が、国民健康保険事業を実施する村の運営資金として県の国民健康保険団体連合会から融資を受けるにあたり、県の国民健康保険融資金規程に基き村長名義の借入金申込書に添付すべき必要書類として右連合会に提出するため、右借入金に関する村議会の議決なく、従って、これが議決書も存在しないのにかからず、ほしいままに、行使の目的をもつて、村長から借入金に関する議案を村議会に提出し村議会においてこれを議決した旨を記録して「村議会議決書(写)」なる文書を作成したときは、刑法第155条第3項の公文書偽造罪が成立する
と判示しました。