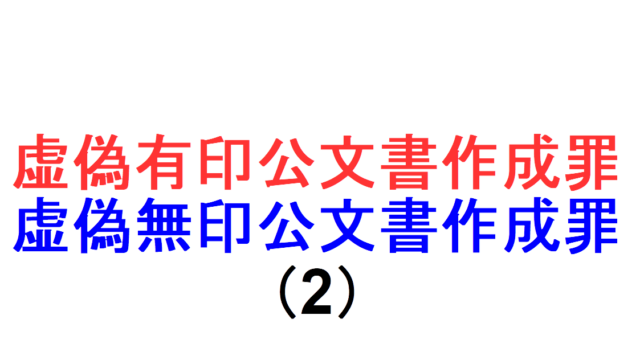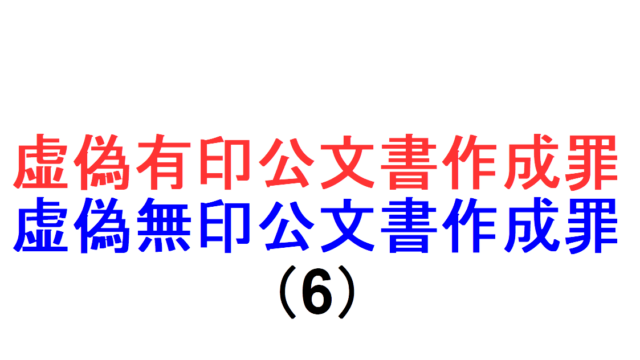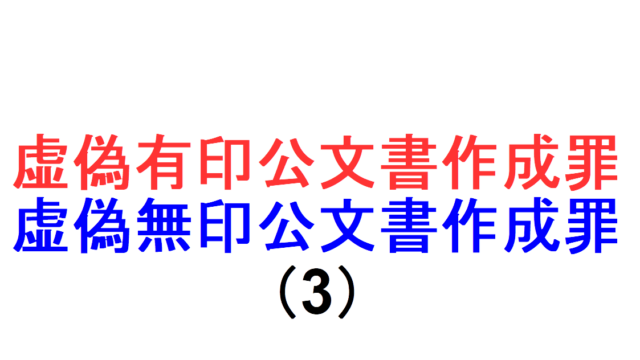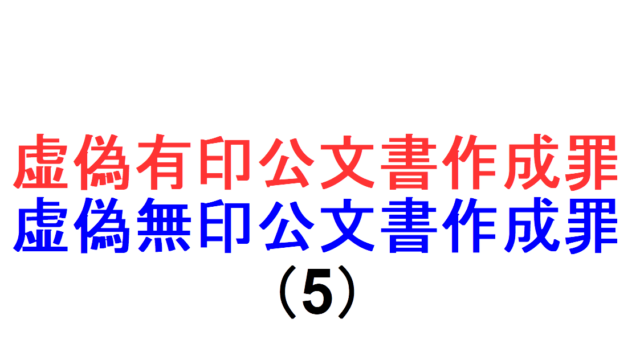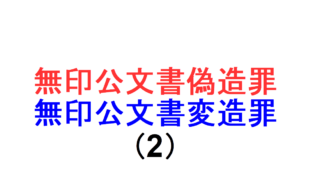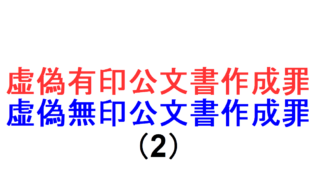虚偽公文書作成罪(1)~「虚偽有印公文書作成罪、虚偽無印公文書作成罪とは?」「保護法益」を説明
これから7回にわたり、虚偽有印公文書作成罪、虚偽無印公文書作成罪(刑法156条)を説明します。
この記事では、虚偽有印公文書作成罪、虚偽無印公文書作成罪を「本罪」といって説明します。
虚偽有印公文書作成罪、虚偽無印公文書作成罪とは?
虚偽有印公文書作成罪、虚偽無印公文書作成罪は、刑法156条に規定があり、
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条(第154条、第155条)の例による
と規定されます。
「前二条(第154条、第155条)の例による」とは、公務員が、その職務に関し、行使の目的で、
- 刑法154条における詔書を偽造・変造したときは、「無期又は3年以上の拘禁刑」に処する
- 刑法155条における公文書を偽造・変造したときは、「1年以上10年以下の拘禁刑」又は「3年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金」に処する
という意味です。
※ 詔書…天皇が一定の国事に関する意思表示を公示するために用いる文書(詳しくは、詔書偽造・変造罪の記事参照)
本罪は、
- 公務員による虚偽公文書の作成
つまり、
- 「無形偽造」及び「無形変造」を処罰するもの
です。
※ 無形偽造…文書の作成権限を有する者が内容虚偽の文書を作成すること。虚偽文書作成ともいう。
※ 無形変造…変造が作成名義人(作成権限がある者)によってなされる場合をいう。
刑法は、「私文書」の無形偽造については刑法160条(虚偽診断書等作成罪)の場合を除き不可罰としているのに対し、「公文書」の無形偽造については本条(刑法156条)で広く可罰的なものとしています。
これは、公文書は、私文書に比べて社会的信用度が高いので、私文書と異なって、虚偽文書の作成も一般的に処罰する必要があると考えられるためです。
罪名(虚偽有印公文書作成罪と虚偽無印公文書作成罪の区別)
本罪は、公務員若しくは公務所の印章、署名の有無によって、
- 虚偽有印公文書作成罪
- 虚偽無印公文書作成罪
とに分けられます。
作成した虚偽の公文書・公図画に公務所の印章、署名があれば、「虚偽有印公文書作成罪」となります。
作成した虚偽の公文書・公図画に公務所の印章、署名がなければ、「虚偽無印公文書作成罪」となります。
※ 「公務員若しくは公務所の印章、署名」の意味の説明は、有印公文書偽造罪(13)の記事参照
保護法益
本罪の保護法益は
公文書の信用性
です。
行為者が公務員であるか否かによってその保護に軽重を設けたものではありません。
この点を判示したのが以下の判例です。
裁判所は、
- 刑法第156条は信用度の高い公文書の無形偽造を私文書と異なって特に処罰することにしたものであって、その保護法益は公文書の信用性に存し、行為者が公務員であるか否かによってその保護に軽重を設けた規定ではない
と判示しました。