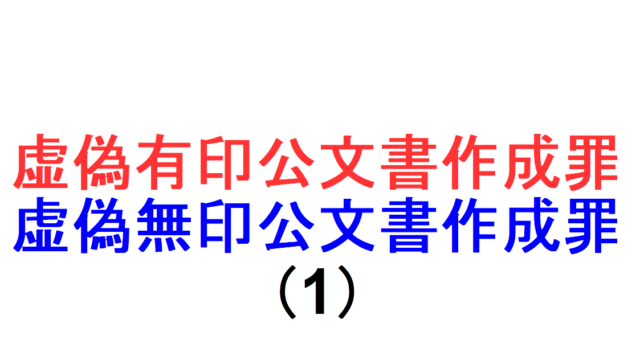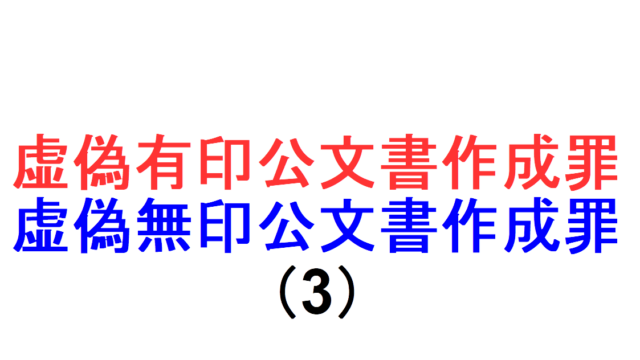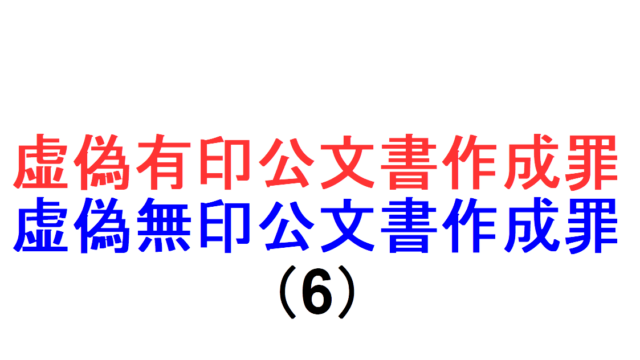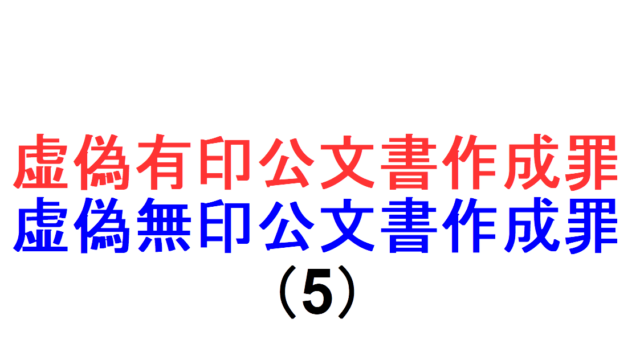虚偽公文書作成罪(2)~「主体(犯人)は『文書を作成する権限を有する公務員』である」「文書を作成する権限がない公務員が公文書を作成した場合は、虚偽公文書作成罪ではなく、公文書偽造罪が成立する」などを説明
前回の記事の続きです。
この記事では、虚偽有印公文書作成罪、虚偽無印公文書作成罪(刑法156条)を「虚偽公文書作成罪」といって説明します。
主体(犯人)は「文書を作成する権限を有する公務員」である
虚偽公文書作成罪の主体(犯人)は、
職務上、当該文書を作成する権限を有する公務員
でなければなりません(最高裁決定 昭和29年4月15日)。
したがって、虚偽公文書作成罪は、文書を作成する権限を有する公務員を主体(犯人)とする身分犯となります。
文書の作成権限ある公務員が内容虚偽の公文書を作成した場合は、職務権限の濫用と認められる場合であっても、虚偽公文書作成罪が成立する
文書の作成権限ある者が内容虚偽の公文書を作成した場合は、たとえそれが職務権限の濫用と認められる場合であっても、公文書偽造罪(刑法155条)ではなく、虚偽公文書作成罪が成立します。
この点に関する判示として、以下のものがあります。
大審院判決(大正11年12月23日)
裁判所は、
- 収入役は市町村の現金出納に関する公簿を作成すべき一般的権限を有する者なれば、収入役が業務上横領罪を犯し、その犯跡を隠蔽するため、如上公簿に虚偽の記載を為すは、刑法第156条の罪(虚偽公文書作成罪)を構成するものにして、刑法第155条の罪(公文書偽造罪)と為すべきものに非ず
としました。
裁判官は、
- 村長がその名義の内容虚偽の公文書を作成した場合は、それが専ら第三者の利をはかる等不法な意思に出でその職務権限の乱用と認められる場合であっても、刑法第156条の罪(虚偽公文書作成罪)が成立し、同法第155条の罪(公文書偽造罪)が成立するものではない
としました。
文書の作成権限は、法令に規定されていると、内規に定められていると、また、慣例によって認められているとを問わない
文書の作成権限は、法令に規定されていると、内規に定められていると、また、慣例によって認められているとを問いません。
この点を判示したのが以下の判例・裁判例です。
大審院判決(明治45年4月15日)
裁判所は、
- 刑法第155条にいわゆる公務所又は公務員の作るべき文書とは、公務所又は公務員がその名義をもってその権限内において所定の形式に従い作成すべき文書にして、その権限が法令によると内規又は慣例によるとはこれを問うことなく、あまねくその職務執行の範囲内において作成せらるるを要するのみ
と判示しました。
裁判官は、
- 刑法第156条にいわゆる公文書とは、公務所又は公務員がその名義をもってその権限において所定の形式に従い作成すべき文書であって、その権限が法令によると内規又は慣例によるとを問わず、あまねく職務執行の権限内において作成せられたものをいう
と判示しました。
大阪高裁判決(昭和41年11月14日)
慣行上、非農地証明書を発行する権限を有する農業委員会長が、虚偽の非農地証明書を発行した事案です。
裁判所は、
- 従来、大阪府においては大阪法務局と打合せのうえ、地目が農地であっても現況が非農地である場合は、申出があれば大阪府知事が非農地証明書を発行し、これを地目変更申請者に交付し、申請者は右証明書を添付して法務局に地目変更の申請をしていたが、昭和28年3月9日付け大阪府農地部長の府下各市町村農業委員会長宛通知により、従来府知事の行なっていた農地法2条に規定する農地に該当せざる旨の証明は、今後、各市町村農業委員会長がこれをなすこととなり、同日付けで大阪法務局民事行政部長宛に大阪府農地部長から、今後右のように取扱うことになったから御協力を頼む旨の依頼がなされ、じらい大阪府においては府下各市町村農業委員会長が慣行上非農地証明書を作成していたことが認められるから、当時泉佐野市農業委員会長であった被告人が、情を知らない同委員会事務局職員Kらをして本件土地が昭和15年頃から現況が山林となっていることを証明する旨の願書に証明者として同農業委員会長たる自己の記名印及び職印を押捺させて作成した本件証明書は、刑法156条にいう公文書に当たるといわなければならない
と判示し、虚偽公文書作成罪が成立するとしました。
補助公務員も虚偽有印公文書作成罪の主体となり得る
作成名義人となる公務員以外の公務員でも、法令により、又は作成権者の委任によって、文書の作成権限を与えられている公務員(補助公務員)は、虚偽公文書作成罪の主体となり得ます。
補助公務員の作成権限については、補助公務員が一定の手続を経由するなどの特定の条件のもとにおいて公文書を作成することが許されている場合には、その内容の正確性を確保することなど、その者への授権を基礎づける一定の基本的な条件に従う限度において作成権限を有しているとして(最高裁判決 昭和51年5月6日)、このような補助公務員が上司の決裁を受けずに文書を作成する行為は、内容が虚偽である限度で虚偽公文書作成罪が成立するとされます。
補助公務員が、その職務上起案すべき公文書につき虚偽の内容を記載して、情を知らない作成権限者に署名押印等をさせた場合は、虚偽公文書作成罪(刑法156条)の間接正犯が成立します(最高裁判決 昭和32年10月4日参照)。
なお、補助公務員がその権限内で公文書を作成することは適法であり、公文書偽造罪は成立しません。
例えば、自らは作成名義人ではないが、名義人から文書作成を委任されている公務員の場合、例えば、助役のように村長から代決の権限を与えられている者は、村長の決済を待つまでもなく村長名義の文書を作成でき、村の助役が村長の代理として職務を執行するにあたり、執務の便宜上代理名義を省略し、村長名義の文書を作成しても、 これをもって文書偽造罪と認めることはできません。
大審院判決(明治44年7月6日)は、
- 助役が村長の代理として職務を執行するに当たり、村長の名義をもって文書を作成すといえども、その文書にして助役が村長代理として正当に作成し得べき性質のものなるときは、執務の便宜上、代理名義を省略したるにどどまり、これをもって偽造と認べきものに非ず
と判示しています。
※ この点については、有印公文書偽造罪(3)の記事でも説明しています。
文書を作成する権限がない公務員が公文書を作成した場合は、虚偽公文書作成罪ではなく、公文書偽造罪が成立する
公務員であっても、
- その作成権限に属しない文書をほしいままに作成するとき
又は
- その職務の執行に関係なく公務所又は公務員名義の文書を作成するとき
は、公文書偽造罪が成立します。
この点を判示した以下の判例があります。
大審院判決(大正7年11月20日)
裁判所は、
- 公務員が公務員たる名義をもって虚偽の内容を有する文書を作成したる場合において、その文書の作成が何ら職務の執行に関せざるものなるときは、公務員に非ざる者が公務員の作るべき文書を偽造したるに異ならざれば、刑法第155条(公文書偽造罪)に問擬(もんぎ)すべきものとす
としました。
大審院判決(昭和8年10月5日)
裁判所は、
- 公務員、行使の目的をもってその職務に関せざる虚偽の公文書を作成したるときは、刑法第155条に問擬(もんぎ)すべきものとす
と判示しました。
裁判所は、
- 公務員であっても行使の目的をもって作成権限が無いにかかわらず公務所又は公務員の印章若しくは署名を冒用して公務所又は公務員の作るべき文書を作成すれば公文書偽造罪が成立する
としました。
裁判所は、
- A鉄道管理局B電力区助役として区長を補佐する傍ら同管理局から出納員もしくは事務助役出納員として指命され、部内職員の給料、族費等の交付、保管等対内的な出納事務には従事するが、同電力区助役もしくは右出納員名義をもつて対外部関係に関する公文書を作成すべき一般的職務権限を有しない被告人が、行使の目的をもって内容虚偽の電柱代金代理受領承諾書と題する文書の末尾に、右を承認する旨記載しA鉄道管理局B電力区出納責任者某なる奥書をし、名下に自己の私印を押捺し、庁印として備付の同電力区の公印を押捺して右文書を作成したときは、刑法第155条第1項の公文書偽造罪を構成する
と判示しました。