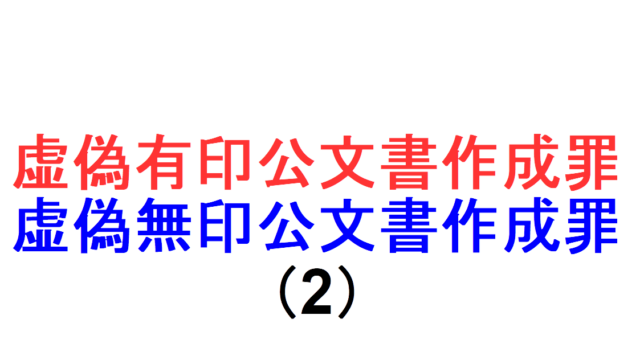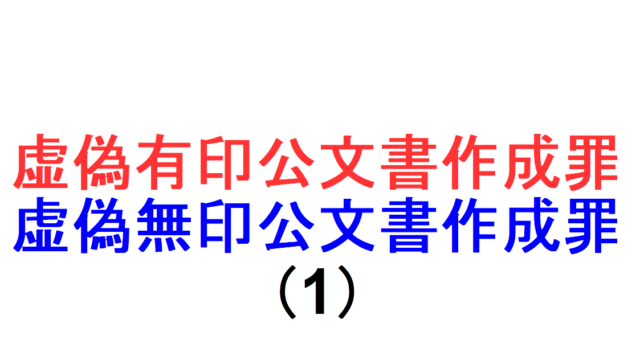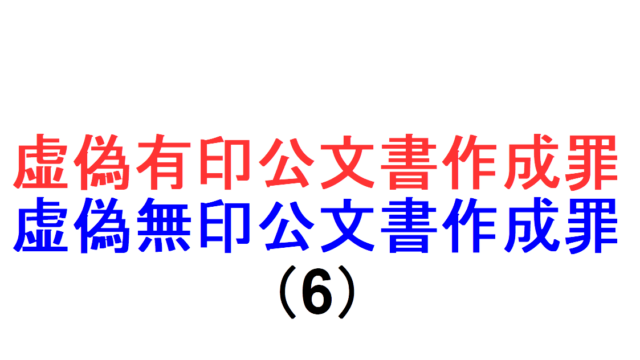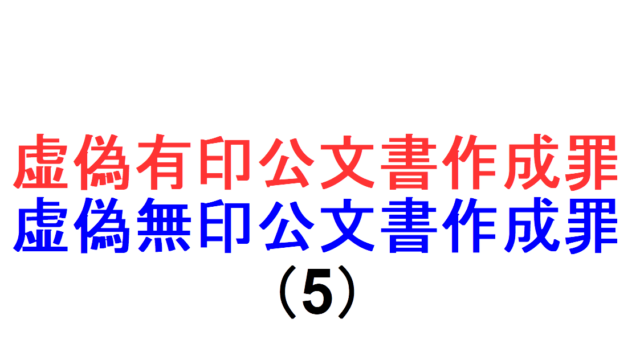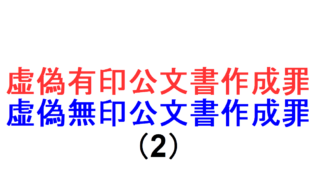虚偽公文書作成罪(3)~「客体(公務所若しくは公務員の印章・署名のある公務所若しくは公務員の文書若しくは図画など)」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、虚偽有印公文書作成罪、虚偽無印公文書作成罪(刑法156条)を「虚偽公文書作成罪」といって説明します。
客体(公務所若しくは公務員の印章・署名のある公務所若しくは公務員の文書若しくは図画など)
虚偽公文書作成罪(刑法156条)の客体は、
及び
- 公務所若しくは公務員の印章・署名のある公務所若しくは公務員の文書若しくは図画(とが)
です。
虚偽公文書作成罪(刑法156条)における公文書とは、
- 公務所又は公務員がその名義をもってその権限内において所定の形式に従い作成すべき文書にして、その権限が法令によると内規又は慣例によるとはこれを問うことなく、あまねくその職務執行の範囲内において作成せられたるもの
をいいます(大審院判決 明治45年4月15日)。
例えば、最高裁決定(昭和38年12月27日)は、農業委員会主事の慣行上の作成権限を認め、同人作成の非農地証明書を虚偽公文書作成罪における公文書であると認めています。
また、虚偽公文書作成罪における公文書には刑法154条(詔書偽造・変造罪)の詔書等も含まれます。
※ 詔書偽造・変造罪の説明は前の記事参照
※「文書」の意味は、有印公文書偽造罪(5)の記事参照
※「図画」の意味は、有印公文書偽造罪(6)の記事参照
※「公務所若しくは公務員の印章、署名」の意味は、有印公文書偽造罪(13)の記事参照
文書は確定的なものとして表示された内容を持つものでなければならない
文書偽造罪にいう文書は、確定的なものとして表示された内容を持つものでなければなりません。
この点について、検察審査会の事務局長をしていた被告人が、部下の事務官に指示又は依頼して、審査申立事件の実地見分調書を作成させた際、同調書に交差点の存在を表示する道路警戒標識がなかったのにあったとの内容虚偽の記載をさせたとして、虚偽公文書作成・行使罪の間接正犯の責任が問われた事案において、当該実地見分調書はいまだ内容が確定されておらず草稿の域をでないものであるとして、虚偽有印公文書作成罪の公文書に当たらないとした以下の裁判例があります。
裁判官は、
- 刑法156条にいわゆる公文書といいうるためには、それが一般人をして公務所又は公務員の権限内において作成した文書であると信ぜしめる程度に形式外観を具えるだけでは足りず、さらに確定的な意識内容の記載であり原本的なものであることを要するのであって、確定的な意識内容の記載といえない草案や草稿は右の公文書にあたらない
と判示しました。
診断書、死亡証書であっても、国公立病院医師の作成するものは虚偽有印公文書作成罪における公文書である
診断書、死亡証書であっても、国公立病院医師の作成するものは虚偽有印公文書作成罪における公文書となります。
東京地裁判決(平成13年8月30日)は、都立病院院長が担当医師と共謀の上、医療事故により死亡した患者の死亡診断書及び死亡証明書の作成の際、死因を病死と記載したことについて、虚偽有印公文書作成罪が成立するとしました。