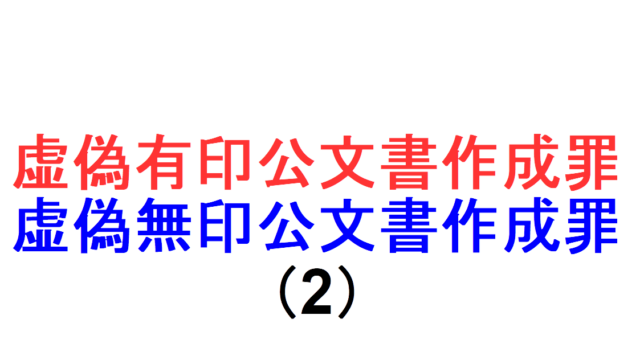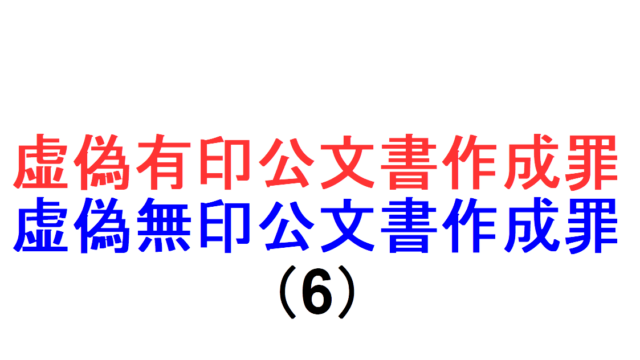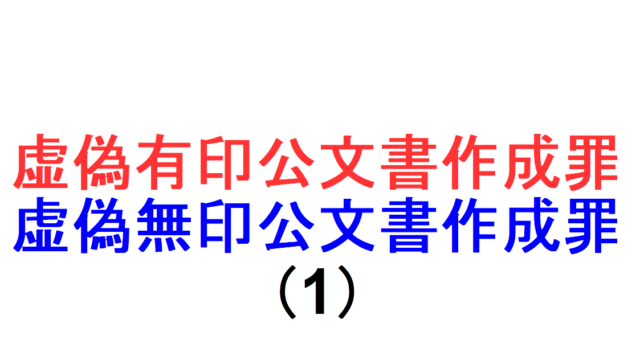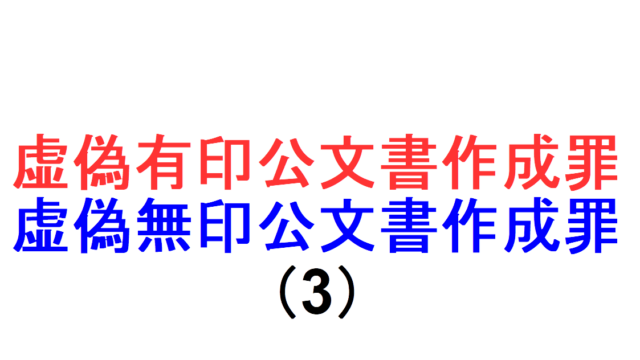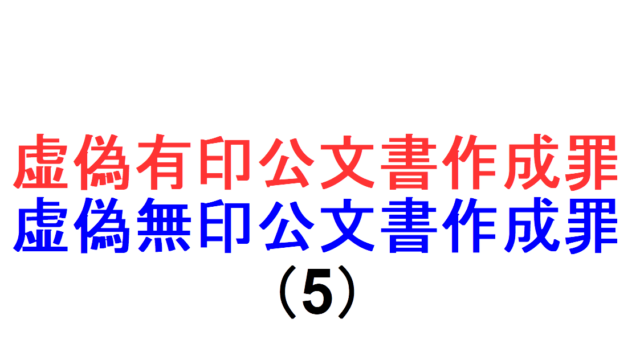虚偽公文書作成罪(4)~「虚偽公文書の作成行為」「虚偽の届出・申請に基づく虚偽公文書の作成」「虚偽公文書作成罪における『変造』」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、虚偽有印公文書作成罪、虚偽無印公文書作成罪(刑法156条)を「虚偽公文書作成罪」といって説明します。
虚偽公文書の作成行為
虚偽公文書作成罪(刑法156条)の行為は、行使の目的を持って、
① 御璽、国璽、御名を使用して、虚偽の詔書その他の文書を作ること
又は
② 御璽、国璽を押捺し、若しくは御名を署した詔書その他の文書を変造すること
又は
③ 公務所・公務員の印章、署名又は偽造した公務所・公務員の印章、署名を使用して、虚偽の文書、図画を作ること
又は
④ 公務所・公務員の捺印、署名した文書、図画を変造すること
又は
⑤ 印章署名のない虚偽の公文書、公図画を作り、若しくは変造すること
です。
虚偽公文書作成の事例
虚偽公文書作成の事例として、以下の判例があります。
大審院判決(大正2年8月29日)
私人の渡航、帰朝に関する事実を証明する職務を有する村長が、その事実がないのを知りながら、渡航、帰朝の事実があるように証明した村長名義の文書を作成した行為について、虚偽公文書作成罪が成立するとしました。
村農地委員会の会長らが、同委員会の議事録を作成するにあたり、会議における発言中の無効な部分を除去することによって、あたかも現実になされた決議と異なる決議があったように記載した行為について、虚偽公文書作成罪が成立するとしました。
大審院判決(大正6年8月20日)
郵便局長(※当時、郵便局は国営)が、郵便振替貯金を受け入れたが、故意に受入当日よりも遅れて、振込金額、振込者、加入者等を受入れ簿に記入し、これに記入当日の日付け印を押印し、文書としてこの日付において振込を受け入れた旨の虚偽の事実を証明する文書を作成した行為について、虚偽公文書作成罪が成立するとしました。
虚偽の届出・申請に基づく虚偽公文書の作成
1⃣ 当事者の届出に基づいて記載される文書について、当該公務員が、その届出事項の内容が虚偽であることを知りながら記載したときは、虚偽公文書作成罪が成立するか否かという問題があります。
土地・建物の表示登記のように当該公務員が実質的審査権を有する場合には、その文書の記載内容が真実に合致すべきことが強く要請されているという理由で、虚偽公文書作成罪の成立を認めるべきであるという見解が一般的です。
この点に関する以下の判例があります。
大審院判決(明治7年4月21日)
裁判所は、
- 家屋の所有者その他より家屋の所有権若しくは共権の取得移転等に関し、形式を備える届出あるも、その事項にして虚偽なること明白なる場合において、市町村長その情を知りながらこれを家屋台帳に記載したるときは、刑法第156条の犯罪(虚偽公文書作成罪)を構成す
と判示ました。
2⃣ 形式的審査権を有するにすぎないときでも、当該公務員が、届出人、申請人と共謀して、 自己の職務上の義務を不法に利用した場合には、虚偽公文書作成罪が成立します。
この点に関する以下の判例があります。
大審院判決(大正6年6月25日)
裁判所は、
- AB間の不動産売買は、Aが未成年者の後見人としてその職務に従い従事中、その資格を濫用し、B及び裁判所書記官Cらと通謀して為した虚偽の意思表示にして、法律上無効のものなれば、Cがその職務の執行として登記簿原本に為したる各売買登記及びこれに伴う核登記済証の記載は、いずれも虚偽にして刑法第156条の犯罪(虚偽公文書作成罪)を構成するものとす
と判示しました。
しかし、偶然に届出事項が虚偽であることを知りながら、文書を作成しただけの場合については学説の見解は分かれます。
虚偽公文書作成罪は成立しないと解する見解が多数です。
これに対し、明確に虚偽だと知って記載すれば虚偽公文書作成罪の成立は避けられないとする見解もあります(理由は、内容虚偽であることを知っていても申立ての受理が義務的であるとはいえないから、本罪が成立すると解すべきであるとします)。
判例は、戸籍事務を管掌する市町村長において、届出事項が実体法規に抵触してその効力を生じないことを知りながら戸籍簿に記載した場合であっても、右事項が届出当事者の真実の意思に合致しているものである限り、虚偽公文書作成罪は成立しないとするものがあります(大審院判決 大正7年7月26日)。
なお、捜査官又は裁判所書記官が事件関係者等の供述を録取する場合は、供述そのものと調書の記載とが符合するかどうかが問題なのであって、供述内容が真実と符合していなくとも供述どおり録取している以上、虚偽公文書作成罪は成立しません。
ただし、判例は、供述者から教唆されて、真実を隠蔽した虚偽の供述調書を作成したときは虚偽公文書作成罪が成立するとします。
大審院判決(昭和8年7月13日)
裁判所は、
- 司法警察官において、供述者の供述をそのまま録取したりとするも、供述者と共謀の上、真正の事実を隠蔽し、虚偽の供述を為さしめ、これを記載したるものなるときは、虚偽の公文書を作成したるものとす
と判示し、虚偽公文書作成罪が成立するとしました。
虚偽公文書作成罪における「変造」
虚偽公文書作成罪における「変造」は、公文書偽造罪における変造(有形変造)とは異なり、
作成権者である公務員が、その権限を濫用して、既存の公文書、公図画に不当に変更を加え、その内容を虚偽のものとする無形変造
を意味します。
※ 有形変造の意味…文書の作成名義人ではない人(文書の作成権限がない人)が真正な文書の内容を改ざんすること
※ 無形変造の意味…文書の作成名義人(作成権限がある人)が真正な文書の内容を改ざんすること
※ 公文書偽造罪における変造の説明は、有印公文書変造罪(9)の記事参照