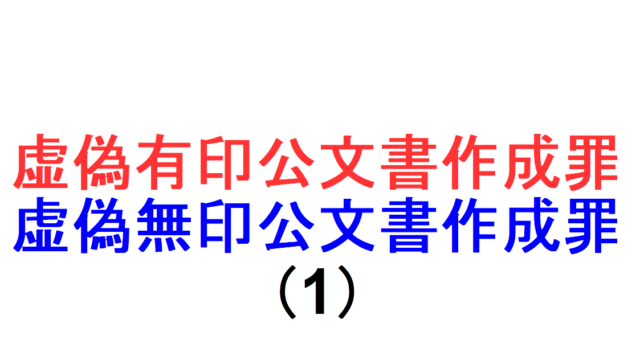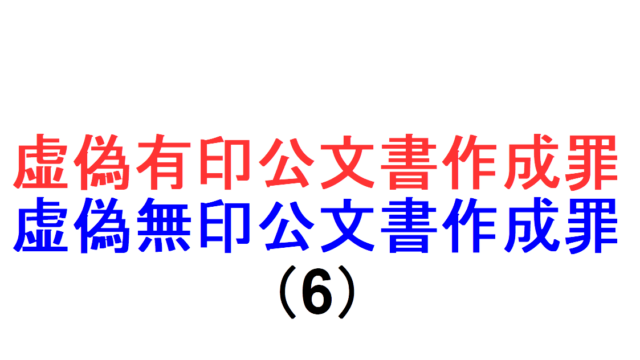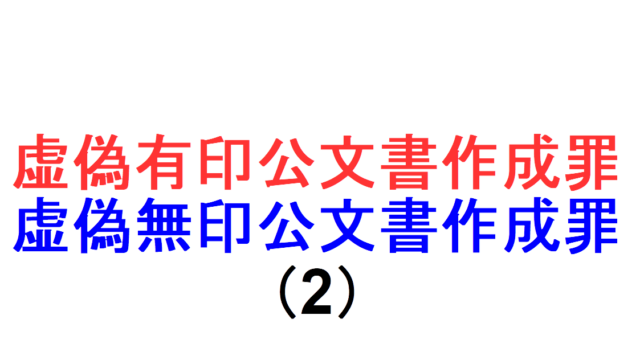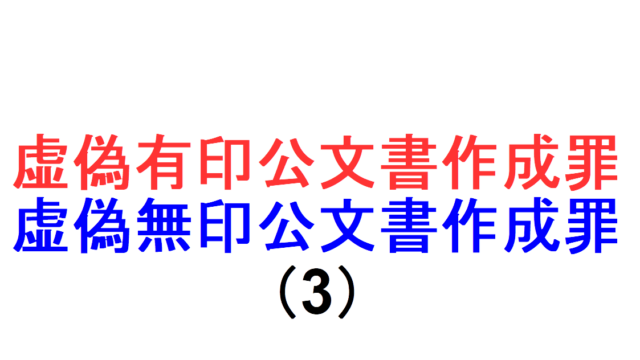虚偽公文書作成罪(5)~「間接正犯による虚偽公文書作成罪の成否」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、虚偽有印公文書作成罪、虚偽無印公文書作成罪(刑法156条)を「虚偽公文書作成罪」といって説明します。
間接正犯による虚偽公文書作成罪の成否
間接正犯による虚偽公文書作成罪の成立が認められるかについて説明します。
「間接正犯」は、
他人を道具として利用し、他人に犯罪行為をやらせ、犯罪を実現する者
いいます(間接正犯の説明は前の記事参照)。
虚偽公文書作成罪は、その主体(犯人)が職務上当該文書を作成する権限を有する公務員であることを要する身分犯です。
主体(犯人)が文書の作成権限を有する公務員であれば、虚偽公文書作成罪の成立は認められるので、
- 作成権限を有する公務員が、他の作成権者である公務員を利用して虚偽公文書を作成させた場合
- 作成権者である公務員が、作成権限のない他の公務員を手足として虚偽の公文書を作成させた場合
には、虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立することに異論はありません。
これに対して、
- 私人あるいは権限のない補助公務員といった身分なき者
について、虚偽公文書作成罪の間接正犯を認めることができるかということについては、見解の対立があります。
見解の対立がある理由は、
- 身分犯の間接正犯が認められるかという理論的な問題点があること
- 刑法157条の公正証書原本等不実記載罪の構成要件的行為は、身分犯の間接正犯一種に当たるが、行為態様も虚偽の申告に限っているばかりか、法定刑は虚偽公文書作成罪(刑法156条)の場合よりかなり軽いため、刑法157条とは別に、一般的に虚偽公文書作成罪の間接正犯を認め得るかが問題となること
にあります。
判例・裁判例の立場
間接正犯による虚偽公文書作成罪の成立が認められるかについて、判例・裁判例の立場は分かれています。
かつて、大審院判決では、
- 村の助役が、村会議員の選挙にあたって、情を知らない選挙長を利用して、虚偽の文書を作成させた事案(大審院判決 昭和11年2月14日)
- 村の助役が、軍事扶助金名義で、県知事から金員を詐取しようと企て、軍事扶助調書に虚偽の事実を記載してその作成権者である村長に提示し、情を知らない村長に署名、調印させ、虚偽の軍事扶助調書を作成ざせた事案(大審院判決 昭和15年4月2日)
について、間接正犯による虚偽公文書作成罪の成立を認めていました。
これに対し、最高裁では、間接正犯による虚偽公文書作成罪の成立を否定したものと肯定したものとがあります。
【否定したもの】
公務員の身分を有しない者が、日本において兵役に服したことがないなど虚偽の事項を記載した証明願いを村役場の係員に提出し、情を知らない係員をして、村長名義の証明書を作成させた事案です。
裁判所は、
- 刑法が157条の処罰規定(公正証書原本等不実記載罪)を設け、しかも156条(虚偽公文書作成罪)の場合の刑よりも著しく軽く罰しているにすぎない点からみると、公務員でない者が虚偽の公文書偽造の間接正犯であるときは157条の場合のほかこれを処罰しない趣旨と解するを相当とする
- 公務員の身分を有しない者が、虚偽の内容を記載した証明願いを村役場の係員に提出し、情を知らない同係員をして村長名義の虚偽の証明書を作成させた行為は、刑法第156条の間接正犯として処罰すべきではない
- 公務員の自分を有しない者が虚偽の内容を記載した証明願いを村役場の係員に提出し、情を知らない同係員をして作成させた村長名義の虚偽の証明書を行使しても、虚偽公文書行使罪にあたらない
とし、間接正犯による虚偽公文書作成罪の成立を否定しました。
【肯定したもの】
地方事務所の建築係(補助者たる公務員)が、まだ着工していない住宅の現場審査申請書に、建前が完了した旨の虚偽の記載をして、情を知らない上司である地方事務所長に提出し、所要の記名、捺印をさせて、内容の虚偽な現場審査合格書を作成させた事案です。
裁判所は、
- 作成権限者たる公務員を補佐して公文書の起案を担当する公務員が、行使の目的で内容虚偽の公文書を起案し、情を知らない右上司を利用してこれを完成した場合は、虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する
と判示し、間接正犯による虚偽公文書作成罪の成立を肯定しました。
以上のとおり、最高裁判例には、間接正犯を否定したものと肯定したものとがあり、
- 成立を否定した判例の事案は、「私人の犯行」にかかるものである
- 成立を肯定した判例の事案は、「当該公文書の作成権者を補佐して、当該公文書を起案する地位にあるとみられる公務員の犯行」にかかるものである
という違いがあります。
その後の下級審裁判例では、間接正犯による虚偽公文書作成罪の成立を否定した裁判例が2件ありあます。
旭川地裁判決(昭和36年9月21日)
私人が住民票抄本用紙に虚偽の生年月日を記載し、情を知らない住民登録係員を利用して住民票抄本を作成させた事案について、間接正犯による虚偽公文書作成罪の成立を否定し、無罪を言い渡しました。
甲府地裁判決(昭和38年2月13日)
銃砲刀剣類の登録審査委員に任命されその鑑定事務に従事して公務員たる資格を持っていた者が、火なわ式銃の模造品を作った者と共謀の上、美術品又は骨とう品として登録を受けようと企て、当該登録審査委員がかねて県教育委員会から交付を受けていた登録原票用紙の所定欄に本物の火なわ銃であるように虚偽の内容を記入するなどして、これを情を知らない教育委員会の係員に提出し、これに基づいて登録手続が実施されたという事案です。
裁判所は、
- 当該登録審査委員は公務員の身分を有する者ではあるが登録原票作成権限を有するものではなく、かつ同作成権限者を補佐して公文書を起案する地位にあったでもないから、結局、両名に虚偽公文書作成罪の間接正犯は成立しない
としました。