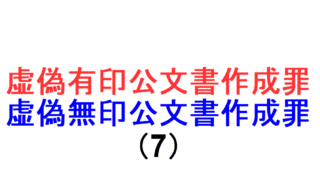公正証書原本不実記載罪(1)~「公正証書原本不実記載罪、電磁的公正証書原本不実記録罪とは?」「保護法益」「未遂規定」「主体(犯人)」を説明
これから14回にわたり、公正証書原本不実記載罪、電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法157条1項)を説明します。
公正証書原本不実記載罪、電磁的公正証書原本不実記録罪とは?
公正証書原本不実記載罪、電磁的公正証書原本不実記録罪は、刑法157条1項に規定があり、
第1項 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する
第2項 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する
第3項 前二項の罪の未遂は、罰する
と規定されます。
刑法157条は、
- 第1項で、公正証書原本不実記載罪、電磁的公正証書原本不実記録罪
- 第2項で、免状不実記載罪、鑑札不実記載罪、旅券不実記載罪
- 第3項で、第1項と第2項の罪の未遂罪
を定めます。
刑法157条の罪は、
虚偽公文書作成罪(刑法156条)の間接正犯のうち、行為を虚偽の申立てに限定するとともに、客体を特に重要な証明力を有する公文書である、権利若しくは義務に関する公正証書の原本又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録、免状、鑑札又は旅券に限定して処罰するもの
です。
なお、権利、義務に関する公証業務のコンピュータ化が進み、書面たる公正証書の原本に代わって電磁的記録が広く普及する時代となったため、昭和62年に電磁的記録が本罪の対象として加えられました。
保護法益
公務員に対して虚偽の申立てをし、公正証書の原本等に不実の記載をさせる行為は、公正証書の原本等が有する公の信用を害するものなので、本罪は、
公正証書の原本等の公共的信用性を保護するために設けられたもの
であると考えられています。
この点、参考となる以下の判例があります。
大審院判決(大正6年10月1日)
裁判所は、
- 公証の制度は、証書による証明の信憑力を確実ならしむるがために設けられたるものにして、公証の当該機関たる公務所又は公務員は、一定の事実につき、これが真実なることを証明して公の信用に供するものとす
- 故に公務員に対し、虚偽の申立を為し、公正証書の原本に不実の記載を為さしむる行為は、その成立は真正なるも、内容の不実なる公正証書を成立せしむるものにして、すなわち、公証制度を濫用して公正証書の有する公の信用に危害を加えるものにほかならず
- これ刑法第157条において処罰するところなり
と判示しました。
なお、学説には、虚偽公文書作成罪を公務員による職権濫用罪として理解する関係で本罪も公務執行妨害罪の一種として捉える見解もあります。
未遂規定
公正証書原本不実記載罪、電磁的公正証書原本不実記録罪(第1項)、免状不実記載罪、鑑札不実記載罪、旅券不実記載罪(第2項)は、いずれもその未遂行為を印章偽造の罪(刑法第19章)によって処罰することはできないことから、刑法157条はその未遂罪を処罰する規定をもうけています(第3項)。
主体(犯人)
公正証書原本不実記載罪、電磁的公正証書原本不実記録罪の主体(犯人)は、
権利若しくは義務に関する公正証書の原本、あるいは権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録を作成する公務員に対し、これに記載ないし記録すべき事項を申告・申請する者
です。
私人に限られず、公務員もその主体になり得ます。