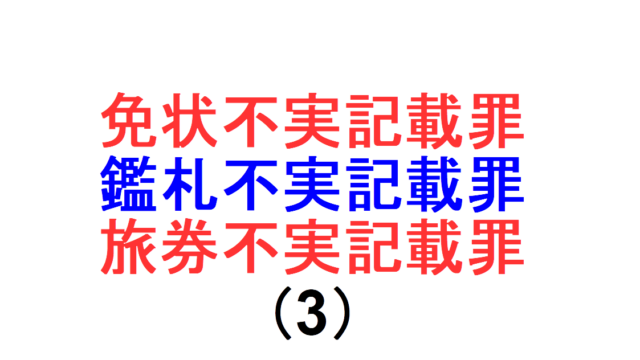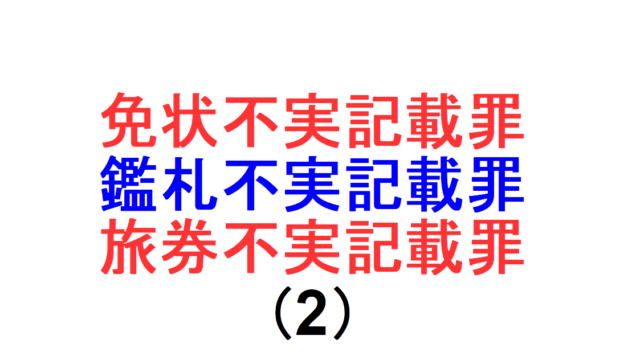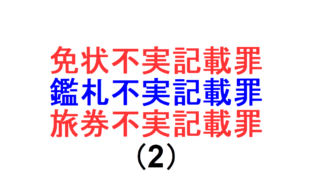免状等不実記載罪(1)~「免状不実記載罪、鑑札不実記載罪、旅券不実記載罪とは?」「主体(犯人)」「客体(免状・鑑札・旅券)」を説明
これから3回にわたり、免状不実記載罪、鑑札不実記載罪、旅券不実記載罪(刑法157条2項)を説明します。
免状不実記載罪、鑑札不実記載罪、旅券不実記載罪は、適宜「本罪」といって説明します。
免状不実記載罪、鑑札不実記載罪、旅券不実記載罪とは?
免状不実記載罪、鑑札不実記載罪、旅券不実記載罪は、刑法157条2項に規定があり、
第1項 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する
第2項 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する
第3項 前二項の罪の未遂は、罰する
と規定されます。
刑法157条は、
- 第1項で、公正証書原本不実記載罪、電磁的公正証書原本不実記録罪
- 第2項で、免状不実記載罪、鑑札不実記載罪、旅券不実記載罪
- 第3項で、第1項と第2項の罪の未遂罪
を定めます。
刑法157条の罪は、
虚偽公文書作成罪(刑法156条)の間接正犯のうち、行為を虚偽の申立てに限定するとともに、客体を特に重要な証明力を有する公文書である、権利若しくは義務に関する公正証書の原本又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録、免状、鑑札又は旅券に限定して処罰するもの
です。
なお、権利、義務に関する公証業務のコンピュータ化が進み、書面たる公正証書の原本に代わって電磁的記録が広く普及する時代となったため、昭和62年に電磁的記録が本罪の対象として加えられました。
主体(犯人)
本罪の主体(犯人)は、
免状、鑑札又は旅券に記載されるべき事項を、権限ある公務員に申告する者
です。
客体(免状・鑑札・旅券)
本罪の客体は、
です(制限列挙)。
「免状」とは?
免状とは、
特定の人に対して、一定の行為を行う権利を付与する、公務所又は公務員の作成する証明書
をいいます。
例えば、判例上、免状に当たるとされたものとして、以下のものがあります。
① 火薬譲渡許可証(大審院判決 明治41年9月24日)
裁判所は、
- 火薬譲受許可証は、一定の人に対し、火薬譲受の権利を付与する警察署の証明書にして免状の一種なりとす
と判示しました。
② 狩猟免状(大審院判決 大正4年4月24日)
裁判所は、
と判示ました。
③ 自動車運転免許証(大審院判決 昭和5年3月27日)
裁判所は、
- 他人の名義を冒用して自動車運転手免許証下付願及び履歴書を偽造行使し、運転手試験を受け、これに合格し、当該吏員をして名義人を運転手とする不実の記載を自動車運転手免許証に為さしめ、その下付を受け、これを行使したる場合においては、免許証下付願及び履歴書の偽造行使罪と、免状に不実の記載を為さしめこれを行使したる罪との間には、互いに手段結果の関係あるものとす
と判示し、「私文書偽造罪(刑法159条)・偽造私文書行使罪(刑法161条1項)」と「免状不実記載罪・不実記載免状行使罪(刑法158条1項)」が成立し、両罪は牽連犯の関係になるとしました。
これに対して、免状に当たらないとされたものとして、以下のものがあります。
① 書記試験及第証書(大審院判決 明治35年5月16日)
裁判所は、
- 刑法第214条(※旧刑法)にいわゆる免状とは、これを受ると同時に、あるいは特殊の行為を実行し得べき権利を享有するものをいう
- 従って、書記試験及第証書の如き試験に及第したることを証するに過ぎざるものは、同条にいわゆる免状に非ず
と判示しました。
② 小学校準教員免許状(大審院判決 明治37年11月10日)
裁判所は、
- 刑法第214条(※旧刑法)にいわゆる免状とは、これを有する者をして特殊の行為を行うことを得せしむべき効力あるものをいう
- 従って、小学校準教員免許状の如きはこれに包含せず
と判示しました。
③ 家庭主食購入通帳(最高裁判決 昭和24年11月17日)
裁判所は、
- 「家庭用主食購入通帳」は、一個人の所有権の客体となるべき有体物であるから、刑法にい わゆる財物にあたるものといわなければならない
- 従って、該通帳が本件被告人の配給物資を騙取せんがための手段であり、道具であるに過ぎなかったとしても、詐欺罪の成立を妨げる理由はない
- されば原審が被告人の所為に対し食糧緊急措置令10条又は刑法157条2項を適用しないで、刑法246条1項又は同法155条1項等を適用したのは正当であって原判決には所論のような法令の適用を誤った違法はない
と判示し、物資をだまし取る手段として、市役所の係員を欺罔し、虚無人名義の「家庭用主食購入通帳」を交付させた行為は詐欺罪に該当するものであって、免状不実記載罪を適用すべきではないとしました。
④ 米穀輸送証明書(福岡高裁判決 昭和30年5月19日)
裁判所は、
- 米穀輸送証明書は、米穀の輸送に関する権利義務の得喪変更等の証明を目的とするものでないから刑法第157条にいう免状にあたらない
と判示ました。
⑤ 外国人登録証明書(東京高裁判決 昭和33年7月15日)
外国人登録原票は、名古屋高裁判決(平成10年12月14日)で、本罪ではなく、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)の客体に該当します。
⑥ 自動車検査証(大阪高裁判決 昭和30年6月20日)
裁判所は、
- 公務員の身分を有しないものが、職務権限を有するAに対し、虚偽の内容を記載した自動車検査証再交付申請書を提出し、制規の手続によって検査証再交付の申請をするもののように装い、情を知らない係員をして大阪府知事名義をもって虚偽の自動車検査証を再交付として作成交付させた行為は、刑法第155条又は同法第156条の間接正犯として処罰するべきではない
- 従って、右の検査証を行使しても偽造公文書行使罪に当らない(最高裁判所昭和27年12月25日第一小法廷判決参照)
- そして自動車検査証は、刑法第157条にいわゆる権利義務に関する公正証書の原本又は免状、鑑札、旅券のいずれにも当らない
- 右の行為は、当審において検察官から提出された「予備的訴因等の追加申立書」記載の如く、道路運送車両法第107第1号にいわゆる詐偽その他不正の手段により同法第70条(自動車検査証の再交付)の規定による検認を受けた者に該当すると解すべきである
としました。
「鑑札」とは?
鑑札とは、
公務所の許可、登録があったことを証明するものであって、公務所が作成下付し、その下付を受けた者がこれを備付け、又は携帯することを要するもの
をいいます。
例えば、
- 犬の鑑札(狂犬病予防法)
- 船の鑑札(船鑑札規則)
- 質屋の許可証(質屋営業法)
- 古物商の許可証(古物営業法)
が挙げられます。
「旅券」とは?
旅券とは、
旅券法に基づいて、外務大臣又は領事官が、外国渡航者に対して発給する、その旅行を認許した旨を記した文書
をいいます。
つまり、パスポートです。