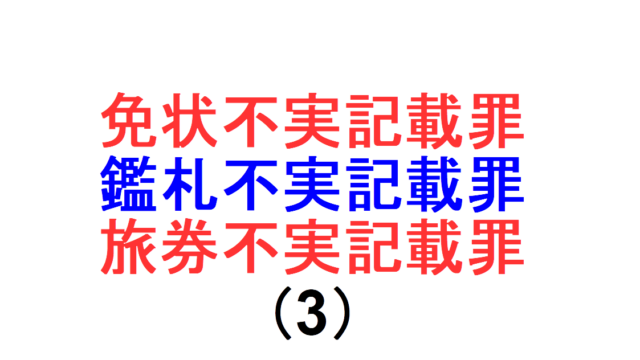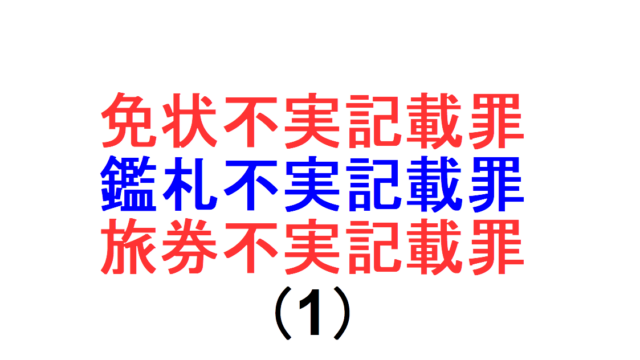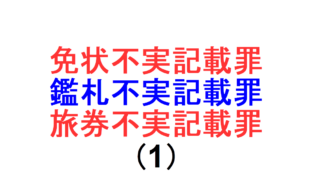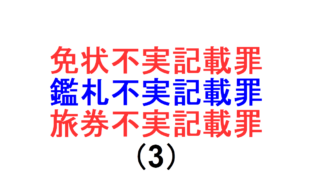免状等不実記載罪(2)~「本罪の行為」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、免状不実記載罪、鑑札不実記載罪、旅券不実記載罪(刑法157条2項)を適宜「本罪」といって説明します。
本罪の行為
本罪の行為は、
公務員に対して虚偽の申立てをし、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせること
をいいます。
※ ここでいう「公務員」の説明は公正証書原本不実記載罪(3)の記事参照
※ ここでいう「虚偽の申立て」の説明は公正証書原本不実記載罪(4)の記事参照
※ ここでいう「不実の記載」の説明は公正証書原本不実記載罪(5)の記事参照
本罪が成立するためには、免状、鑑札又は旅券に、具体的に不実の記載がされたことを要する
本罪が成立するためには、免状、鑑札又は旅券に、
具体的に不実の記載がされたこと
を要します。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(大正4年4月24日)
裁判所は、
と判示ました。
例えば、自動車運転免許証について、都道府県公安委員会に虚偽の住所を申し立て、雨天免許証に虚偽の住所が記載されれば、「具体的に不実の記載がされたこと」に該当します。
自動車運転免許証の更新申請の際、自己の住所について虚偽の申立てをし、その旨不実の記載をさせた行為について、本罪の成立を認めた以下の裁判例があります。
東京高裁判決(平成4年1月13日)
裁判所は、
- 住所が本籍、氏名、生年月日と並んで、それ自体個人特定の重要な資料となり得ることは自明のことである
- 自動車運転者は、一定の要件のもとに、警察官から免許証の提示を求められたときは、これを提示する義務がある(道路交通法95条2項、67条1項)とされているのであるから、これに対応して、運転免許証の個人特定に関する事項に本籍、氏名、生年月日と並んで住所を加えたものと解することができる
- したがって、運転免許証の住所の記載が免許証の証明対象ではなく、免状等不実記載罪の「不実の記載」には含まれず、刑法157条2項の構成要件に該当しないとすることは到底できない
と判示しました。
東京地裁判決(昭和61年7月8日)
裁判所は、
- 運転免許証の記載事項としての住所欄は、本籍欄、氏名欄ともに免許を受けた者を特定する上で必要であるばかりでなく、住所地の管轄公安委員会が行う運転免許証の更新、取消、停止処分等の手続においても必要不可欠であり、したがって、道路交通法上、住所変更があったときは、すみやかに公安委員会に届け出る義務があるとともに、その違反に対して罰則が設けられているのであるから、運転免許証の記載事項として、住所欄がその重要な部分であることは明らかである
とし、運転免許証更新申請をするに当たり、自己の住所について虚偽の申立てをし、その旨不実の記載をさせた行為について、免状不実記載罪の成立が認めました。
東京高裁判決(判昭62年4月13日)
裁判所は、運転免許証の住所欄に虚偽の住所を記載させる行為につき、実質的違法性があるとし、虚偽の住所を記載した運転免許証更新申請書を係員に提出して免許証に不実の記載をさせ、その交付を受け、交通取締警察官に対して行使したことは、免状不実記載罪、不実記載免状行使罪(刑法158条1項)に当たるとしました。
本罪には、不実を記載された免状、鑑札、旅券の下付を受ける行為も包含される
免状、鑑札、旅券は、当該名義人において下付を受けて所持するのでなければその効用が認められないので、本罪には、不実を記載された免状、鑑札、旅券の下付を受ける行為も包含されます。
なので、本罪を犯した者が、不実記載の免状、鑑札、旅券の下付を受けても、別に詐欺罪を構成することはありません。
この点を判示した以下の判例があります(いずれも旅券に関する事案)。
大審院判決(昭和9年12月10日)
裁判所は、
- 他人名義を偽りて、外国旅券下付を制し、その下付を受けたる事実に対しては、刑法第157条第2項を適用すべきものにして、外国旅券規則違反及び詐欺罪を問擬(もんぎ)すべきものに非ず
と判示しました。
裁判所は、
- 係員を欺罔して旅券の下附を受ける行為は詐欺罪にあたらない
と判示しました。