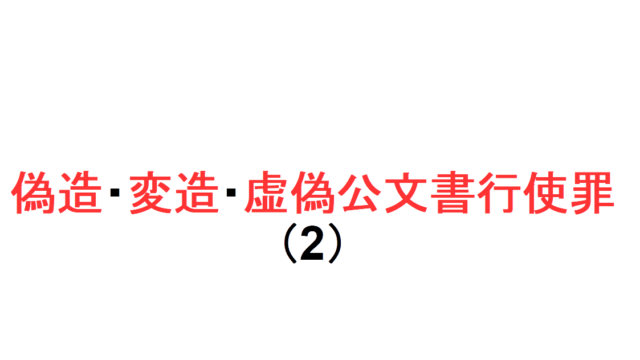偽造公文書等行使罪(10)~他罪との関係⑤「本罪と①預合罪、②加重収賄罪、③窃盗罪、④適正課税法違反との関係」を説明
前回の記事の続きです。
偽造・変造・虚偽公文書行使罪、不実記載公正証書原本行使罪、不実記録電磁的公正証書原本共用罪等(刑法158条)を適宜「本罪」といって説明します。
この記事では、本罪と
との関係を説明します。
① 預合罪との関係
「預合罪」と「公正証書原本不実記載罪・不実記載公正証書原本行使罪」は、併合罪の関係になるとした裁判例があります。
裁判所は、
- 旧商法491条の預合罪(現在は、会社法965条に預合いの罪が規定されている)が成立する場合、不存在会社の設立登記を申請し(公正証書原本不実記載罪)、登記官吏をして商業登記簿の原本にその旨記載させて備え付けさせたときは(不実記載公正証書原本行使罪)、因果関係こそ存するものの、公正証書原本不実記載・不実記載公正証書原本行使罪は、預合罪の構成要件によって包括的に評価し尽される関係になく新たな法益を侵害するものであるから、別に公正証書原本不実記載・同行使罪を構成し、両者の罪の関係は併合罪である
としました。
② 加重収賄罪との関係
虚偽公文書作成罪・偽造公文書行使罪の事実が、加重収賄罪の事実のうち収賄の刑の加重をすべき原因である不正行為の事実に該当する場合には、「加重収賄罪」と「虚偽公文書作成・偽造公文書行使罪」は観念的競合の関係になるとした裁判例があります。
虚偽公文書作成・同行使の事実が加重収賄の刑の加重されるべき原因となる事実である場合の罪数について判示した判決です。
裁判所は、
- 虚偽公文書作成、同行使の事実が加重収賄の事実のうち収賄の刑の加重をすべき原由たる不正行為事実に該当する場合には、その収賄と虚偽公文書作成、同行使の各事実は刑法第54条第1項前段の一罪として処断すべき行為である
と判示しました。
③ 窃盗罪との関係
「有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪」と「窃盗」が併合罪になるとした裁判例があります。
東京高裁判決(平成20年4月24日)
窃盗(未遂)の手段として偽造有印公文書行使が行われた場合であっても、両罪は、牽連犯の関係にはないとした判決です。
事案は、被告人が、コインロッカー内の金員の窃取を企て、検察事務官の身分証明書である検察事務官証票1通を偽造し、これをコインロッカーの管理会社従業員に提示して行使し、同人にコインロッカー計156台を解錠させるなどしてそのコインロッカー内に保管されていた荷物を物色したが、金員の発見に至らなかったため、窃盗の目的を遂げなかったという有印公文書偽造罪、偽造有印公文書行使罪、窃盗未遂罪の事案です。
裁判官は、
- 偽造有印公文書行使と窃盗未遂については、窃盗未遂の手段として偽造有印公文書行使が行われた場合であっても、両罪は、犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず、刑法54条1項後段所定の牽連犯の関係にはないと解するのが相当であるから、有印公文書偽造とその行使とは牽連犯の関係にあるが、これらと窃盗未遂とは併合罪の関係にあると解すべきである
と判示しました。
④ 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律違反との関係
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(適正課税法)違反と本罪の関係について説明します。
海外への不正送金をするため、取扱銀行の担当者に対し、他人名義の偽りの外国送金依頼書兼告知書を提出するとともに、偽造に係る他人名義の外国人登録証明書を提出・行使した場合には適正課税法違反(同法9条1号後段・3条1項1号の罪)と偽造有印公文書行使罪とは観念的競合に当たるとした裁判例があります。
横浜地裁判決(平成15年12月25日)
裁判所は、
- 適正課税法に関する告知書の各提出と偽造有印公文書の各行使はそれぞれ1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから、刑法54条1項前段、10条により各1罪としてそれぞれ重い偽造有印公文書行使罪の刑で処断する
と判示しました。