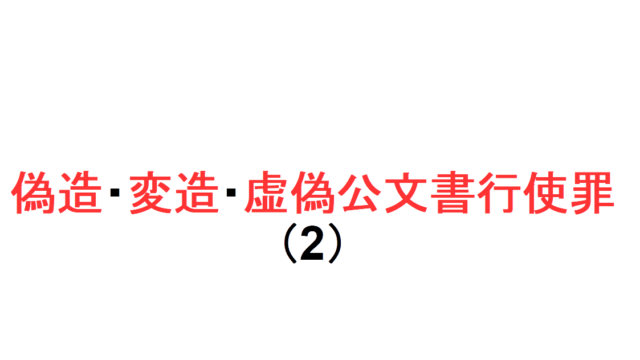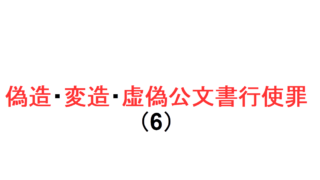偽造公文書等行使罪(5)~「本罪の罪数の考え方」を説明
前回の記事の続きです。
偽造・変造・虚偽公文書行使罪、不実記載公正証書原本行使罪、不実記録電磁的公正証書原本共用罪等(刑法158条)を適宜「本罪」といって説明します。
この記事では、本罪の罪数の考え方を説明します。
数人を経由して偽造文書を行使した場合の本罪の罪数の考え方
包括一罪と認定した事例
1⃣ 詐欺を行う目的で、偽造文書を情を知らない訴訟代理人に交付してこれを裁判所に提出させたときは、訴訟代理人に対して偽造文書の行使があるのはもちろんのこと、裁判所に対しても行使の事実を認めるのが正当であり、これらを法律上より観察すれば、以上の行為を一括して偽造文書の行使を完成したものと認めるべき旨判示した以下の判例があります。
大審院判決(大正3年11月5日)
裁判所は、
- 詐欺を為す目的をもって、偽造文書を情を知らざる訴訟代理人に交付し、裁判所に提出せしめたるときは、その代理人に対して偽造文書の行使あるはもちろん、訴訟代理人の手を借り、裁判所に対し欺罔手段を施すものにはかならざれば、裁判所に対しても行使の事実を認るを至当とす
と判示しました。
2⃣ 偽造文書を相手方の代理人を経由して相手方に交付せしめた行為は、法律上包括してこれを観察すると、単一の偽造文書行使罪として包括一罪として処分すべきものと判断した判例があります。
大審院判決(大正4年3月5日)
裁判所は、
- 偽造文書を相手方の代理人を経由して相手方に交付せしめたる行為は、法律上、包括してこれを観察し、単一なる偽造文書行使罪をもって処断すべきものとす
と判示しました。
複数の偽造文書等を一括して行使した場合の本罪の罪数の考え方
観念的競合と認定した事例
複数の偽造文書を一括して行使した場合には、複数の偽造文書行使罪は、観念的競合となります。
郵便貯金通帳(※当時は公文書であった)の受入れ又は払戻しに関する各記載は、各々その受入れ又は払戻しに関する事項を証明するものとしてそれぞれ1個の公文書といえるのであるから、受入れ又は払戻しに関する複数欄が偽造された貯金通帳を行使する行為は、各偽造公文書行使罪の観念的競合になると判断した判例があります。
大審院判決(昭和7年2月25日)
裁判所は、
- 郵便貯金通帳における受入れ又は一部の即時払いに関する各記載は、各1個の公文書を成し、その偽造は各記載ごとに公文書偽造罪を構成す
- 被告人は、行使の目的をもってほしいままに通帳の各貯金受入欄又は各払出欄に関する部分に各郵便局長の印影を顕出し、そのほか所要箇所に記入し、各日付印又はその割印影を顕出して各郵便貯金の受入れ又は払戻しを為したる趣旨の各文書を偽造したる上、右貯金通帳各欄に関する記載が真正なるものの如く装い、右通帳を提出行使したるものとす
- 然らば、各偽造公文書行使の行為は、それぞれ1個の行為にして数個の罪名に触れる場合に該当する
と判示し、各偽造公文書行使罪は観念的競合になるとしました。