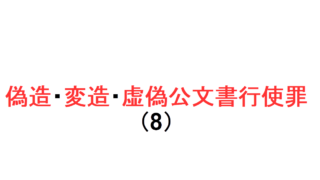偽造公文書等行使罪(9)~他罪との関係④「本罪と横領罪との関係」を説明
前回の記事の続きです。
偽造・変造・虚偽公文書行使罪、不実記載公正証書原本行使罪、不実記録電磁的公正証書原本共用罪等(刑法158条)を適宜「本罪」といって説明します。
この記事では、本罪と横領罪(刑法252条)の関係を説明します。
横領罪との関係
偽造文書行使罪と横領罪とが牽連犯になるとした判例
自己の占有する他人の財物を横領するにつき、偽造文書の行使によってその領得の意思を実現したときは、偽造文書の行使が横領に先行する場合であろうと同時であろうと、行使は横領の手段の関係に立つから、偽造文書行使罪と横領罪は牽連犯(刑法第54条1項後段)の関係になります。
ただし、横領罪の成立後にその犯跡を隠ぺいするために偽造文書行使罪を実行したときは、偽造文書行使罪と横領罪に牽連関係はなく、併合罪となります。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(大正11年9月19日)
裁判官は、
- 自己の占有する他人の財物を横領するにつき、偽造文書行使により自己領得の意思を実現せしめたるときは、偽造文書行使の罪はその行為が横領の行為に先立つと、また、同時なるとを問わず、横領罪に対して刑法第54条にいわゆる手段たる関係を有すべしといえども、横領罪成立後において、その犯跡隠蔽せんがために偽造文書行使罪を実行したるときは、二罪は各自独立し、その間に手段たる牽連関係なきものとす
と判示しました。
不実記電磁的公正証書原本供用罪と横領罪とが観念的競合になるとした判例
不実記電磁的公正証書原本供用罪と横領罪とが観念的競合になるとした以下の判例があります。
他人Aが所有する建物をAのために預かり保管していた者が、金銭的利益を得ようとして、同建物の電磁的記録である登記記録に不実の抵当権設定仮登記を了したことにつき、電磁的公正証書原本不実記録罪・不実記録電磁的公正証書原本供用罪が成立するとともに、横領罪の成立を認め、不実記電磁的公正証書原本供用罪と横領罪とは観念的競合の関係に立つとしました。
事案の概要は、C社の実質的代表者である被告人が、甲社と医療法人Aらとの間の裁判上の和解に基づき、C社からAらに順次譲渡されたものの所有権移転登記が未了であった建物をAのために預かり保管中、原状回復を口実にしてAらから解決金を得ようと企て、登記官に虚偽の申立てをして、同建物及び敷地に係る各登記記録上に、共犯者が理事長を務める医療法人Dを登記権利者とする不実の抵当権設定仮登記を記録させ、これを閲覧できる状態にさせて用に供したというものです。
弁護人は、
- 本登記とは異なり、仮登記には順位保全の効力があるだけであるから横領罪は成立しない
と主張するとともに、
- 抵当権設定仮登記が不実であることを前提に電磁的公正証書原本不実記録罪及び同供用罪の成立を認めながら、その一方で横領罪にも当たるとするのは自己矛盾である
といった趣旨の主張をしました。
これに対し、裁判所は、
- 本件仮登記は不実であるから、電磁的公正証書原本不実記録罪及び同供用罪が成立することは明らかである
とした上で、横領罪の成否については、
- 仮登記を了した場合、それに基づいて本登記を経由することによって仮登記の後に登記された権利の変動に対し、当該仮登記に係る権利を優先して主張することができるようになり、 これを前提として、不動産取引の実務において、仮登記があった場合には、その権利が確保されているものとして扱われるのが通常である
- 以上の点にかんがみると、不実とはいえ、本件仮登記を了したことは、不法領得の意思を実現する行為として十分であり、横領罪の成立を認めた原判断(※原判決の判断)は正当である
- また、このような場合に、同罪と上記電磁的公正証書原本不実記録罪及び同供用罪が併せて成立することは、何ら不合理ではないというべきである
- なお、本件仮登記による不実記録電磁的公正証書原本供用罪と横領罪とは観念的競合の関係に立つと解するのが相当である
としました。