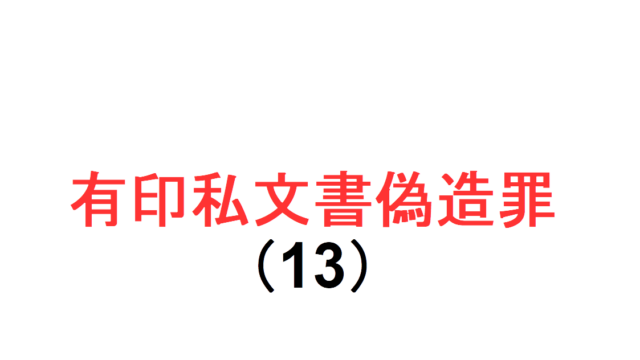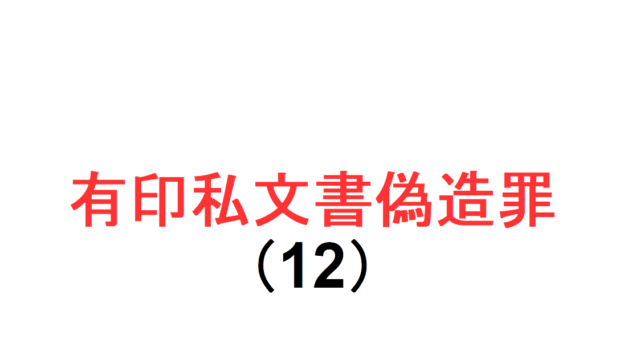有印私文書偽造罪(1)~「有印私文書偽造罪とは?」「未遂規定はない」などを説明
これから15回にわたり、有印私文書偽造罪(刑法159条)を説明します。
有印私文書偽造罪とは?
有印私文書偽造罪は、刑法159条の第1項に規定があり、
第1項 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する
第2項 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする
第3項 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する
と規定されます。
罪名
第1項の罪名は「有印私文書偽造罪」となります。
第2項の罪名は「有印私文書変造罪」となります。
第3項の罪名は「無印私文書偽造罪」「無印私文書変造罪」となります。
法定刑
有印私文書偽造罪(第1項)、有印私文書変造罪(第2項)の法定刑は「3月以上5年以下の拘禁刑」です。
無印私文書偽造罪・無印私文書変造罪(第3項)の法定刑は「1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金」です。
有印私文書偽造罪(第1項)、有印私文書変造罪(第2項)は、無印私文書偽造罪・無印私文書変造罪(第3項)より重く処罰されます。
これは、他人の印章・署名のある私文書の方がそれらを欠く私文書に比べて高い信用性が認められるためです。
私文書の無形偽造、無形変造は処罰されない(刑法上、虚偽私文書作成罪、私文書変造罪はない)
刑法159条の罪は、私文書の
- 有形偽造
- 有形変造
を罰するものです。
私文書の無形偽造は、刑法160条(虚偽診断書作成罪、虚偽検案書作成罪、虚偽死亡証明作成罪)の場合を除き処罰されません。
※ 有形偽造とは、文書の作成権限がない人が他人名義の文書を作成することをいいます。
※ 無形偽造とは、文書の作成権限がある人が事実でない内容の文書を作成することをいいます。
私文書も、公文書と同じく、文書に対する公共的信用を保護するためには、文書の有形偽造、有形変造を処罰して形式的真正をまず確保しなければ、その目的を十分に達成できません。
他方、私文書は、公文書と異なり、虚偽記載が社会生活に大きな影響を持ち得る医師作成の診断書のような一定の文書を除き(虚偽診断書作成罪:刑法160条)、内容の真実性をも刑罰をもって確保しなければならないという要請はそれほど高くないと考えられるため、私文書の無形偽造、無形変造は不処罰となっています。
よって、刑法では、虚偽私文書作成罪、私文書変造罪はありません。
私文書偽造・変造罪は、公文書偽造・変造罪に比較し軽い刑が定められている
私文書偽造・変造罪は、公文書偽造・変造罪に比較し軽い刑が定められています。
これは、私文書に対する公共的信用性が公文書におけるそれより類型的に低いことを考慮したものです。
文書作成者の身分により差をもうけたものではありません。
この点を判示した判例がありあす。
裁判所は、
- 刑法第156条は信用度の高い公文書の無形偽造を私文書と異って特に処罰することにしたものであって、その保護法益は公文書の信用性に存し、行為者が公務員であるか否かによってその保護に軽重を設けた規定ではない
と判示しました。
裁判所は、
- 刑法第158条第1項の偽造公文書行使罪の法定刑が同法第161条第1項の偽造私文書行使罪のそれより重いのは、その保護法益である公文書の信頼度が私文書のそれより高いことに基くものであって、その文書作成名義者の身分による差別ではない
と判示しました。
未遂規定はない
刑法159条の罪に未遂罪を罰する規定はありません。
しかし、私印偽造罪、私印不正使用罪、偽造私印使用罪を規定する刑法167条が、本罪の未遂に当たる行為の一部を処罰する役割を果たしています。