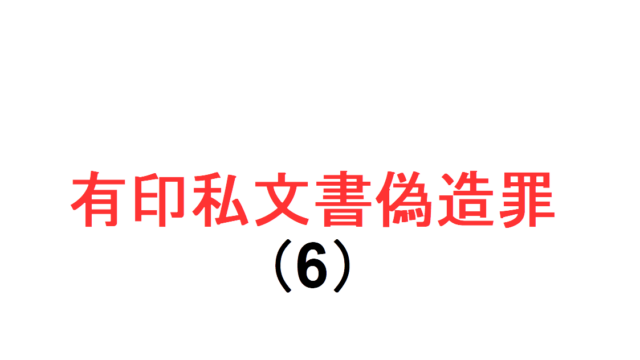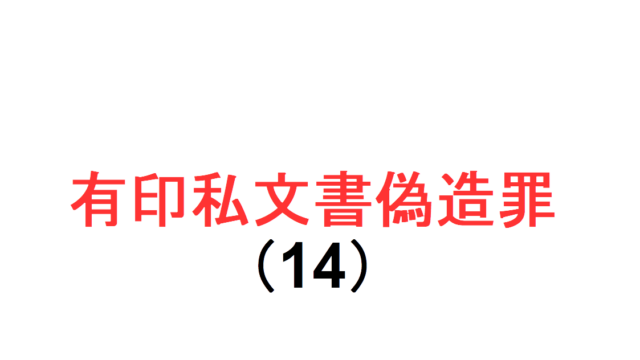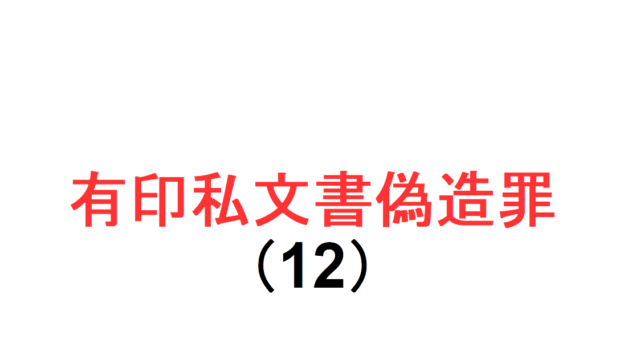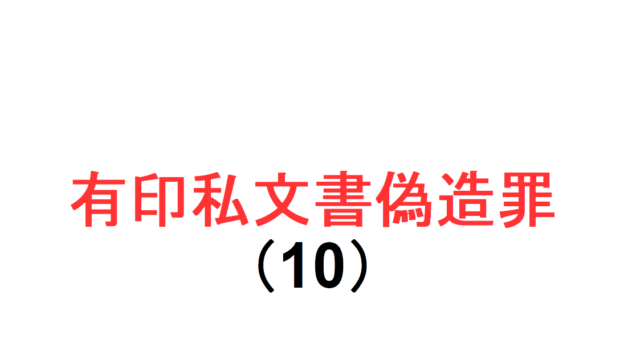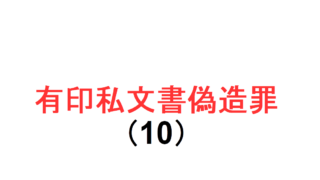有印私文書偽造罪(11)~行為⑦「代理権・代表権を超越・濫用した場合の文書偽造罪の成否」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、有印私文書偽造罪(刑法159条)を説明します。
代理権・代表権を超越・濫用した場合の文書偽造罪の成否
代理権・代表権を超越・濫用した場合の文書の作成名義人
代理・代表名義の文書は、代理人・代表者の意思表示の効果が本人(代理人・代表者に代理権・代表権を与えた者)に帰属する性質の文書であるがゆえに、本人の意思に由来する文書とみられることになり、文書の作成名義人は本人ということになります(この点の説明は前回の記事参照)。
これに対し、文書の名義人ではなく、文書の作成者については、代理・代表権限濫用の場合は本人であり、権限超越の場合は代理人・代表者になると考えられています。
つまり、本人から代理権・代表権を授与された代理人・代表者がその権限の範囲内で文書を作成した場合には、たとえ自己又は第三者の利益を図るためであっても(代理・代表権の濫用)、その文書作成は本人の意思に基づくものといえるので、作成者は本人となると考えられるのに対し、代理人、代表者がその権限を超越して文書を作成した場合には、たとえ本人の利益を図るためであっても、その文書作成は本人の意思に基づかないものとなるから、作成者は代理人・代表者となると考えられています。
代理権・代表権の超越
代理・代表資格の冒用して文書を作成した場合、文書偽造罪が成立します(詳しくは前回の記事参照)。
そして、代理権・代表権を有する者が、その権限を越えて本人名義の文書を作成した場合も、代理・代表資格の冒用の一種となるので、文書偽造罪が成立します。
判例は、
- 他の事件に使用する目的で預かっていた他人名義の白紙委任状を、連帯保証人となる保証契約締結の委任状とした場合(大審院判決 明示42年12月2日)
- 他人の山林の分筆を承諾させ、白紙に調印させてその名義の分筆承諾書を作成するに当たり、ほしいままに質権放棄の旨を併せて記載した場合(大審院判決 大正6年11月5日)
- 叔父の承諾を得て、その土地に抵当権を設定し、他人から300円の融資を受けようとするに当たり、叔父の印章を託されたことを奇貨として、その承諾の範囲を越え、更に5筆を加えて担保とし、650円を借り入れる旨の借用証書を作成した場合(大審院判決 昭和7年10月27日)
につき、いずれも文書偽造罪が成立するとしています。
代理権・代表権の濫用
代理権・代表権を有する者が、その権限の範囲内でこれを濫用して本人名義の文書を作成した場合に文書偽造罪が成立するか否かについては、事件の事案ごとに異なります。
この点に関する以下の判例があります。
大審院判決(明治42年12月13日)、大審院判決(大正6年12月20日)
会社の取締役が、会社のためではなく、専ら自己又は第三者の利益を図るために会社名義の文書を作成した場合は私文書偽造罪に当たるとしました。
大審院判決(大正8年7月9日)
上記判例と同様の事案で、専ら本人たる会社の利益を図る目的に出た場合にはたとえ作成した文書の内容が虚偽でも偽造にはならないとしました。
大審院判決(大正11年10月20日)
刑事連合部の判決で、代理人又は代表者が、自己又は第三者の利益を図る目的で、代理権・代表権を濫用した場合でも偽造罪は成立しないとしました。
逸脱か濫用か紛らわしい場合における文書偽造罪の成否
逸脱か濫用か紛らわしい場合における文書偽造罪の成否についての判例として、以下のものがあります。
大審院判決(大正12年3月13日)
会社の支配人が、会社の営業範囲に属しない売買に関し、自己のために、会社又は支配人の名義で売買契約書等の文書を作成した事案につき、私文書偽造罪が成立するとしました。
数人の代表取締役が共同して会社を代表する定めがあるのに、その一人である被告人が、他の代表取締役の署名・印章を冒用して共同代表の形で会社名義の文書を作成した事案につき、そうした定めがある場合、各代表取締役は、他の代表取締役と共同して会社を代表することができるだけで、単独で会社を代表する権限はないから文書偽造罪を構成するとしました。
漁業協同組合参事として、水産業協同組合法の規定により旧商法38条1項の支配人に関する規定が準用される地位にあった被告人が、組合内部の定めでは、組合員等のために融通手形として振り出す組合長名義の約束手形の振出権限はすべて専務理事に属するとされているにもかかわらず、組合長や専務理事の承認を受けずに、組合長振出名義の融通手形を作成した事案につき、被告人は単なる起案者、補佐役として手形作成に関与していたにすぎず、作成権限そのものがなかったとみるべきであるとして有価証券偽造罪が成立するとしました。