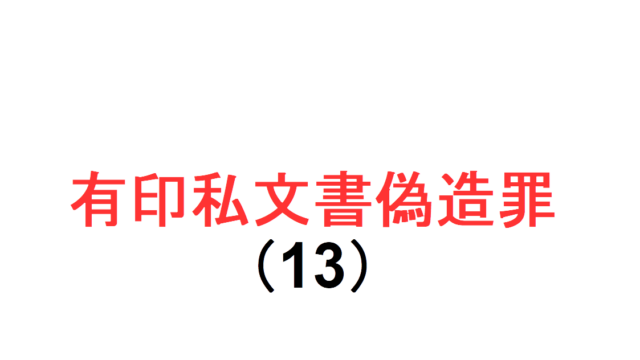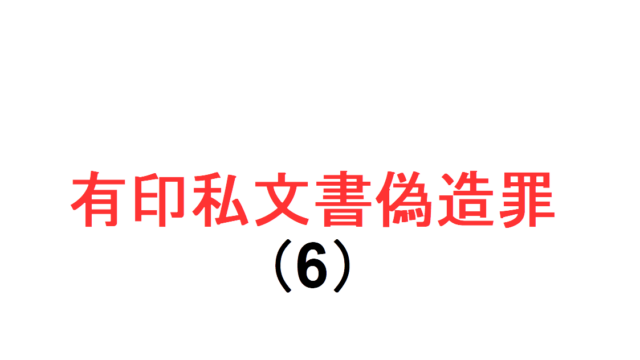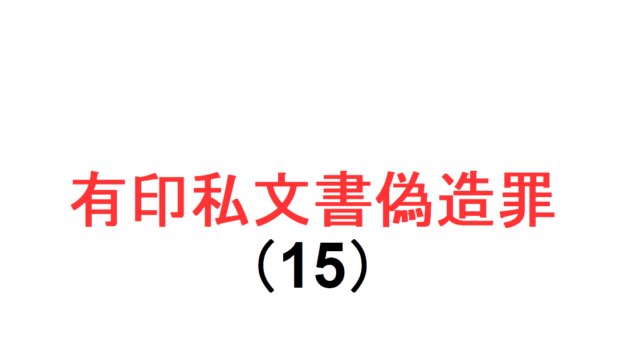有印私文書偽造罪(3)~「本罪の客体である『権利、義務に関する文書』」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、有印私文書偽造罪(刑法159条)を適宜「本罪」といって説明します。
本罪の客体である「権利、義務に関する文書」の説明
本罪の客体は、
他人の権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画(とが)
です。
ここでいう「文書」は「私文書」、「図画」は「私図画」と呼ばれます(「私文書」「私図画」の説明は前回の記事参照)。
この記事では、本罪の客体である「権利、義務に関する文書」を説明します。
「権利、義務に関する文書」の意義
1⃣ 本罪は、「権利、義務に関する文書」と「事実証明に関する文書」とを対象とします。
「権利、義務に関する文書」について、学説において、
- 権利、義務の発生、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする文書であるとする見解
- より広く、権利、義務の発生、変更、消滅の要件となる文書のみならず、その原因となる事実について証明力のある文書を含むとする見解
とがあります。
「権利、義務に関する文書」と併せて「事実証明に関する文書」を客体としている点からすると、権利、義務の消長の要件となる文書のみならず、その存否を証明する文書も含めてよいと考えられています。
この点、裁判例では、仙台高裁判決(平成2年10月1日)が、
- 直接法律的にある権利・義務を発生・変更・消滅させる効力を持つものでなくとも、事実上権利・義務に変動を与える可能性を有する文書であれば、これに該当すると解するのが相当
と判示しています。
2⃣ 「権利、義務に関する文書」の「権利、義務」は、
- 私法上のものであると、公法上のものであるとを問わない
- 売買、貸借、贈与、交換などの財産関係に関するものでもよい
- 婚姻、養子縁組の届出書のような身分関係に関するものでもよい
- 民事、刑事の訴訟に関するものでもよい
とされます。
仙台地裁判決(平成15年5月28日)は、無断で結婚させた他人の男女1組の離婚届を偽造し、役所に提出してこれを受理させた行為につき、有印私文書偽造罪、偽造有印私文書行使罪(刑法158条1項)、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)、不実記載公正証書原本行使罪(刑法158条1項)の成立を認めています。
「権利、義務に関する文書」の具体例
判例が「権利、義務に関する文書」と認めたものとして、以下の文書があります。
- 教会の世話掛を嘱託する辞令書(大審院判決 大正2年4月17日)
- 送金を依頼する電報頼信紙(大審院判決 大正11年9月29日)
- 宛名のない借用証書(大審院判決 大正4年9月2日)
- 譲受人を表示していない偽造の債権譲渡証(大審院判決 大正12年5月24日)
- 虚無の権利の催告書(大審院判決 昭和8年5月23日)
- 弁論再開申立書(口頭弁論が終結した後に、再度、口頭弁論を開くことを申し立てる書類(大審院判決 昭和14年2月15日)