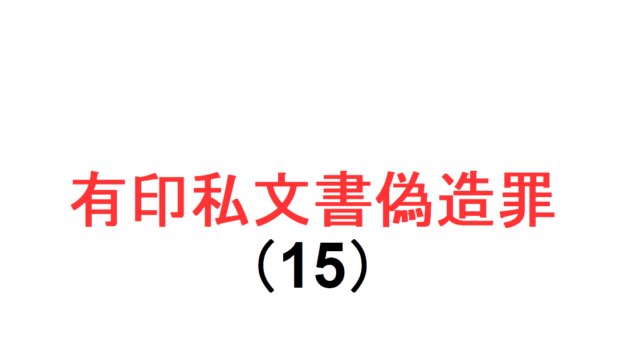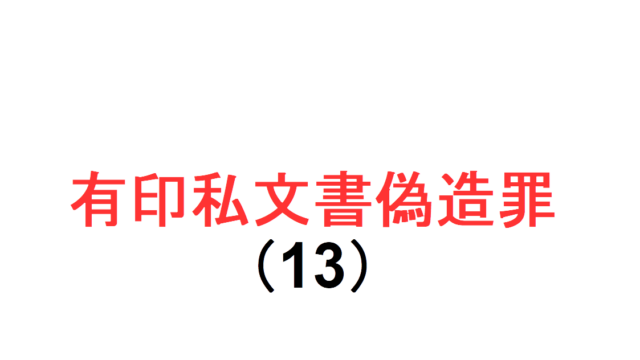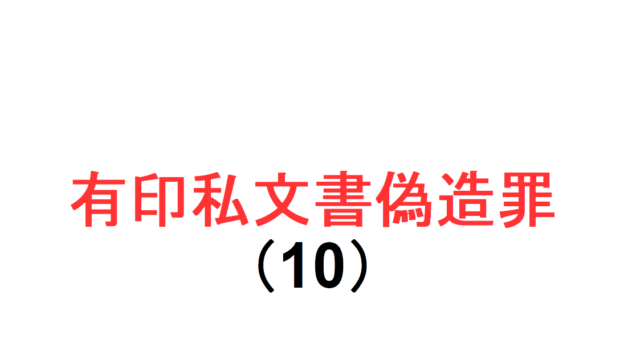有印私文書偽造罪(5)~行為①「『他人の印章・署名を使用して』とは?」「『偽造した他人の印章、署名を使用して』とは?」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、有印私文書偽造罪(刑法159条)を適宜「本罪」といって説明します。
本罪の行為
本罪の行為は、行使の目的を持って、
① 他人の印章、署名を使用して、権利、義務又は事実証明に関する文書、図画を偽造すること
又は
② 偽造した他人の印章、署名を使用して、権利、義務又は事実証明に関する文書、図画を偽造すること
です。
この記事では、上記の
- 「他人の印章・署名を使用して」の意味
- 「偽造した他人の印章、署名を使用して」の意味
を説明します。
① 「他人の印章・署名を使用して」とは?
「他人の印章、署名を使用して」とは、
他人の真正な印章・署名を不正に使用すること
の意味です。
例えば、
- 他人の捺印・署名のある白紙を利用すること
- 捺印・署名のある白紙文書に補充権を超えて補充すること
- 文書の内容を偽り、他の事項に関する文書であると偽って署名・捺印させること
がこれに当たります。
参考となる以下の判例があります。
大審院判決(大正4年10月19日)
裁判官は、
- 文書の内容を偽り、他の事項に関する文書なるがごとく欺き、これに作成者として他人に署名押捺せしめ、これを利用して一定の文書を完成したるときは、たとえその署名者若しくは代筆者が署名中のある文字を誤記したる場合といえども、当該署名者の文書を偽造したるものという得べきものとす
と判示しました。
「印章」について
印章について述べた判例として、以下のものがあります。
大審院判決(大正14年10月10日)
書画の雅号印は、特定人を表彰するに足りるから、印章であると判示した判決です。
裁判所は、
- 刑法第159条第1項にいわゆる事実証明に関する文書とは、人類の社会生活に交渉を有する事実を証明するに足るべき文書を指称すると解するを相当とす
と判示しました。
大審院判決(明治42年10月21日)
有合印を用いた場合は他人の印章を使用したことにはならないとした判決です。
裁判所は、
- 刑法第159条第1項にいわゆる他人の印章中には、有合印を包含せざることはもちろんの如くなるも、名義人が真実筆記したる署名を冒用して文書を作成したる場合は、同条項の前段に当たり、新たに他人の名義を冒署して文書を作成したる場合は、同条項の後段に当たる
と判示ました。
「署名」について
判例は、署名について、作成者が誰であるかを示すに足りる記名(印刷やゴム印で押された氏名)でよく、自署である必要はないとします。
その記名が、本人の氏名を表すものであると、その通称又は商号を表すものであると、また、本人の自署になると、他人をして代筆させたのであると、若しくは印刷によって表出したのであるとを問わないとしています。
大審院判決(明治45年5月30日)
裁判所は、
- 作成者たる他人の記名を使用して文書を偽造したる以上は、その記名が本人の氏名を表すものなると商号若しくは通称を表すものなるとを問わず、また本人の自筆なると本人が他人をして代筆せしめたると若しくは印刷によりて表出したるとを論ぜず刑法第159条第1項の文書偽造罪を構成す
と判示しました。
しかも、氏と名とを併記する必要もなく、それを各別に示した場合、しかも、それが片仮名で、氏のみを表記した場合でもよいとされます。
大審院判決(明治43年1月30日)
裁判所は、
- 刑法にいわゆる署名とは、通例一定の人が自己を表彰するために文字をもってその氏名を表記するものを指称すれども、単に片仮名を用い、その氏名のみを表記したる場合において、これを署名に非ずというを得ず
- 一定の関係ある者の間においては、単に氏若しくは名のみをもってするも、その人を表彰するに足るが故に、氏若しくは名のみを表記するも、なおこれを署名といわざるを得ず
と判示しました。
このほか、判例は、
- 氏名のほか商号その他の符号文字を用いた場合(大審院判決 明治43年3月10日)
- 屋号を記した場合(大審院判決 明治43年9月30日)
- 普通取引上に使用される銀行の名義を表示する略号を用いた場合(大審院判決 大正4年2月20日)
- 雅号を用いた場合(大審院判決 大正14年10月10日)
でも、それによって特定人を表彰し得るのであれば署名が使用されたこととなるとしています。
② 「偽造した他人の印章、署名を使用して」とは?
1⃣ 「偽造した他人の印章、署名を使用して」とは、
偽造した他人の印章・署名を使用すること
の意味です。
2⃣ 行為者自身が偽造したものであると、他人が偽造したものであるとを問いません。
3⃣ 偽造は、必ずしも行使の目的に出たものであることを要しません。
4⃣ 代理、代表名義を冒用して文書を作成した場合は(例えば、法人名義の文書を作成して社判を押捺した場合)、その印章、署名は、代理、代表資格ありと偽った本人、法人のものであることが必要です(最高裁決定 昭和45年9月4日)。
そうすると、法人の場合、署名に記号を含まないとすると、法人の印章がない限りすべて刑法159条3項の無署名の私文書ということになります。