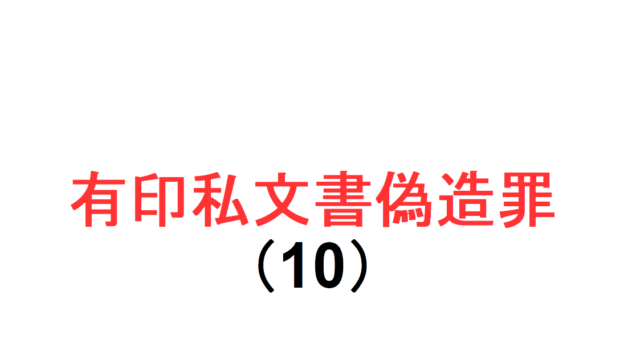有印私文書偽造罪(6)~行為②「『行使の目的』とは?」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、有印私文書偽造罪(刑法159条)を適宜「本罪」といって説明します。
本罪の行為
本罪の行為は、行使の目的を持って、
① 他人の印章、署名を使用して、権利、義務又は事実証明に関する文書、図画を偽造すること
又は
② 偽造した他人の印章、署名を使用して、権利、義務又は事実証明に関する文書、図画を偽造すること
です。
この記事では、上記の「行使の目的」の意味を説明します。
「行使の目的」とは?
1⃣ 文書の偽造・変造及び虚偽文書の作成は、いずれも「行使の目的」をもって行われることが必要とされています。
行使の目的とは、
他人をして偽造・変造文書を真正な文書と誤信させ、虚偽文書を内容の真実な文書と誤信させようとする目的
をいいます。
2⃣ 文書の偽造・変造がこうした目的に出たものである以上、偽造・変造罪に要する主観的要件は常に具備するものと解されています。
他人をして偽造文書を真正文書と誤信させる積極的な目的まではなかったとしても、その危険が実在することを意識して、その目的とするところの用に供しようとするときは、行使の目的が失われません。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(大正2年12月6日)
裁判所は、
- 私文書偽造行使罪は、行使の目的をもって文書を偽造し、これを行使するによりて成立する犯罪なるをもって、本罪の構成要件としては、犯人に偽造手形を行使するの意思あることを必要とし、犯人にこの意思ありとするには、犯人が人をして真正の文書なりと誤信せしむる目的をもってこれが偽造を為したることを要すると同時に、文書の偽造がこの目的に出たるときは、文書偽造罪に要する主観的条件は常に具備するものとす
- また、犯人の目的は人をして偽造の文書を真文書なりと誤信せしむるに在せざる場合といえども、犯人がこの危険の実在することを意識し、これをその目的とするところの用に供せんと企てたるときは、なお行使の目的をもて文書を偽造したるものたることを失わざるものとす
- しかれども、文書の信用を害すべき危険が客観的には実在するも、偽造者が主観的に全然これを否定し、又は全然これを意識いせざりし場合においては、いわゆる行使の目的なきものにして、文書偽造罪は主観的要件の欠缺によりて成立せざるものとす
と判示しました。
3⃣ 行使の目的は、必ずしも確定的な目的であることを要せず、未必条件付で行使する目的であってもよいとされます(大審院判決(大正11年4月11日)。
4⃣ 行使の目的として、他人を害し、又は自己を利する意思が存在することまでは求められていません。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(明治41年11月9日)
裁判所は、
- 文書偽造行使罪の成立には、文書の偽造及び行使あることをのほか、その行使が実害を生じ、又は生じ得べきものたることを必要とするも、被告において他人を害し、又は自己を利するの意思ありたるや否やは問うところに非ず
と判示しました。
大審院判決(明治43年12月13日)
裁判所は、
- 文書偽造罪の成立には、文書の形式又はその内容を偽りたる所為が抽象的に該文書の信用を害すべき危険あるのみをもって足り、これをほかにして特定の人に対し、具体的に損害を与え、又はこれを与えるの危険あることを要せず
と判示しました。
文書をその本来の効用に従って使用する目的がなくとも、他の一定の効用を果たすべく真正な文書として使用する目的さえあれば行使の目的があると認められる
必ずしも文書をその本来の効用に従って使用する目的がなくとも、他の一定の効用を果たすべく真正な文書として使用する目的さえあれば行使の目的があると認められます。
これを認めた裁判例として、以下のものがあります。
大審院判決(昭和7年6月8日)
私通の相手方女性から将来のために貯金をしてくれるよう懇請されたものの、預金すべき金員がなかったことから郵便貯金通帳を偽造してこれを同人に贈与しようと考え、偽造した事案で、行使の目的があると認められました。
市選挙管理委員会の主事として委員会に関する事務に従事していた被告人が、市長及び市会議員選挙の終了後に投票通知書又は投票通知再交付書を再製してこれを市選挙管理委員会事務局に備え付けた事案で、行使の目的があると認められました。
裁判所は、
- 被告人において、投票通知書又は投票通知再交付書を市町村選挙管理委員会が公職選挙法施行令31条の規定(市町村の選挙管理委員会は特別の事情がない限り投票の期日の前日までに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならないとの規定)に基づき投票期日の前日までに選挙人に交付すべき入場券に代わるべき文書としての本来の用途に供する目的はなかったが、同委員会が同令45条の規定(選挙に関する書類を当該選挙によって公職に就任した者の任期間当該選挙管理委員会で保存しておくことを命じている規定)により選挙人が投票期日に出頭し投票したことを証する資料として保存しなければならない文書として使用する目的があった以上、行使の目的があったものといわなければならない
旨判示しました。
偽造であることの情を知る宛名人に文書を交付した場合でも、宛名人が更に他人に対してこれを行使し得ることが予想できるのであれば、行使の目的があると認められる
直接的には、偽造であることの情を知る宛名人に文書を交付した場合でも、宛名人が更に他人に対してこれを行使し得ることが予想できるのであれば、行使の目的(他人をして偽造文書を真正な文書と誤信させ、虚偽文書を内容の真実な文書と誤信させようとする目的)があると認められます。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(大正2年4月29日)
裁判所は、
- 偽造文書の行使は、必ずしも宛名人に対してのみ行われるに限らず、名宛人その情を知るも、なお他にこれを行使するを得べきをもって、苟も真正のものとしてその効用を為さしむる目的をもって偽造せられたる以上、始めより情を知れる者にこれを交付したるに過ぎざる場合においてもまた刑法第159条第1項に行使の目的をもって文書を偽造しとあるに該当するものとす
と判示しました。
裁判所は、
- 何人かにより真正な文書と誤信される危険があることを意識しながら文書を偽造する以上、「行使の目的」をもって文書を偽造するものと解して差し支えなく、偽造者自らこれを行使する意思があるか、あるいは他人をして行使させる意思があるかは問うところではない
としました。
行使の目的の存在時期
行使の目的は、偽造行為の当時に存在しなければならないことは条文上も当然といえますが、必ずしも偽造の当初から特定した事実に向けられている必要はなく、抽象的ではあっても後に現実化し得るのであればそれで足りるとされます。
なお、行使の目的で偽造行為に及べばその時点で偽造罪が成立するので、その後その文書が実際に行使されたかどうかは、偽造罪の成否に影響を与えるものではありません。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(明治43年1月27日)
裁判所は、
- 偽造文書の行使は、偽造の当初において特定する事実たることを要す
- 犯人が後日に至り該文書を行使したるときは、その行使は即ち偽造の目的たる所為にしてその結果というを妨げず
と判示しました。
行使の目的が認められない場合
行使の目的があると認められない旨判断した裁判例としては、以下のものがあります。
札幌地裁判決(昭和39年6月24日)
拾得した他人名義の運転免許証に自己の写真を貼付したり、その氏名欄等を改ざんした事案において、偽造の手段、方法がいたって稚拙であり、被告人が言うように、「いたずら半分の気持から自分の免許証として楽しみに持っていたいという気持ち」から改ざんに及んだものと認定して、行使の目的を否定しました。
大阪地裁判決(昭和47年7月10日)
他人名義の運転免許証に自己の写真を貼付したり、その氏名欄等を改ざんした上、無免許運転をする際に携帯していたという事案において、自動車運転免許の試験を数回受験したけれどもいずれも不合格になっていた被告人が、友人ら周囲の者から嫌味を言われたり馬鹿にされていたため、自己も運転免許証を持っているということを友人らに誇示したいという自己の虚栄心を満足させる目的で改ざんに及んだものと認定して、行使の目的を否定しました。
鹿児島地裁判決(平成17年12月16日)
寮建設費用名下に農協が加入する連合会から融資金を詐取しようと企て、市建築主事名義の確認済証を勝手に作成して、農協を介して同連合会に提出したという事案において、被告人としては、農協も連合会もこれが偽造であることは分かっているはずであるとの認識を有していたものであると認定した上、被告人も、同文書が農協を通じて連合会に渡った後にどのように用いられるのかという点については、深く考えず、明確に認識していなかったと考えられるから、行使の目的を認めるにはなお合理的な疑いが残ると判断しました。
行使の目的は判決で判示される必要がある
1⃣ 文書偽造罪は、行使の目的で文書を偽造することによって成立する犯罪です。
なので、偽造罪が認定される場合には、判文上も行使の目的をもって偽造したことが明示される必要があります。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(大正3年10月28日)
裁判所は、
- 文書偽造罪は、行使の目的をもって文書を偽造するに非らざれば成立せざるが故に、判文上、行使の目的をもって偽造したることを明示するか若しくはこれを認め得べき事実を判示するに非ざれば、未だもって本罪として擬律し得ざるものとす
と判示しました。
大審院判決(大正7年1月24日)
裁判所は、
- 被告らが文書偽造したる行為に対し、刑法第159条第1項を適用しながら、他人に対しこれを行使するの目的に出でたるものなるや否を明示せざる判決は理由不備の不法あるものとす
と判示しました。
2⃣ 文書の具体的使途がどのようなものであるかということは必ずしも犯罪の成否に影響を及ぼす事柄ではないことから、判文上、行使の目的があることを判示しさえすれば足り、犯人が偽造文書をどのような用途に供しようとしたかという点についてまで詳細に示す必要はないとされます。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(大正5年9月22日)
裁判所は、
- 証書の偽造が行使の目的に出でたる以上は、常に犯罪を構成することもちろんにして、その使途の如何は犯罪の成否に影響を及ぼすべきことなきをもって、証書偽造罪を断ずる判決において、必ずしも犯人が偽造証書をいかなる用に供せんとしたるやを詳示するの要なし
と判示しました。