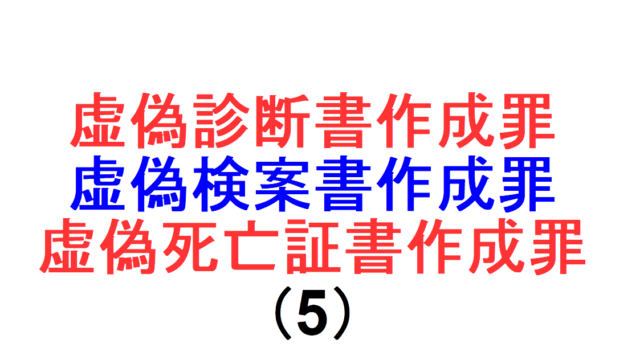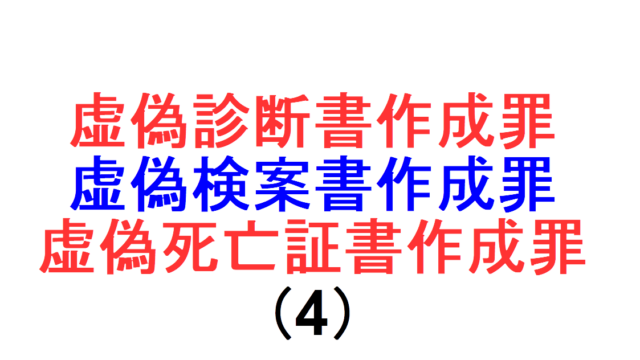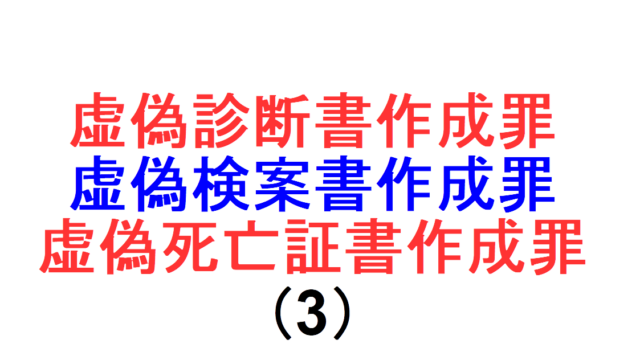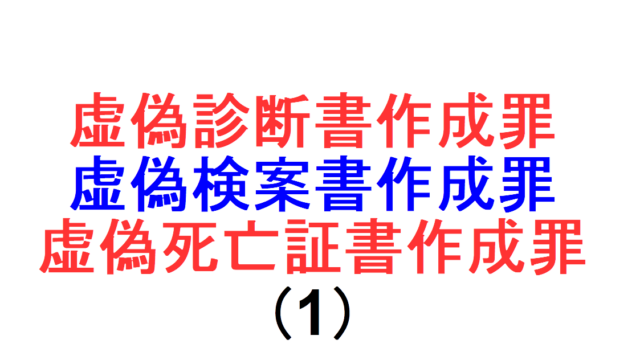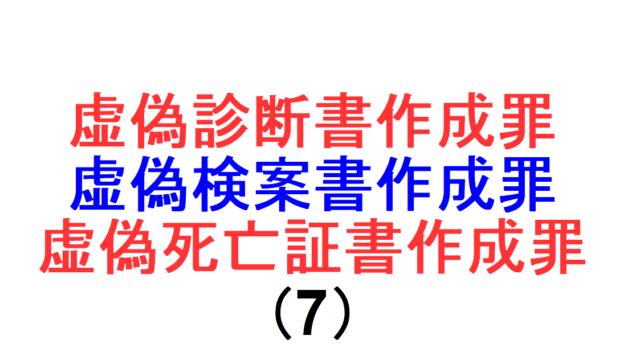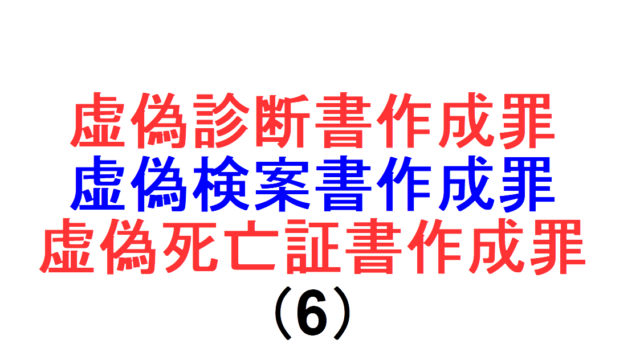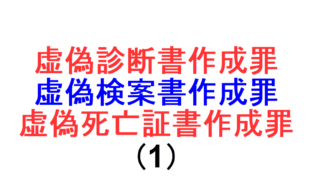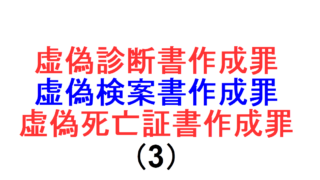虚偽診断書等作成罪(2)~「主体(犯人)」「『医師』とは?」「『医師』に『歯科医師』が含まれるか?」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、虚偽診断書作成罪、虚偽検案書作成罪、虚偽死亡証書作成罪(刑法160条)を適宜「本罪」といって説明します。
主体(犯人)
本罪の主体は、医師に限られます。
しかも、医師のうち「医師法等の定める有資格の医師であって、私人として医療を行う者」に限られます。
本罪は、医師が犯人であることを犯罪の成立要件とする真正身分犯です。
※ 真正身分犯は、構成要件において行為者が一定の身分をもたなければ犯罪を構成しないものをいいます。
※ 不真正身分犯は、構成要件において行為者が一定の身分をもつことで法定刑が加重あるいは減軽されるものをいいます。
「医師」とは?
「医師」とは、
医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者
をいいます(医師法2条)。
公務員である医師(例えば、国公立の病院に動務する公務員である医師)が本罪に該当する行為を実行した場合には、虚偽公文書作成罪(刑法156条)が成立します。
これは、医師が公務員である場合は、客体である公務所に提出すべき診断書・検案書・死亡証書は公的色彩が強く、内容の真実性を担保する公共的要請が高いためです。
したがって、本罪の成立は、
医師法等の定める有資格の医師であって、私人として医療を行う者
に限られます。
この点、参考となる判例として以下のものがあります。
被告人がAと共謀して刑務所医務課長Cを買収してDのため同人が勾留に堪えられない旨の虚偽の内容の診断書を作成させてこれを入手しようと決め、Aがその任に当たることになったところAは医務課長の買収が困難なのを知って医務課長名義の診断書を偽造しようと決意し、Bを教唆して本件診断書を作成偽造せしめたという事案です。
この判決は、「被告人の故意は、Aと共謀して医務課長をして虚偽の公文書を作成する罪(刑法156条の罪)を犯させることを教唆することであるが、現実には公文書偽造の結果となったという事実の錯誤の問題である」としており、公務員である医師が診断書に虚偽の記載をした場合につき虚偽公文書作成罪が成立することを前提とした判断をしている点が注目すべき点となっています。
「医師」に「歯科医師」が含まれるか?
歯科医師が本罪にいう「医師」に含まれるか否かについては議論が分かれているところ、これを肯定するのが通説とされています。
肯定説が妥当とされる理由として、
- 医師について、医師法19条2項が「診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会った医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があった場合には、正当の事由がなければこれを拒んではならない」と規定し、歯科医師についても、歯科医師法19条2項において、医師と同様に、「診療をなした歯科医師は、診断書の交付の求があつた場合は、正当な事由がなければこれを拒んではならない」と規定しており、自ら診察等をして診断書を作成した医師と診療をして診断書を作成した歯科医師とを別異に取り扱う必要はないものと考えられること
- 口腔外科疾患については口腔がんの治療等の重要疾患が含まれ、その治療は歯科医師ないしは医師が行っていること
- 公益社団法人日本口腔外科学会の専門医制度規則や厚生労働省大臣官房統計情報部医政局作成の「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」において、歯科医師と医師とが同列に扱われていること
が挙げられています。
これに対し、否定説の理由として、
- 本罪と同様の規定振りである秘密漏示罪(刑法134条1項)において「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者」とあり、そこには「医師」のみが掲げられ、歯科医師は掲げられていないこと
- 歯科医師は法律の用語例としては医師に含まれないのが普通であること
が挙げられています。