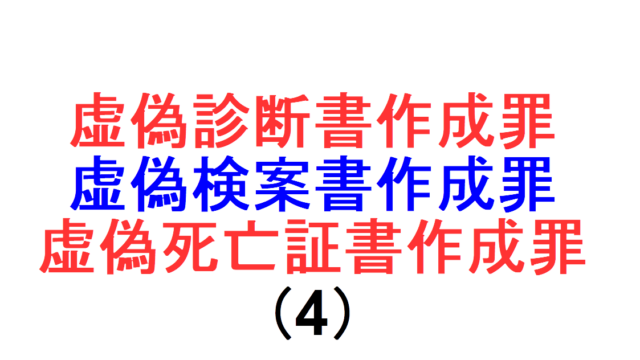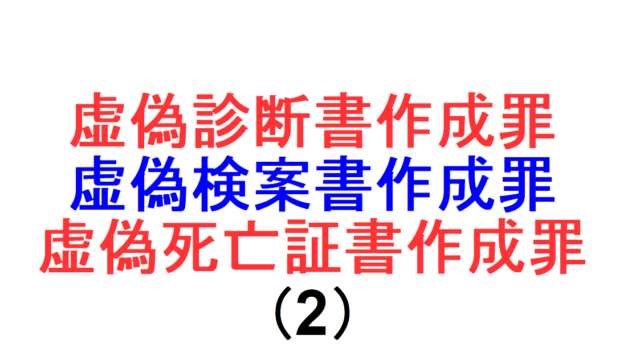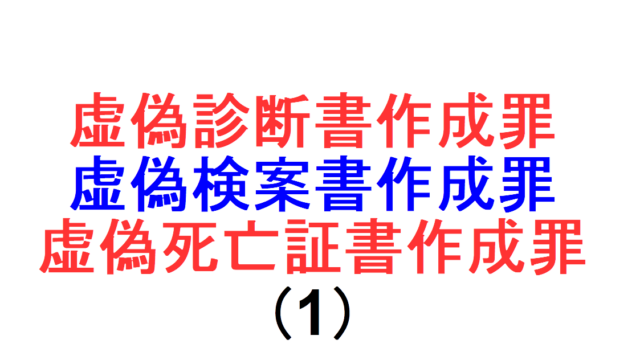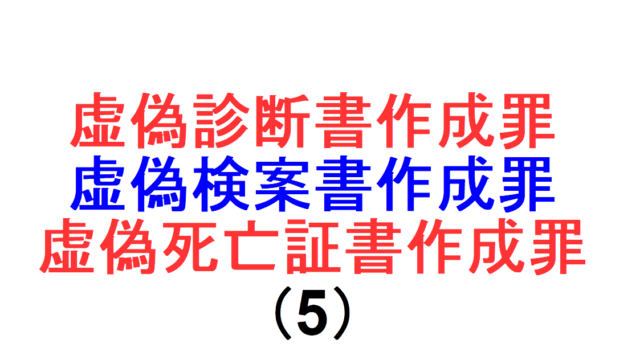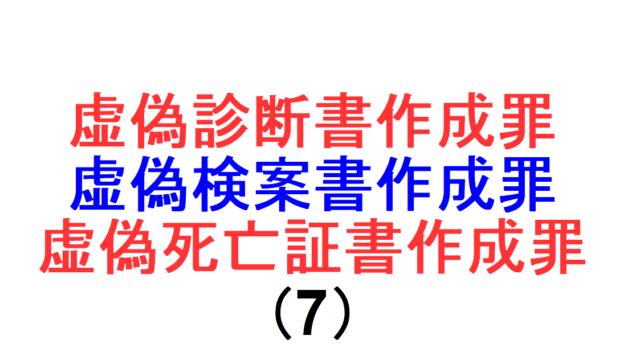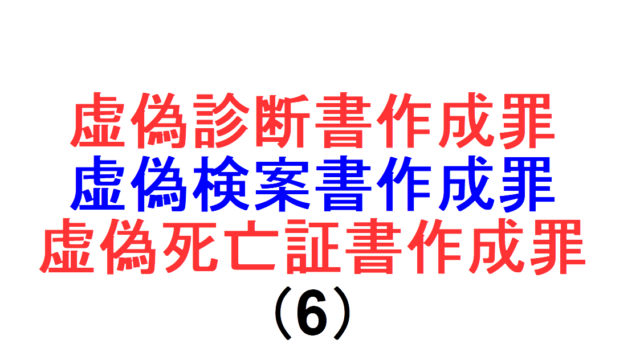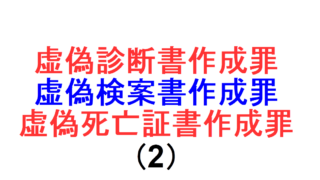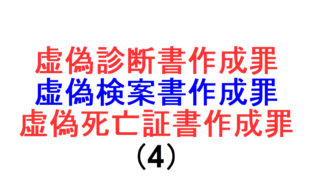虚偽診断書等作成罪(3)~「客体(『公務所』『公務員』『提出すべき』『診断書』『検案書』『死亡証書』とは?)」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、虚偽診断書作成罪、虚偽検案書作成罪、虚偽死亡証書作成罪(刑法160条)を適宜「本罪」といって説明します。
本罪の客体
本罪は、刑法160条において、
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する
と規定されます。
本罪の客体は、条文に記載されるとおり、
公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書
です。
以下で定義について詳しく説明します。
「公務所」「公務員」とは?
「公務所」とは、
官公庁その他公務員が職務を行う所
をいいます(刑法7条2項)。
「公務員」とは、
国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員
をいいます(刑法7条1項)。
「提出すべき」とは?
「提出すべき」とは、
- 法令の規定によって、公務所に提出することを義務付けられているもの
及び
- 公務所に提出することが予定されているもの
と解されています。
医師自ら提出する場合であると、他の者によって提出される場合であるとを問いません。
この点を判示した以下の判例・裁判例があります。
大審院判決(大正5年6月26日)
裁判所は、
と判示しました。
東京高裁判決(昭和27年11月27日)
刑法161条の虚偽診断書等行使罪に関する裁判例ですが、考え方は本罪にも当てはまります。
裁判所は、
- 公務所に提出すべき医師の診断書が虚偽の記載内容を有している限り、そのことを認識して当該公務所にこれを提出行使した以上、その行使者が、人を介してこれを行いたると、はたまた、該診断書の法定の提出義務者であると否とを問わず刑法第161条第1項所定の虚偽私文書行使の罪の成立するを妨げない
としました。
「診断書」とは?
1⃣ 「診断書」とは、
医師が診察の結果に関する判断を表示して人の健康上の状態を証明するために作成する文書
をいいます。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(大正6年3月14日)
裁判所は、
- 刑法第160条にいわゆる医師の診断書とは、医師が診察の結果に関する判断を表示して人の健康上の状態を証明するために作成する文書を指称するものにして、伝染病防止法第3条の規定により医師が伝染病患者を診断したることある旨の届出をなすために作成する届書の如きものを包含せざるものとす
と判示しました。
大阪地裁判決(昭和48年3月23日)
この判決は、
- 入院手続をとって部屋の使用を開始した後1週間後に入院したのに、診断書に入院手続をとった日を入院日と記載した場合には虚偽診断書作成罪が成立しない
- 患者が無断で外出、外泊し病院にほとんどおらず、診療も治療も受けていないのに診断書に「入院加療中」と記載した場合には虚偽診断書作成罪が成立しない
とした判決です。
裁判所は、
- 刑法160条の「診断書」とは、医師が診察の結果に関する判断を表示して人の健康状態を証明するために作成する文書である
- そこでまず、入院に関する記載が虚偽診断書作成罪の対象事項であるか否かについて考えるに、診断書は、通常、医師が診察の結果知りえた疾病、創傷、健康状態などにつき、その病名、症状、創傷の部位程度、健康状態の良否に関する認識と断が記載されるが、それは必ずしも医師の専門的知識と経験にもとづいて診察した事項に限られるものではない
- 入院の有無は、加療の必要性とその程度を推測させる事情であり、その限りにおいて傷病の重さをある程度示す事項である
- もちろん人それぞれの事情によって、重篤な病人が入院しないで自宅療養している場合もあれば、たいした病気でもないのに入院治療している場合もあるから、入院の有無はあくまで「ある程度」参考になる事実にすぎないものではある
- 同様に、入院の時期についても、例えば最近入院したのか、それとも数か月あるいは数年前から入院しているのか等を想定すれば、入院時期が傷病の状況に一定の説明を与えるものであることが理解できる
- このように入院に関する事実は、それが記載されれば、やはり傷病ないし健康状態を、間接的ではあるがある程度説明するものとして(医師もそのつもりで診断書に入院の事実を記載しているはずである)本罪の対象たる事項と解すべきである
- それでは、公訴事実第一の診断書に「ひき続き昭和40年2月2日本院入院」とある記載は虚偽と認めるべきであろうか
- 診断書に記載される入院に関する事項のもつ意義を、前記のように理解すれば、記載されるべき入院の始期は現実に入院した時点でなければならないであろう
- ところが本件のように入院手続をとり、病室に荷物まで入れて病室の使用を開始しておきながら(単なる入院の予約ではない)、現実に診療を受けはじめたのがその約1週間後であった場合は事柄は簡単ではなるものではないし、また医師が患者に対して入院費を請求し、あるいは保険関係機関に診療報酬を請求するときの入院の始期は当然入院手続をとった2月2日ということになるが、同じ医師の業務としてこれらの取扱いとの整合性を全く無視することも相当ではない
- そして前述したような、入院に関する記載の症状を説明する記述としての間接的、参考事項的性格をもあわせ考えると、これも程度問題ではあるが、形式的に入院手続をとり、ひと月もふた月も入院時期を遅らせたような場合とは異なり、入院手続をとった日に現実に病室に荷物をもちこんで部屋の使用を開始し、約1週間後には入院している本件のような場合には、入院手続をとった時点を入院日と記載したからといって、これを虚偽の記載であるとまでいうことはできない
- つぎに、公訴事実第ニの診断書に、昭和40年2月27日の時点で「入院加療中」と記載することが、虚偽であるかどうかについて考えるに、なるほど当時Aは病院にほとんどおらず、従って診療も治療を受けていなかったのであるが、無断外出、外泊中であっても入院中であることにはかわりはないし、患者としてはいつでも入院している病院での診療を受けうる状態にあり、「入院加療中」とはこのような状態をも含めて用いられる言葉である
- したがって、現実に診療行為をしていない時期であっても、それが外出外泊等による一時的なものと考えうる以上(そしてこの時点では、まだAが病院に戻る意思がないことは明らかになっていない)入院中でさえあれば、「入院加療中」と記載したからといって、これを虚偽の事実記載ということは相当でない
と判示しました。
2⃣ 「診断書」に関する条文として、刑訴規則179条の4において、病気を理由とする公判期日延期申立ての添付資料として「診断書」が挙げられています。
3⃣ また、最高裁判決(昭和30年12月2日)は、
- 公職選挙法49条3号、同法施行令52条1項3号に基いて作成される選挙人に対する医師の証明書は、その内容が医師の診察の結果に関する判断を表示して人の健康上の状態を証明する部分を包含する限り医師法20条にいわゆる「診断書」と解すべきである
とします。
「検案書」とは?
「検案書」とは、
死後初めて死体に接した医師が死亡の事実を医学的に確認した結果を記載したもの
です。
「死亡証書」とは?
「死亡証書」とは、
生前から診断にあたっていた医師が患者の死亡時に作成する診断書
です。
死亡証書は、医師法20条の死亡診断書と同じものです。