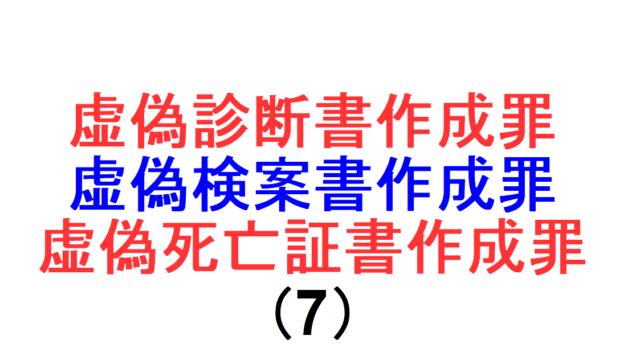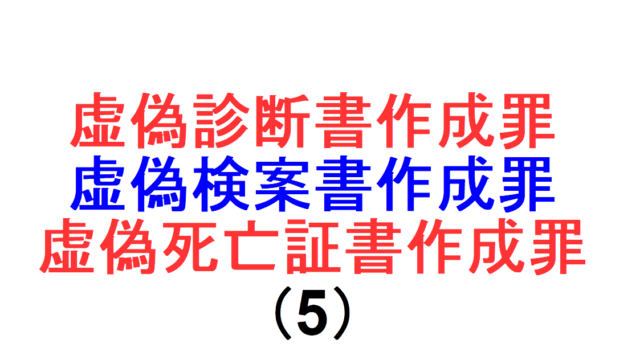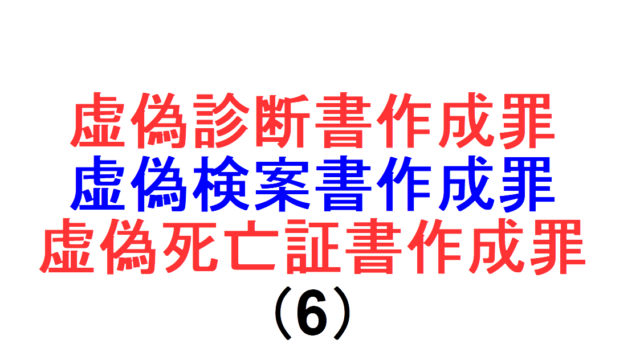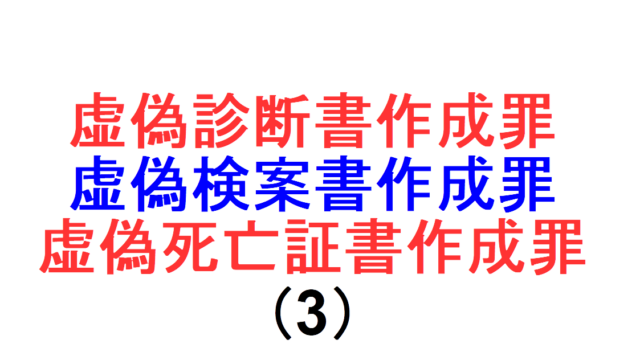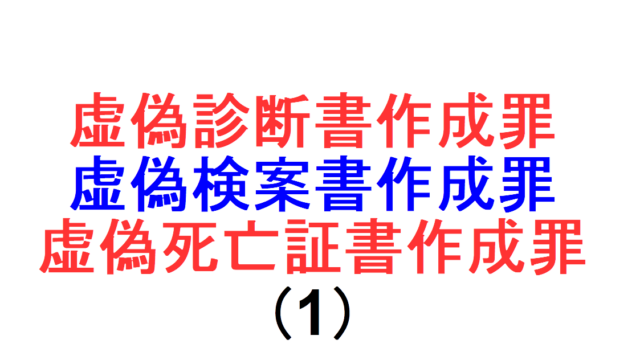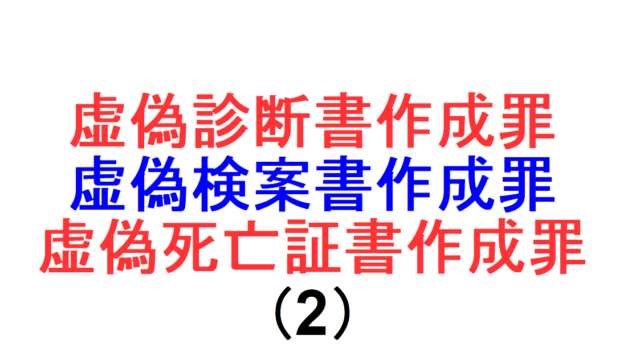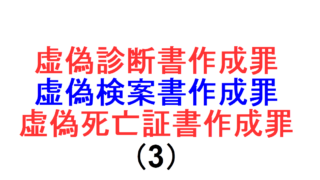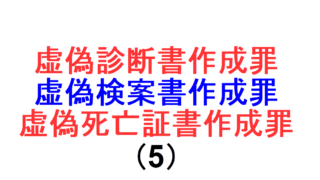虚偽診断書等作成罪(4)~「本罪の行為」「既遂時期」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、虚偽診断書作成罪、虚偽検案書作成罪、虚偽死亡証書作成罪(刑法160条)を適宜「本罪」といって説明します。
本罪の行為
本罪は、刑法160条において、
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する
と規定されます。
本罪の行為は、
医師が虚偽の記載をすること
です。
「虚偽の記載」とは、
客観的事実に反する一切の記載(病状、死因、死亡日時等)
をいいます。
客観的事実に関するものであるか、判断に関するものであるかを問いません。
自己の認識又は判断に反する証明文書の作成だけが処罰の対象となります。
医師が診断書の記載が実質上真実に適合するにもかかわらず、虚偽と誤信した場合には、客観的に真実に反するわけではないので、本罪を構成しません。
本罪を構成しない根拠は、公務所の判断を誤らせるおそれがないためとされます。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(大正5年6月26日)
裁判所は、
- 刑法第160条は公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡診断書に医師が虚偽の記載をなしたる行為を処罰する規定にして、その虚偽の記載には事実に関するものに限らず、判断に関するものを包含す
- 故に、医師がその作成する診断書の公務所に提出するものなることを了知しながら、人の健康状態に関する診断の結果につき、これに不実の記載をなしたる行為は、刑法第160条の犯罪を構成するものとす
- 刑法第160条の処罰規定は、虚偽の証明を禁止するの趣旨に出たるものなれば、いわゆる虚偽の記載たるには、その診断書等の記載が実質上、真実に違背することを要す
- 従って、その記載が実質上、真実に適合するにかかわらず、単にこれを作成する医師において不実と誤信したる場合の如きは、犯罪を構成せざるものとす
と判示しました。
裁判例
診断書等が虚偽の記載とされ、本罪が成立するとした裁判例として、以下のものがあります。
- 安静加療然るべしでないと認識しながらそのように判断した旨を診断書に記載をした事案(大審院判決 大正5年6月26日)
- 樹上から墜落死亡した者について、故意にその原因を記載せず、単に脳溢血により死亡した旨を死亡証書に記載した事案(大審院判決 大正12年2月24日)
- 死亡診断書作成の際、死亡日時が昭和12年9月4日午後3時30分と知悉しながら、死亡日時を同月3日午後3時30分と記載した事案(大審院判決 昭和13年6月18日)
- 国有林内において死亡したものであることを知悉しながら、ことさらに死亡の場所を「〇〇病院」と死亡診断書に記載した事案(東京地裁八王子支部 昭和44年3月27日)
- 障害年金を受給しようとする者らの聴覚障害の程度が障害年金の支給を受けられるような聴力レベルでないのに、障害年金の支給を受けられるレベルに該当する旨の内容虚偽の診断書を作成した事案(札幌地裁判決 平成22年1月20日、札幌地裁判決 平成23年9月22日、札幌地裁判決 平成24年3月19日)
虚偽記載とはいえないとされた事例として、以下の裁判例があります。
大阪地裁判決(昭和48年3月23日)
入院手続をとって部屋の使用を開始した後、1週間後に入院したのに、診断書に入院手続をとった日を入院日と記載したこと、患者が無断で外出、外泊し病院にほとんどおらず診療も治療も受けていないのに診断書に「入院加療中」と記載したことにつき、虚偽の記載といえないとしました。
既遂時期
本罪は、
虚偽診断書等が作成されること
により既遂に達します(「既遂」の説明は前の記事参照)。
作成された診断書等が公務所に提出されたか否かは本罪の成否とは無関係です。