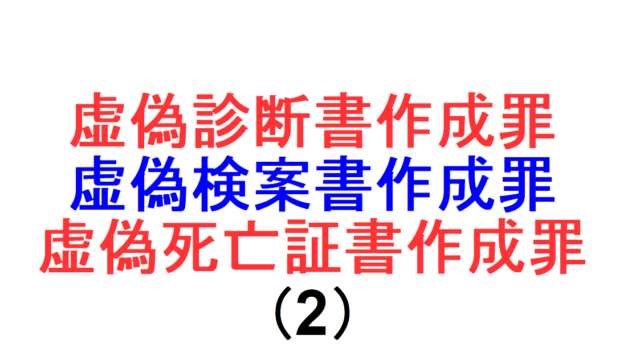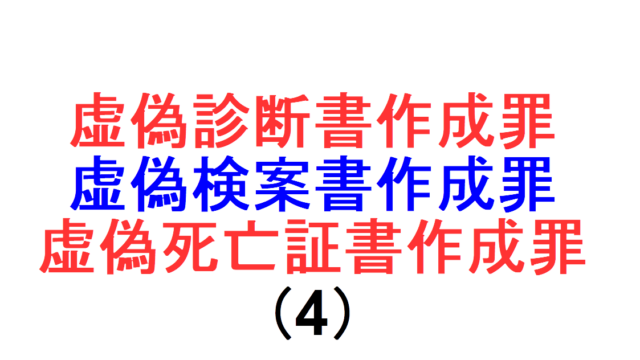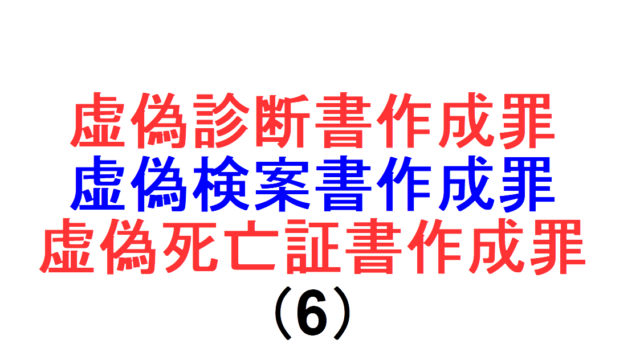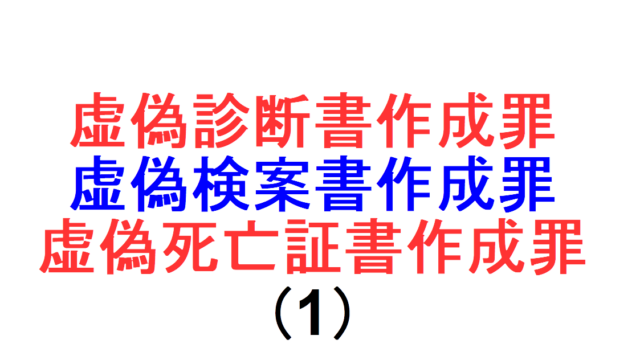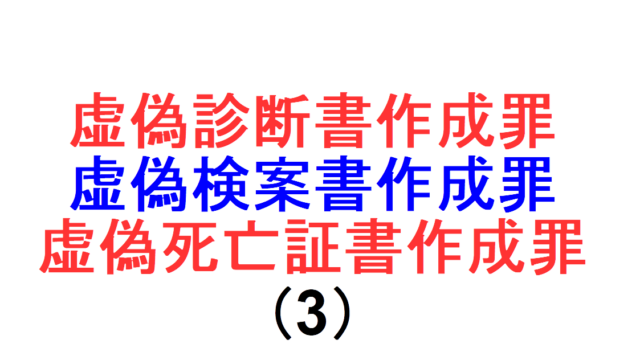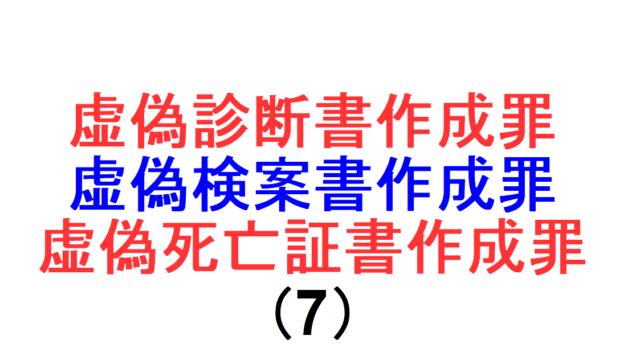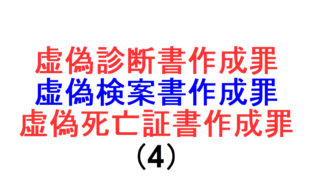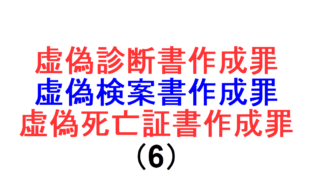虚偽診断書等作成罪(5)~「本罪の間接正犯は成立しない」「本罪の成立には、行使の目的(虚偽診断書等を公務所へ提出する目的)」を要する」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、虚偽診断書作成罪、虚偽検案書作成罪、虚偽死亡証書作成罪(刑法160条)を適宜「本罪」といって説明します。
本罪の間接正犯は成立しない
間接正犯による本罪の成立が認められるかについて説明します。
「間接正犯」は、
他人を道具として利用し、他人に犯罪行為をやらせ、犯罪を実現する者
いいます(間接正犯の説明は前の記事参照)。
替え玉を使って、情を知らない医師に虚偽の診断書を作成させる行為は、本罪の間接正犯として処罰し得るようにも見えます。
しかし、公文書について私人による虚偽公文書作成罪の間接正犯は成立しない場合あることの対比から(詳しくは前の記事参照)、本罪についても処罰されないと解されています。
本罪の成立には、「行使の目的(虚偽診断書等を公務所へ提出する目的)」を要する
行使の目的の要否について、「虚偽診断書等の公務所への提出」という「行使の目的」が
- 必要であるとする説(行使の目的必要説)
- 不要であるとする説(行使の目的不要説)
とがあります。
結論は、行使の目的必要説が相当とされます。
行使の目的必要説は、「公務所に提出すべき」という文言を理由に、本罪を目的犯と解することを理由とします。
「公務所に提出すべき」という文言の中には、「公務所への提出」という「行使の目的」が含まれていると解するのが相当であって、そのため「行使の目的」が成立要件として規定されていないといえるとされます。
したがって、公文書偽造罪(刑法155条)とは構造的な違いがあり、行使の目的必要説が相当とされます。
これに対し、行使の目的不要説は、公文書偽造罪(刑法155条)の「作成すべき文書」という文言との対比で、「提出すべき」ということが当然に目的を表現する意味にもとれず、提出すべき文書の認識があれば足りるとすることを理由とします。