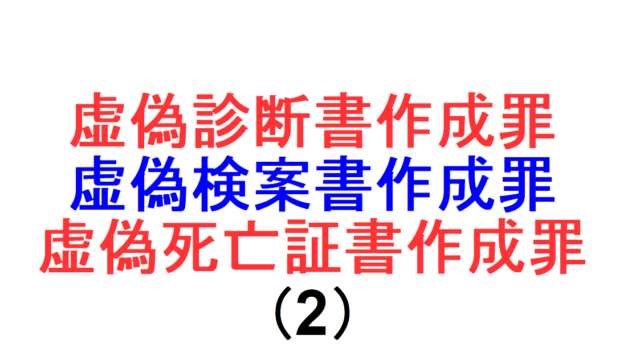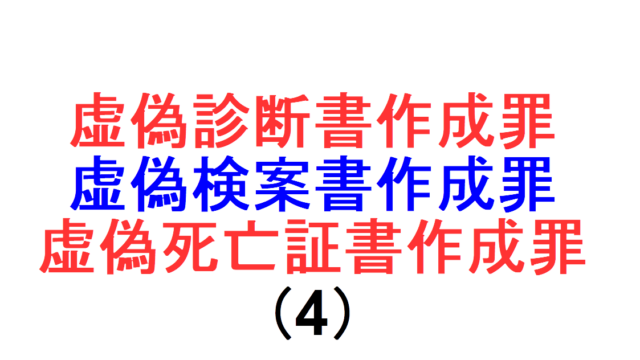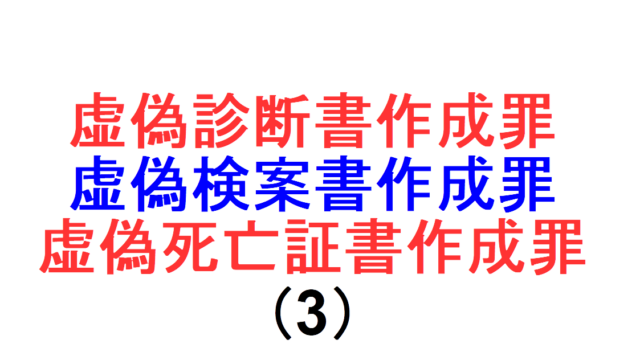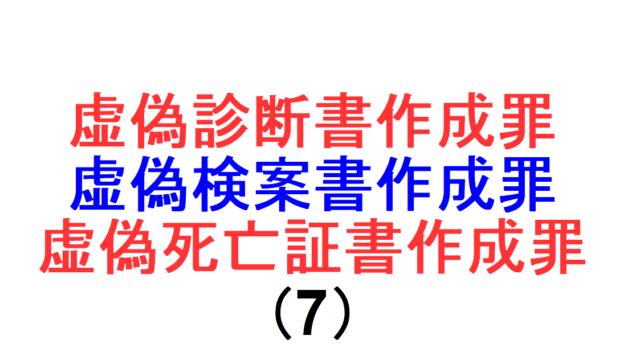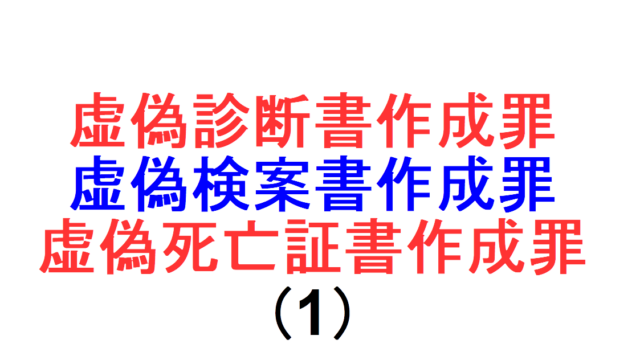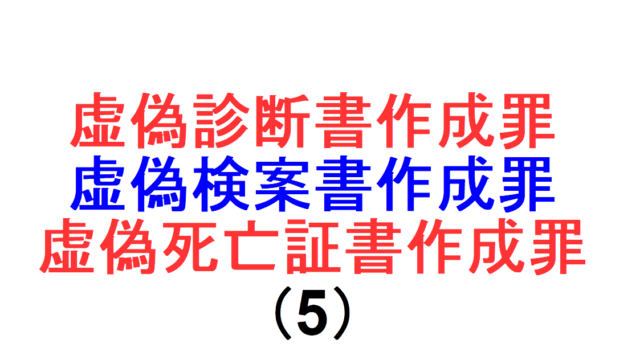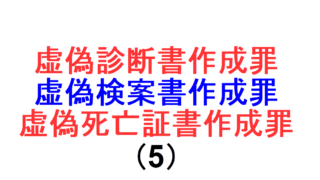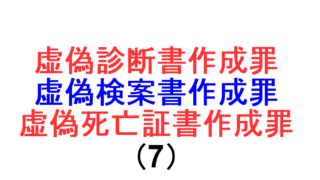虚偽診断書等作成罪(6)~「本罪の故意」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、虚偽診断書作成罪、虚偽検案書作成罪、虚偽死亡証書作成罪(刑法160条)を適宜「本罪」といって説明します。
本罪の故意
本罪は故意犯です(故意についての詳しい説明は前の記事参照)。
なので、本罪が成立するためには、本罪の主体(犯人)たる医師が、本罪を犯す故意を有していることが必要です。
本罪の故意が認められるためには、医師が、
その作成する診断書、検案書及び死亡証書が公務所に提出されるべきものであることを表象し、かつ、これに虚偽の記載をすることを認識・認容して本罪の行為すること
を要します。
参考となる以下の裁判例があります。
東京地裁判決(平成13年10月9日)
被告人に本罪の故意があったと認められないとして無罪を言い渡した事例です。
【事案】
被告人(医師)が死亡診断書を作成し、第三者を介してこれを提出して行使したこと、客観的にはBが階段から転落して負傷した事実はなく、Bが死亡したのは暴行を受けて負傷したためであること、したがって、被告人が死亡診断書の死亡の原因欄に「転倒、転落」、死因の種類欄に「外因死、不慮の外因死、転倒・転落」などと記載したのは、客観的には誤りであったことについて争いがなく、本件当時、被告人がBの死亡についてどのような認識を有していたのか、その認識内容からみて、実際に被告人が本件死亡診断書の死亡の原因欄等に記載した内容が、虚偽といえるのかどうかが争われた事案(虚偽診断書作成、同行使被告事件)です。
【判決】
裁判所は、
- 被告人において、Bが意図的に強度かつ多数回にわたる殴打等の暴行を加えられたと認識し、かつ、同人が階段からの転落等によって負傷したことはないと認識し、よって、Bが階段からの転落等によって負傷したために死亡したものではないと認識していたとは認め難い
などとして、合理的な疑いを入れない程度に検察官の立証が尽くされていないとして、被告人を無罪としました。