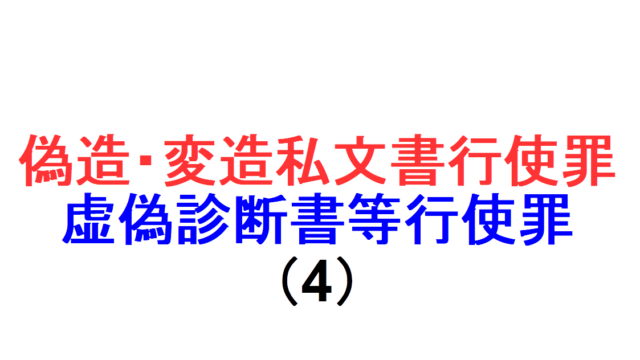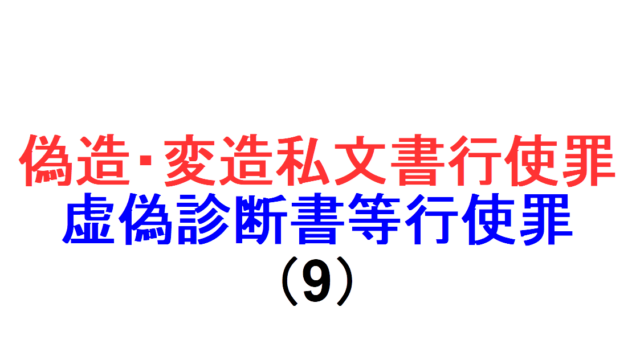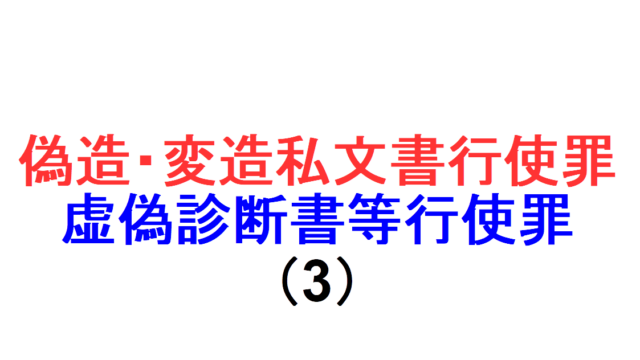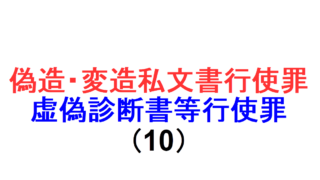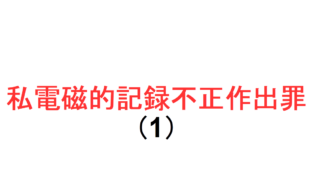偽造私文書等行使罪(11)~「変造私文書行使罪の判決において、変造行為自体の詳細を明示する必要はない」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、刑法161条の罪(偽造有印私文書行使罪、変造有印私文書行使罪、偽造無印私文書行使罪、変造無印私文書行使罪、虚偽診断書行使罪、虚偽検案書行使罪、虚偽死亡証書行使罪)を説明します。
変造私文書行使罪の判決において、変造行為自体の詳細を明示する必要はない
変造私文書行使罪の判決において、変造行為自体の詳細を明示する必要はありません。
変造私文書行使罪の判示として変造行為自体の詳細を明示することが必要かという点に関し、不要であると判示した以下の裁判例があります。
東京高裁判決(昭和30年5月31日)
裁判所は、
- 変造私文書行使の事実を認定するには、その私文書が変造されたものであり、被告人が変造文書であるという情を知りながら真正なものとしてこれを行使したことを認定判示すれば足りるのであって、それがいつ何人によって変造されたものであるか、また被告人以外の者が変造したとすれば、被告人がその変造者や変造の日時その他の具体的事実を知っていたかどうかというようなことまでも認定判示する必要はない
旨判示しました。
このことは、検察官が起訴する当たっても、起訴状に変造行為自体の詳細を明示する必要はないことも意味します。