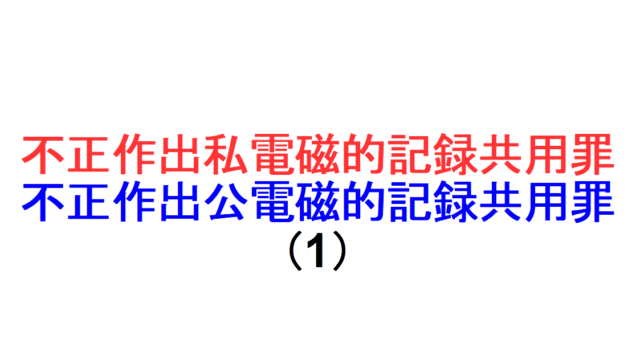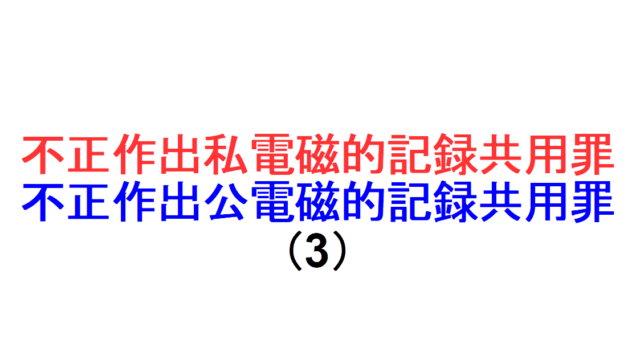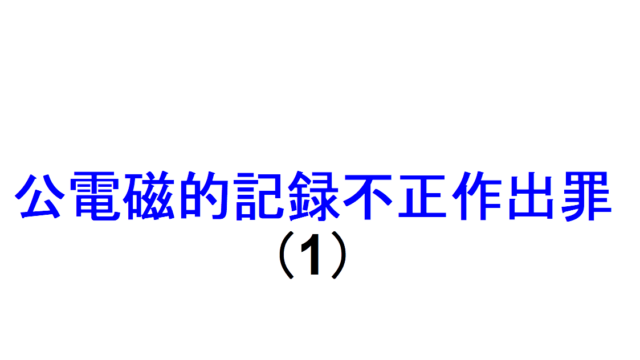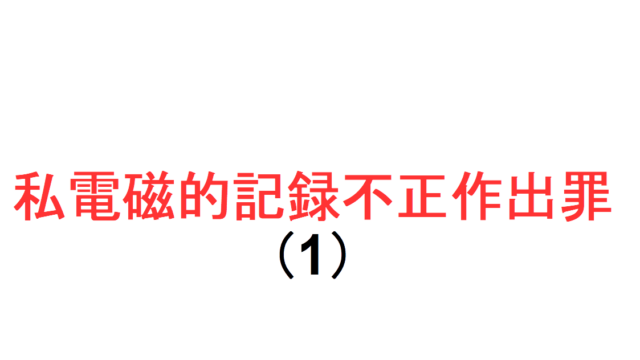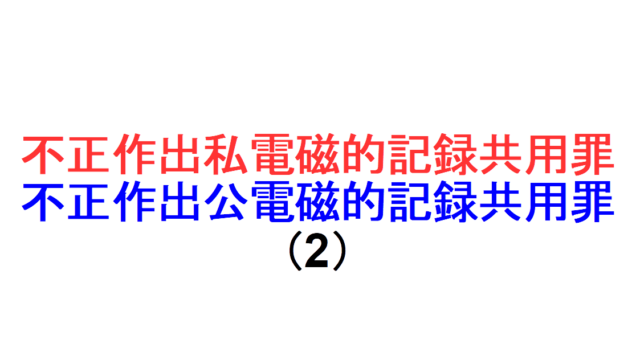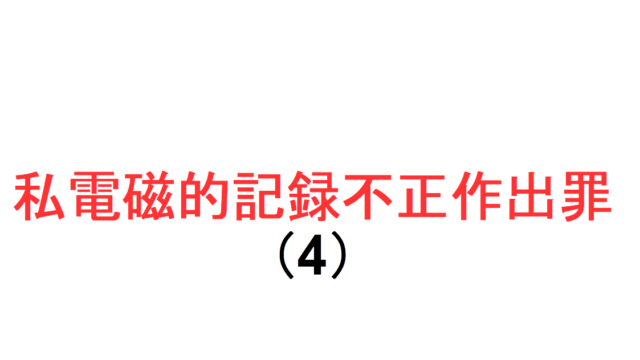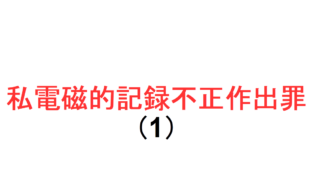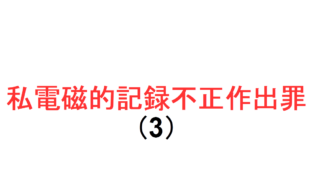私電磁的記録不正作出罪(2)~「本罪の客体」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、私電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2第1項)を適宜「本罪」といって説明します。
本罪の客体
私電磁的記録不正作出罪の客体は、
人の事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録
です。
不正作出に係る電磁的記録が公文書に対応する公電磁的記録(公務所又は公務員により作られるぺき電磁的記録)である場合は、公電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2第2項)により重く処罰されることになっているので、本罪の客体は、公電磁的記録以外の電磁的記録…つまり、
私電磁的記録
に限られます。
本罪の客体となる私電磁的記録は、私文書偽造の客体となる文書の場合と同様に、電磁的記録の証明機能を保護するという考えに基づき、
「権利、義務又は事実証明に関するもの」
に限られます。
本罪の客体については、さらにその中で
「人の事務処理の用に供するもの」
に限定されています。
これは、電磁的記録が文書と異なり、それ自体独立してその証明機能を発揮するのではなく、それを用いて一定の事務処理をすることが予定されているシステム及びプログラムのもとで用いられてはじめて本来の機能を発揮するものであることによります。
「権利、義務又は事実証明に関する」の意義
「権利、義務又は事実証明に関する」の意義は文書偽造・変造罪におけるそれと同意義です。
詳しい説明は、有印私文書偽造罪(3)~「本罪の客体である『権利、義務に関する文書』」を説明の記事で行っています。
「電磁的記録」の意義
「電磁的記録」の意義は、刑法7条の2
この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう
と定義されています。
具体例
「権利、義務に関する」電磁的記録には、
- オンライン化された銀行の元帳ファイルの記録
- 乗車券の磁気ストライプ部分
が該当します。
「事実証明に関する」電磁的記録には、
- 勝馬投票券の裏面の磁気ストライプ部分(甲府地裁判決 平成元年3月31日は、勝馬投票券の裏面の磁気記録は「勝馬投票券払い戻しのための事務処理の用に供する事実証明に関する電磁的記録」としている)
- パソコン通信のホストコンピュータ内の顧客データベースファイル(京都地裁判決 平成9年5月9日)
- いわゆるネットオークションの運営会社が管理するサーバーコンピュータ内の会員の情報に関する記録(大阪高裁判決 平成19年3月27日)
- 売掛金その他の会計帳簿ファイルの記録
などがあります。
なお、キャッシュカードの磁気ストライプ部分の記録について「事実証明に関する」電磁的記録に当たるとした裁判例(東京地裁判決 平成元年2月17日、東京地裁判決 平成元年2月22日)がありますが、キャッシュカードは支払用カードとして刑法163条の2(支払用カード電磁的記録不正作出罪、不正作出支払用カード電磁的記録共用罪、不正電磁的記録カード譲渡し等罪)の客体とされ、本罪の客体から除外されることとなっています。
通話可能度数が印字されたテレホンカードについても刑法163条の2の客体とされ、本罪の客体からは除外されることとなっています。
なお、プログラムを記録した電磁的記録については、電子計算機に対する指令の組み合わせを記録したものであり、それ自体は、「権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録」ではないと解されいます(学説)。