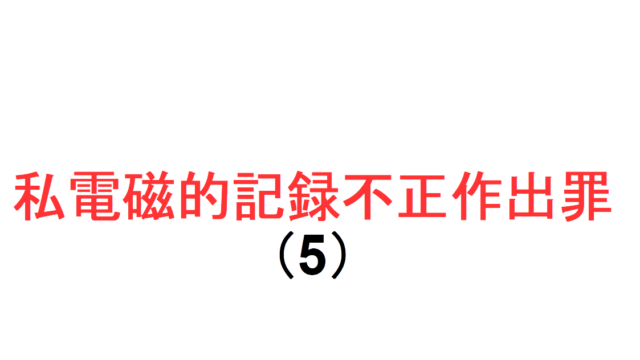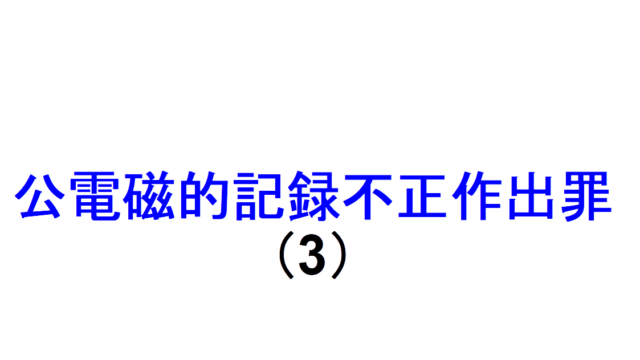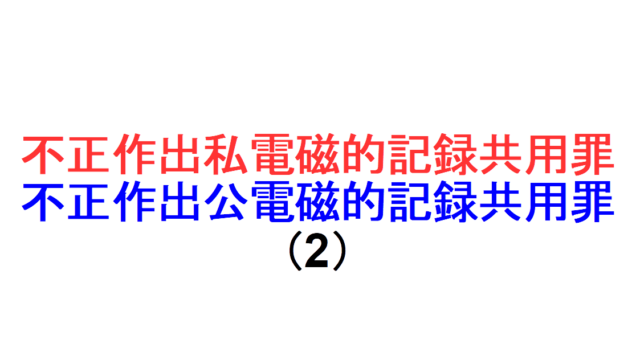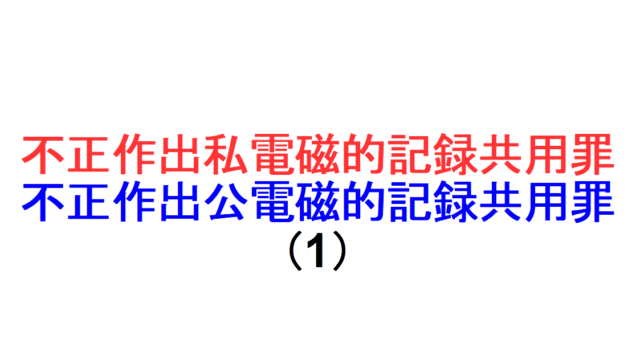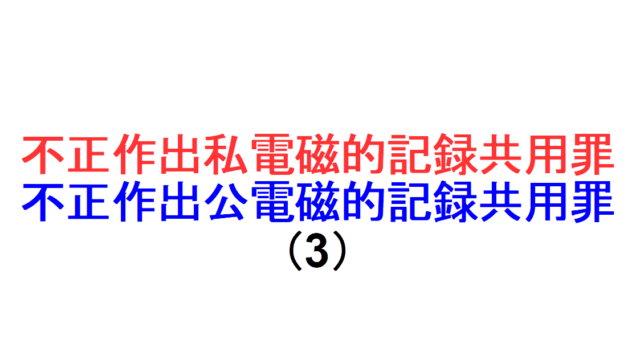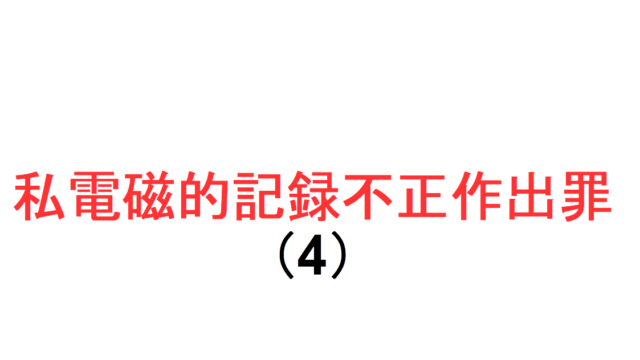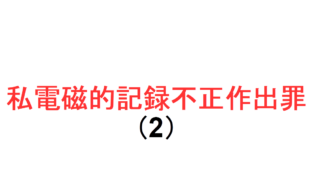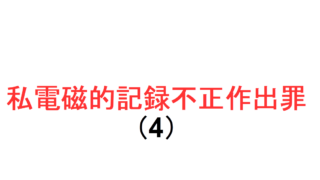私電磁的記録不正作出罪(3)~「『人の事務処理を誤らせる目的』とは?」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、私電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2第1項)を適宜「本罪」といって説明します。
「人の事務処理を誤らせる目的」とは?
私電磁的記録不正作出罪は、刑法161条の2第1項において、
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する
と規定されます。
本罪を含め、刑法161条の2の罪である
- 私電磁的記録不正作出罪(第1項)
- 公電磁的記録不正作出罪(第2項)
- 不正作出私電磁的記録共用罪、不正作出公電磁的記録共用罪(第3項)
は、いずれも目的犯です。
目的犯とは、犯罪の成立に所定の目的が必要とされる犯罪をいいます。
本罪を含め、刑法161条の2の罪の目的は、
「人の事務処理を誤らせる目的」
です。
「人の事務処理を誤らせる目的」とは、
不正に作られた電磁的記録を用いて他人の事務処理を誤らせる目的
をいいます。
ここにいう「事務処理」とは、
財産上、身分上その他の人の社会生活に影響を及ぼし得ると認められる事柄の処理
を意味し、業務として行われる事務か否か、法律的な事務か否か、財産上の事務か否か等を問いません。
例えば、
- 他人名義のキャッシュカードを入手するため、銀行がインターネット上に開設するホームページに接続して、ホームページ上のロ座開設申込フォームに虚偽の情報を入力して、銀行の事務センターのコンピュータに送信した場合には、銀行がコンピュータを介して行う口座開設の事務処理を誤らせる目的があるといえる
- 勤務先会社の取引先から頼まれてその買掛金債務を減らすため、同社の売掛金ファイル上の電磁的記録を勝手に改変した場合には、当該会社の売掛金管理事務の処理を誤らせる目的があるといえる
と考えられます。
これに対し、情報入手のため他人の電磁的記録のコピーを勝手に作るような行為は、それだけでは人の事務処理を誤らせる目的があるとはいえないと考えられます。
刑法161条の2の罪が「人の事務処理を誤らせる目的」を要するとされた理由
刑法161条の2の罪は、電磁的記録が文書に代わって権利、義務又は事実に関する証明手段として利用されるようになってきたことから、文書の場合と同様に、その公共的信用を保護するために設けられたものです。
なので、刑法161条の2の罪は、あらゆる不正作出、供用行為を処罰の対象とするのではなく、文書偽造罪の「行使の目的」と同様に何らかの限定が必要であると考えられて立法されました。
電磁的記録は、コンピュータの用に供されて人の事務処理に役立てられるものであるため、通常は対人行使の形態をとる文書偽変造罪における「行使」という表現は、電磁的記録の用い方を表す上で適切ではありません。
また、たとえ不正に作られたものであっても、記録内容が同一であるため原本又は正規に作られたコピーと同一の機能を果たす場合があり、これが一定のシステムで用いられても、その証明機能を害して人の事務処理に実害を及ぼさないこともあり得えます。
こうしたことから「行使の目的」による限定では処罰範囲を適正に画することができないと考えられ、刑法161条の2の罪については「人の事務処理を誤らせる目的」という実質的な違法目的がある場合に限定して犯罪の成立が成立するとされました。