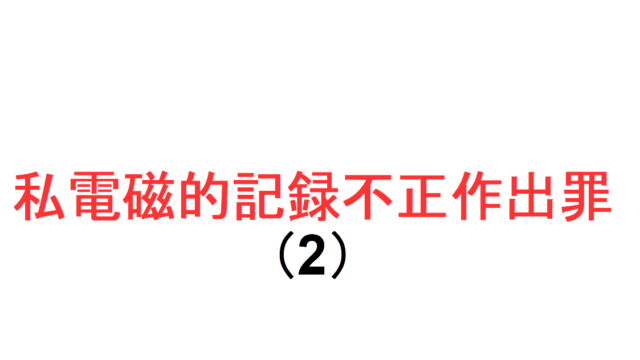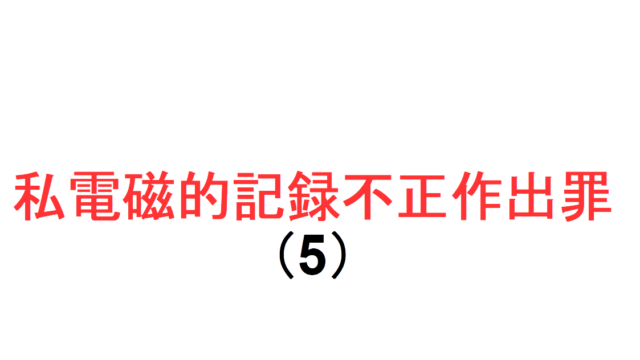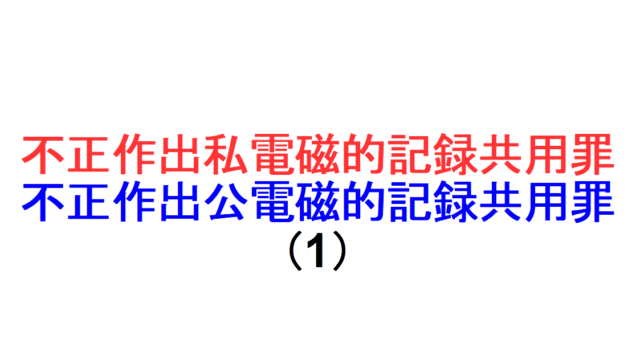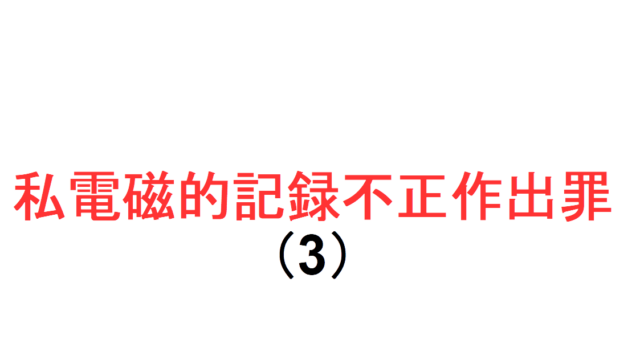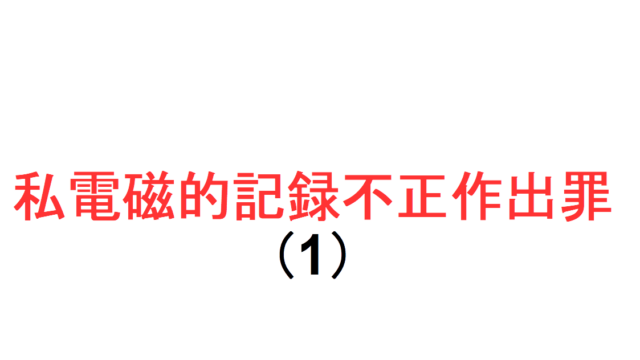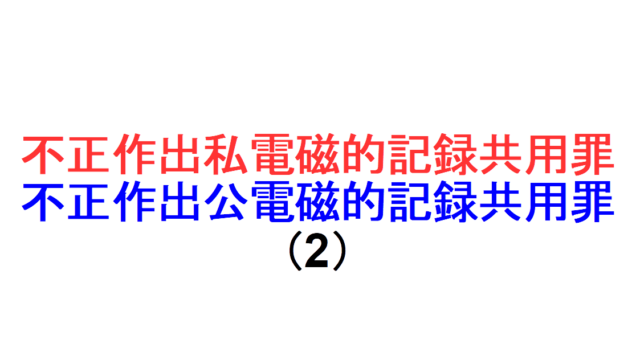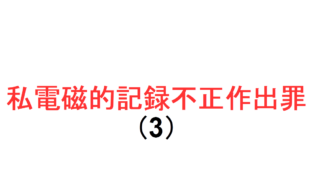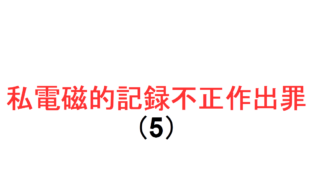私電磁的記録不正作出罪(4)~「『不正に作る(不正作出)』とは?」「記録の内容を自由に決定できる者が、内容虚偽の電磁的記録を作出することは処罰の対象外である」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、私電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2第1項)を適宜「本罪」といって説明します。
本罪の行為(私電磁的記録の不正作出)
私電磁的記録不正作出罪は、刑法161条の2第1項において、
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する
と規定されます。
本罪は、
私電磁的記録を不正に作る行為
を処罰の対象とするものです。
電磁的記録については、文書偽造罪における偽造・変造・虚偽作成とは異なり、
不正作出
が処罰の対象とされています。
「不正作出」が処罰されることとなった経緯
「文書」には、作成名義人(文書に表示される意思又は観念の帰属主体)が存在するため、その名義を偽る偽造、変造あるいは作成名義は偽らないが虚偽の内容を盛り込む虚偽作成という概念がふさわしいと考えられます。
これに対して「電磁的記録」には、可視性、可読性がないのみならず、例えば、銀行のオンラインシステムにおける預金元帳ファイルの残高更新の過程のように、入力したデータがプログラムにより既存のデータとともに処理、加工されて新たに作り出されることが少なくなく、その作出に複数の者の意思や行為がかかわることがあるなど、その作出過程に文書と異なる特質があります。
また、「電磁的記録」は「文書」のようにそれ自体で客観的・固定的な意味を有するものとして独立して社会的機能を発揮するものではなく、それを使用することが予定されている一定のシステム及びプログラムのもとで用いられてその予定された本来の証明機能を果たすものであるという点で、その利用過程にも「文書」と異なる特質があります。
他方、「電磁的記録」は一定のシステムに用いられて証明機能を果たすものであるから、それが作り出されるべきシステムにおいてはその設置運営主体の意思に基づいて正当に作り出されるものであることが当然の前提とされています。
以上のような「電磁的記録」の作出及び利用過程における特質にかんがみると、電磁的記録の公共的信用を保護するには、
- その作出過程に関わり合う者の関与のあり方において不正と評価される行為
すなわち
- 電磁的記録が作り出されるべきシステムの設置運営主体との関係において、記録の作出に関与する権限がないのに、あるいはそのような権限があってもこれを濫用し、その主体の意思に反して本来その者の与えられた権限の範囲では作ることが許されない記録を作出する行為
を処罰すべきことが妥当とされています。
そして、このようなとらえ方によって、公務員による公電磁的記録の虚偽作成のような、いわば公文書の虚偽作成に相当するような行為についても、結局システムの設置運営主体たる国、公共団体等が作ることを許さない記録を作るのであるから、全く権限のない非公務員による公電磁的記録の作成と同等の処罰価値が認められます。
こうした観点から、本罪においては、文書偽造罪とは異なり、「不正作出」が処罰されることとなったものです。
「不正に作る(不正作出)」とは?
本罪でいう「不正に作る」とは、
権限なく又は権限を濫用して電磁的記録を作ること
をいいます。
すなわち、
電磁的記録の作出過程に関与する行為者において、当該記録が作り出されるべきシステムの設置運営主体との関係で、記録の作出に関与する権限がないのに、あるいはそのような権限があってもこれを濫用して(当該記録の作出がその主体の意思に反し許されないという意味では実質的にその権限の範囲を逸脱しているということもできる)記録を作った場合
に「不正に」作出したこととなります。
電磁的記録を「作る」とは?
電磁的記録を「作る」とは、
記録媒体上に電磁的記録を存在するにいたらしめること
をいいます。
記録をはじめから作り出す場合のほか、既存の記録を部分的に改変、抹消することによって新たな電磁的記録を存在するにいたらしめる場合も含みます。
具体例
これまで、裁判例により不正作出に当たると認められた行為としては、以下のものがあります。
- 的中していない勝馬投票券の裏面の磁気ストライプ部分の電磁的記録を磁石で抹消した上、自分で制作した電磁的記録書込装置を用いて的中している勝馬投票券のそれと同一の内容のデータを書き込んで改ざんした行為(甲府地裁判決 平成元年3月31日)
- パソコン通信のサーバーの電子掲示板等に他人名義で商品売込みに関する虚偽の情報を書き込み、同情報を閲覧した者から商品代金名下に振込送金させた金員を詐取した者が、詐欺事犯の発覚を免れるため、パソコン通信のホストコンピュータ上に登録された他人の住所等の記録を無断で変更した行為(東京地裁判決 平成9年5月9日)
- インターネットオークションを運営する会社の管理するサーバーコンピュータに会員がパスワードを変更したという虚偽の情報を送信し、また、同会員がオークションに出品された商品に対して入札した事実がないのにこれを落札した旨の虚偽の情報をインターネットオークションを運営する会社のサーパーコンピュータに送信して、それぞれその旨の情報をサーバーコンピュータに記憶蔵置させた行為(大阪高裁判決 平成19年3月27日)
以上の行為は、いずれも、無権限者が、ほしいままに、データを入力するなどしてシステムの設置運営主体の意図しない電磁的記録を不正に作出したものです。
「不正作出」には、上記のとおり、権限を有する者が権限を濫用して電磁的記録を不正に作出する場合も含まれます。
すなわち、データの入力等の権限を有するものの、システムの設置運営主体との関係上、その補助者として真実のデータだけを入力等すべき義務を有する者が、その権限を濫用して虚偽のデータを入力等して内容虚偽の電磁的記録を不正に作出する類型の行為も本罪の対象となります。
その具体的な例としては、
- 給与事務の担当者が、その権限を濫用して、架空人に対する給与情報のデータを入力して、給与台帳ファイルにその旨の記録を作出する行為
- 証券会社の職員が、その権限を濫用して同社のオンラインシステムに虚偽の株式買付注文があった旨の情報を入力して、売買が成立した旨の電磁的記録を作出する行為
などが考えられます。
記録の内容を自由に決定できる者が、内容虚偽の電磁的記録を作出することは処罰の対象外である
不正作出罪はあくまで不正に電磁的記録を作出する行為を処罰するものであり、内容虚偽の電磁的記録を作出することを一般的に処罰の対象とするものではありまあせん。
したがって、本来記録の内容を自由に決定できる者の記録の作出にあっては、たとえその内容に虚偽があっても、記録の作出に関与する権限の点から見て、何ら不正に作ったものとはいえないため、本罪の対象とはなりません。
例えば、商店主が、脱税や水増し請求等の目的で取引状況を記録した磁気ファイルに虚偽の記録を作り出すことは本罪に当たりません。
なお、このような解釈に対しては「不正に」という文言によってこの結論が確保されているか疑問であり、会社役員と自営業者で可罰性を分けることには疑問があるとする説もあります。
しかし、本罪の「不正に」は上記のように権限なしに及び権限を濫用してと解されるので、権限がありかつ権限を濫用していない場合を本罪の対象とすることは文言解釈から無理があるといわざるを得えないとされます。