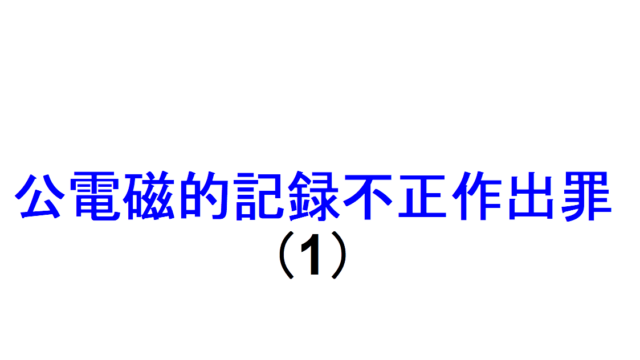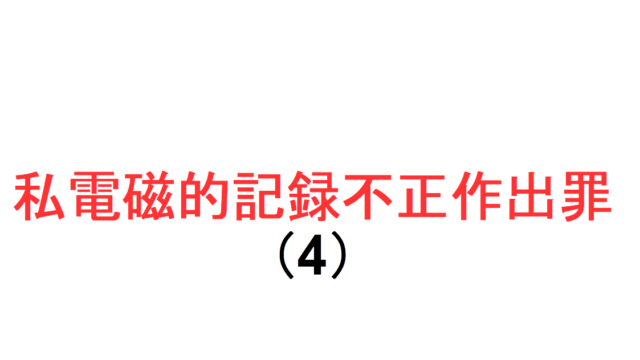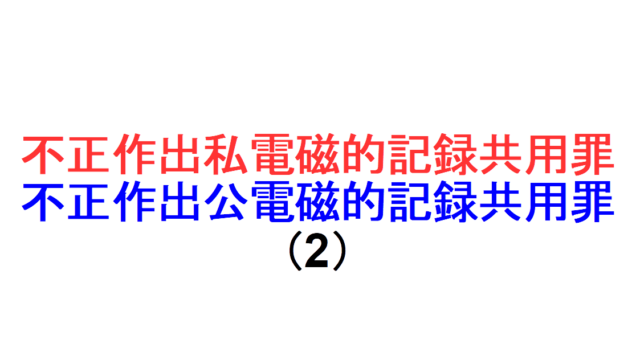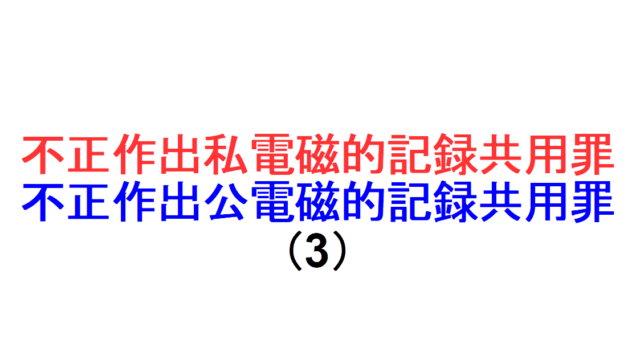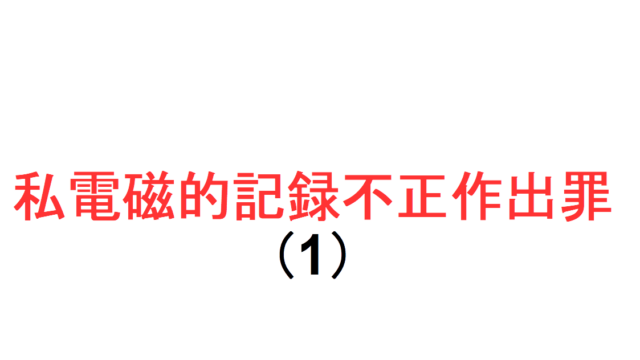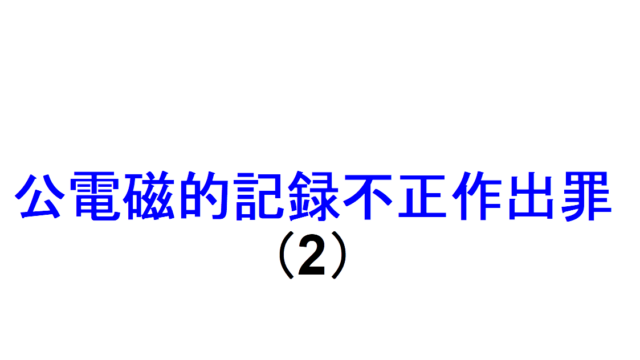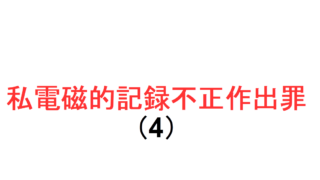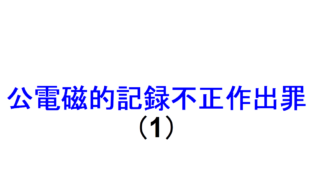私電磁的記録不正作出罪(5)~「『電磁的記録不正作出罪』と『不正作出電磁的記録共用罪』との関係」「①文書偽造罪、②電子計算機使用詐欺罪、③不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反、④電磁的記録毀棄罪との関係」を説明
前回の記事の続きです。
「電磁的記録不正作出罪」と「不正作出電磁的記録共用罪」との関係
電磁的記録を不正作出してこれを供用した場合における「電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2第1・2項)」と「不正作出電磁的記録共用罪(刑法161条の2第3項)」との関係は、手段と結果の関係にあるので牽連犯になります。
文書偽造罪との関係
電磁的記録を不正に作出した上、これをプリントアウトして文書を作成した場合には、通常、「電磁的記録不正作出罪」と「文書偽造罪(刑法18章)」が成立し、両者は併合罪の関係になります。
なお、電磁的記録を不正に作出した上、情を知らない文書の作成権限者をしてその内容をプリントアウトさせて文書を作成させたときの文書偽造罪の成否については間接正犯の態様による文書偽造、虚偽文書作成罪の問題となります。
電子計算機使用詐欺罪との関係
「電磁的記録不正作出罪・不正作出電磁的記録共用罪」と不実の電磁的記録の作出又は虚偽の電磁的記録の供用による不法利得を処罰の対象とする刑法246条の2所定の電子計算機使用詐欺罪とは、その保護法益、罪質及び処罰すべき行為のとらえ方、範囲を異にしており、文書偽造・同行使罪と詐欺罪との関係と同様、「電子計算機使用詐欺罪」が「電磁的記録不正作出罪・不正作出電磁的記録共用罪」の特別類型に当たるわけではありません。
したがって、これらの各罪が成立する場合の罪数関係は、手段と結果の関係になるので、原則として文書偽造、同行使罪と詐欺罪の罪数関係(牽連犯)と同様に、「電磁的記録不正作出罪・不正作出電磁的記録共用罪」と「電子計算機使用詐欺罪」は牽連犯になると考えられています。
もっとも、例えば銀行の元帳ファイルに不実の記録を作出して、これを供用すると同時に財産上不法の利益を得るような場合のように、客観的には一個の行為によってこれらの各罪が犯される場合も少なくなく、場合によっては「電磁的記録不正作出罪・不正作出電磁的記録共用罪」と「電子計算機使用詐欺罪」は観念的競合の関係になることもあり得えるとされます。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反との関係
不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条に違反してサーバーコンピュータに不正にアクセスすることを手段として、私電磁的記録を不正に作出した場合の不正アクセス罪と私電磁的記録不正作出罪の関係は、通常の形態として手段又は結果の関係になく、牽連犯とはなりません(最高裁決定 平成19年8月8日)。
両罪については併合罪となる場合が多いが、事実関係によっては観念的競合となることもあり得えるとされます。
電磁的記録毀棄罪との関係
電磁的記録の一部を消去するような行為については、文書の場合と同様、それが単に記録としての効用を毀損したにとどまれば公電磁的記録毀棄罪(刑法258条)又は私電磁的記録毀棄罪(刑法259条)に当たるが、新たな証明力を生じさせたと認められる場合には、電磁的記録不正作出罪に当たると考えられています。