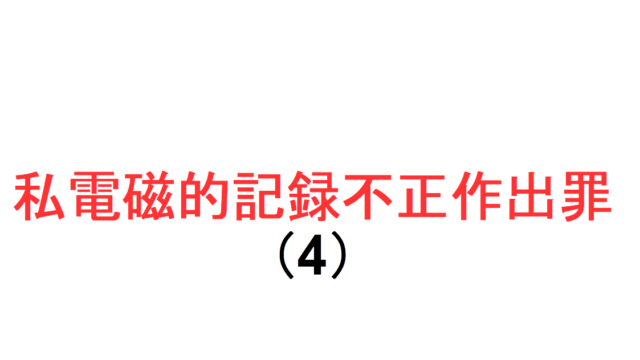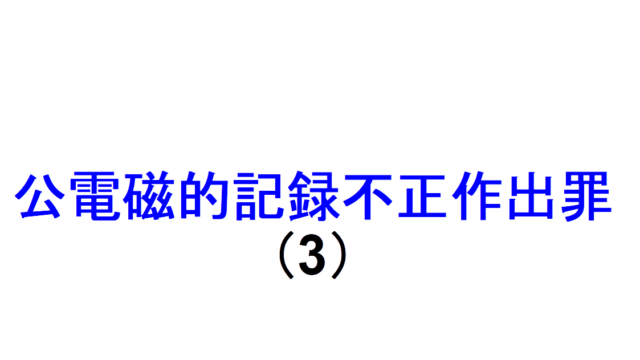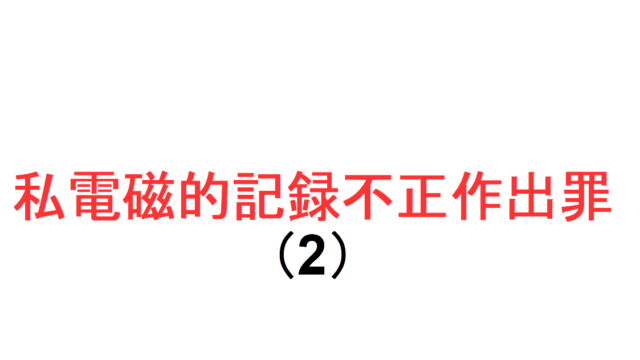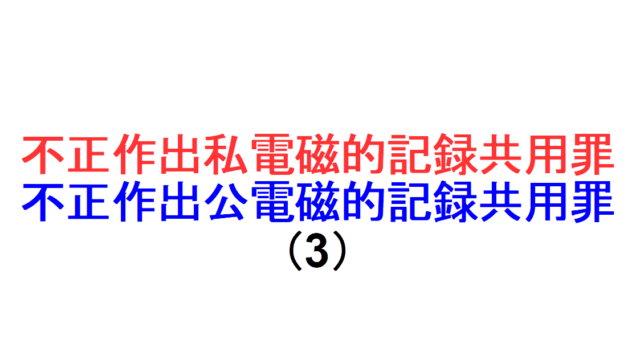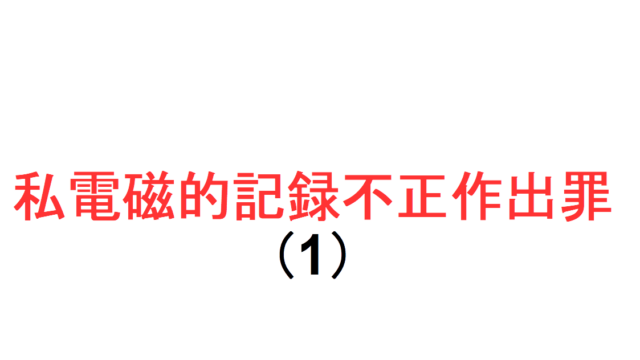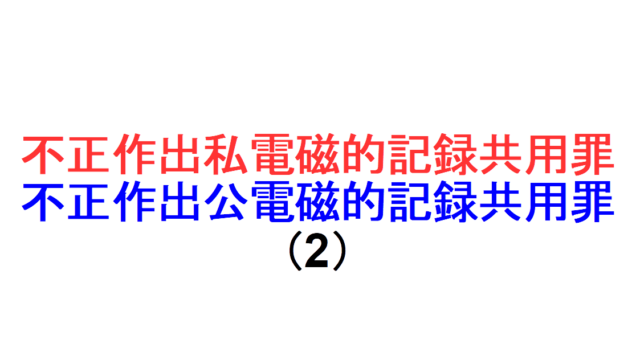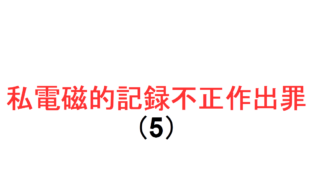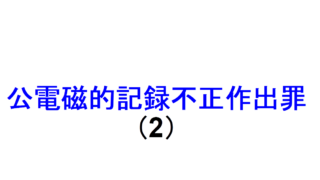公電磁的記録不正作出罪(1)~「公電磁的記録不正作出罪とは?」を説明
これから3回にわたり、公電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2第2項)を説明します。
公電磁的記録不正作出罪とは?
公電磁的記録不正作出罪は、刑法161条の2の第2項に規定があります。
刑法161条の2は、
第1項 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する
第2項 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する
第3項 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する
第4項 前項の罪の未遂は、罰する
と規定します。
公電磁的記録不正作出罪(第2項)は、公文書偽造罪(刑法155条)の電磁的記録バージョンを考えると分かりやすいです。
公電磁的記録不正作出罪は、
人の事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録のうち、公務所又は公務員により作られるべき公電磁的記録を不正に作る行為を、私電磁的記録の不正作出(第1項)より重く処罰するもの
です。
その理由は、公電磁的記録が私電磁的記録よりもその信用性が高く、社会的に重要な機能を果たしていることから、これを厚く保護する必要があるためです。
法定刑
公電磁的記録不正作出罪の法定刑については、公文書偽造罪(刑法155条)の法定刑との均衡から、自由刑は10年以下の拘禁刑となっています。
本罪の対象となる電磁的記録にはその重要性信用性の程度において多種多様なものがあることから、「100万円以下の罰金刑」が選択できることとなっています。
なお、「電磁的記録」は、「文書」と異なり、その作出に当たって印章、署名が用いられることが想定されません。
また、入力担当者を表示するために記録されるlD番号や電子印鑑が仮にこれに相当するとしても、その有無のみによって信用性の程度に類型的な差異が生ずるものとは考えられません。
したがって、文書偽造罪の場合のように有印、無印の別によって法定刑に差は設けられていません。
刑法161条の2の罪の説明
罪名
第1項は「私電磁的記録不正作出罪」を規定し、この罪は、私文書偽造罪(刑法159条)の電磁的記録バージョンを考えると分かりやすいです。
第2項は「公電磁的記録不正作出罪」を規定し、この罪は、公文書偽造罪(刑法155条)の電磁的記録バージョンを考えると分かりやすいです。
第3項は「不正作出私電磁的記録共用罪」「不正作出公電磁的記録共用罪」を規定し、この罪は、偽造私文書行使罪(刑法161条)、偽造公文書行使罪(刑法158条)の電磁的記録バージョンを考えると分かりやすいです。
刑法161条の2の立法趣旨
刑法161条の2は、コンピュータの普及による情報化社会の著しい進展に伴い、電磁的記録が、文書に代わり、社会的に重要な機能を果たしつつあることから、これにふさわしい刑法上の保護を与えるため、昭和62年の刑法改正によって新設されたものです。
電磁的記録が、広く文書に代わって社会的に機能するようになり、このような電磁的記録には、判例(大審院判決 明治43年9月30日など)が文書の要件の一つとしている可視性、可読性がないことから、従来の文書偽造・変造罪、偽造・変造文書行使罪の客体としての文書といえるかどうかの疑義がありました。
そこで電磁的記録を勝手に作り出したり、勝手に作り出した電磁的記録を事務処理の用に供するような、その当罰性等において文書偽造・変造罪、偽造・変造文書行使罪に匹敵する反社会的行為を処罰するために本条を新設し、電磁的記録にふさわしい刑法上の保護を図ることとしたものです。
なお、平成13年の法改正により、電磁的記録のうち支払用カード(クレジットカード、プリペイドカード、図書カードなど)を構成するものについては、刑法163条の2(支払用カード電磁的記録不正作出罪、不正作出支払用カード電磁的記録共用罪、不正電磁的記録カード譲渡し等罪)が新設され、本条の客体から除外されることとなりました。