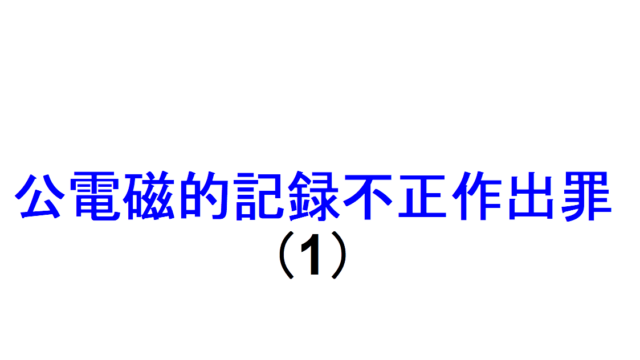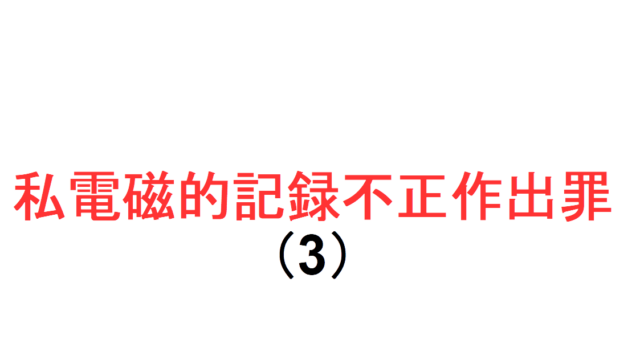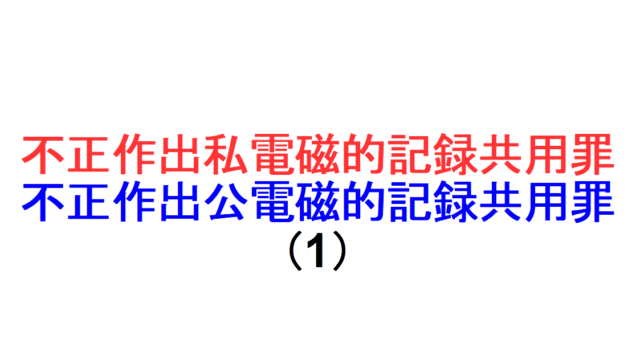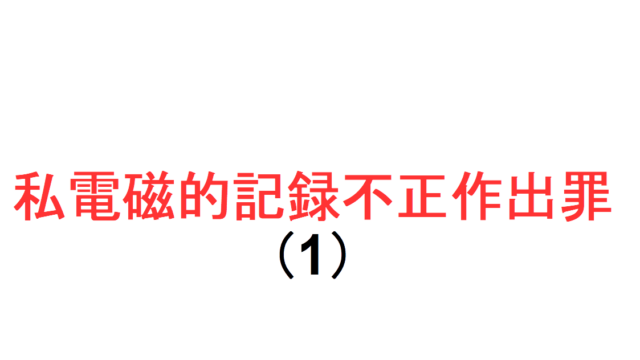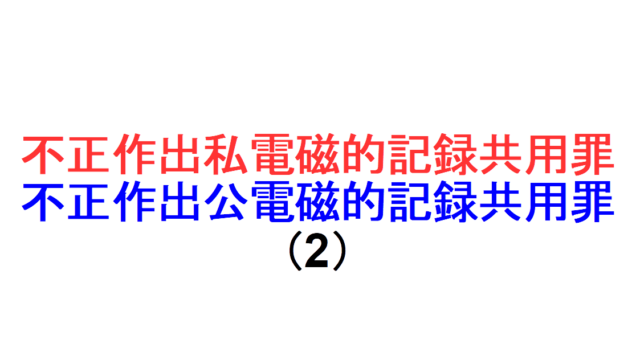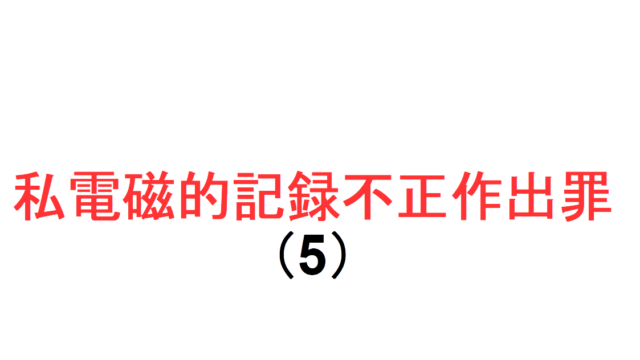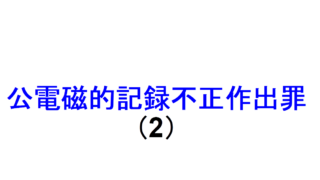公電磁的記録不正作出罪(3)~「本罪の行為」「罪数、他罪との関係」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、公電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2第2項)を適宜「本罪」といって説明します。
本罪の行為
公電磁的記録不正作出罪の行為は、
「人の事務処理を誤らせる目的」で公電磁的記録を「不正に作る」こと
です。
「人の事務処理を誤らせる目的」や「不正に作る」の意義は、私電磁的記録不正作出罪と同様です(詳しくは私電磁的記録不正作出罪(3)、私電磁的記録不正作出罪(4)の記事参照)。
公電磁的記録を不正に作る行為についても、私電磁的記録不正作出罪の場合と同様に、
- 無権限者による不正作出行為
- 権限濫用による不正作出行為
とががあります。
「無権限者による不正作出」の例として、
- 権異のない公務員が端末機を勝手に操作してデータを入力して不正に電磁的記録を作出する行為
- 公務所が外部からのデータの入力を受け入れて自動的に作ることとしている電磁的記録に、他人になりすまして勝手にデータの入力を行い、記録を作出する行為
が挙げられます。
「権限濫用による不正作出」の例として、
- データの入力等、記録の作出過程を部分的に分担している公務員が、システムの設置運営主体たる国等との関係でその補助者として真実のデータを入力すべき職責を有しているにもかかわらず、その職責に反して虚偽のデータを入力してそれに見合う記録を作出する行為
が挙げられます。
なお、「無権限者による不正作出」に当たるか、「権限濫用による不正作出」に当たるかについては、具体的な事件によっては微妙な場合もあり得えます。
例えば、戸籍事務に従事する市職員が、架空の人物になりすまして金融機関から金員をだまし取るため、同人物の戸籍をねつ造した上、住民基本台帳ファイルシステムの端末機を操作して磁気ディスクをもって調製される住民票に架空の人物に係る不実の転入記録を作り上げるなどした行為(仙台地裁判決 平成2年9月11日)については、一見すると権限濫用行為に当たると思われますが、当該職員に与えられていた具体的な権限によっては、無権限者による不正作出と評価できる場合もあるとされます。
もっとも、いずれにせよ不正作出に当たることとなるので、この点を厳密に分類する実益はあまりないといえるとされます。
罪数、他罪との関係
罪数、他罪との関係は、
で説明しています。