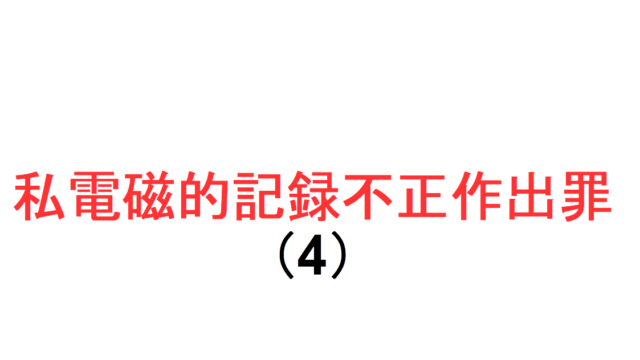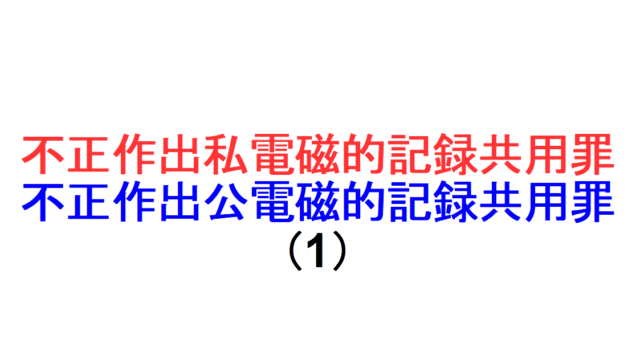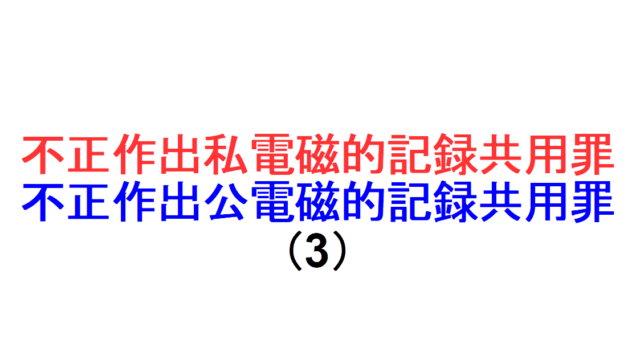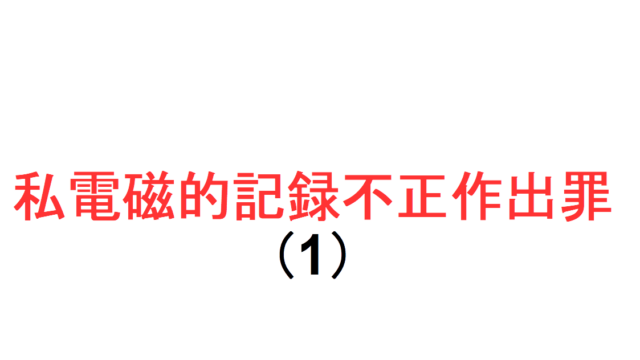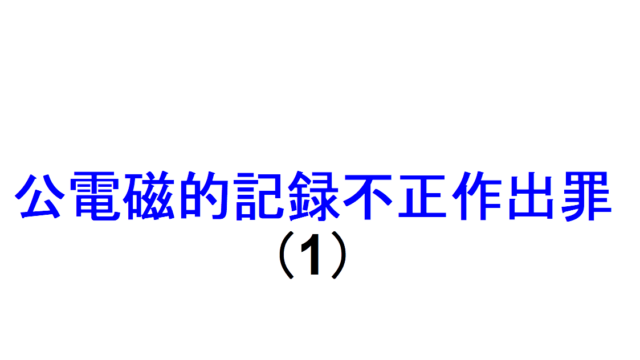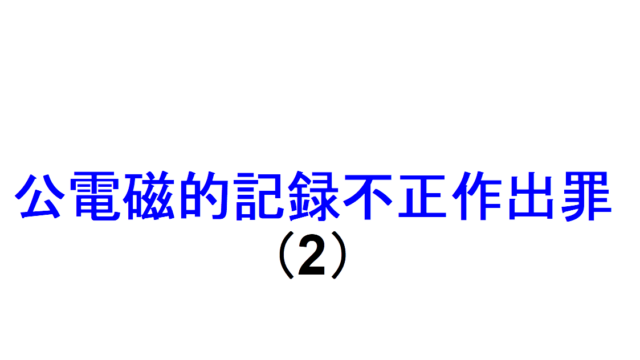不正作出電磁的記録共用罪(2)~「本罪の客体・行為」を説明
前回の記事の続きです。
不正作出公電磁的記録共用罪、不正作出私電磁的記録共用罪(刑法161条の2第3項)を適宜「本罪」といって説明します。
本罪の客体
本罪は、刑法161条の2第3項において、
不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する
と規定されます。
本罪の客体は、
不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録
です。
私電磁的記録(刑法161条の2第1項)、公電磁的記録(刑法161条の2第2項)のいずれであっても本罪の客体となります。
当該電磁的記録の作成自体について、不正作出罪に問えない場合であっても、本罪の対象となり得えます。
したがって、このような電磁的記録であれば、必ずしも供用の行為者自身が不正に作出したものである必要はありません。
また、その不正作出の行為者が人の事務処理を誤らしめる目的によらずに不正作出した場合も含まれます。
本罪の行為
本罪は、刑法161条の2第3項において、
不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する
と規定されます。
本罪の行為は、
「第1項(刑法161条の2第1項)の目的」、つまり、「人の事務処理を誤らせる目的」で、「人の事務処理の用に供」すること
です。
「人の事務処理を誤らせる目的」の意義は、私電磁的記録不正作出罪の場合と同じです(詳しくは私電磁的記録不正作出罪(3)の記事参照)。
「人の事務処理の用に供」するとは、
不正に作出された電磁的記録を他人の事務処理のため、これに使用される電子計算機において用い得る状態に置くこと
をいいます。
本罪の具体例として、
- インターネットオークションの会員情報や住民基本台帳ファイルの記録のような備付型電磁的記録について、不正作出行為を完了し、これをサーバーコンビュータや、所定の磁気ディスク装置などに備え付けるなどして、当該事務処理に用い得る状態に置くこと
が挙げられます(大阪高裁判決 平成19年3月27日、仙台地裁判決 平成2年9月11日)。
なお、従前は、不正に作出された磁気ストライプ部分のある銀行預金通帳のような携帯型電磁的記録については、これを銀行の自動預入支払機(ATM)に挿入して、記録内容が読み取り可能な状態にすることについて本罪の対象となっていましたが、現在は不正作出支払用カード電磁的記録共用罪(刑法163条の2第2項)の対象となっています(東京地裁判決 平成元年2月17日)。
このような供用行為を開始したときに供用罪の実行の着手があり、それが完了した時点で既遂に達するものとされます。
例えば、携帯型電磁的記録にあっては、不正作出された磁気ストライプ部分のある銀行預金通帳を銀行の現金自動預入支払機(ATM)に挿入しようとしたときに実行の着手があり、これを挿入して記録内容の読み取りが可能となった時点で既遂になります。
備付型電磁的記録の場合は、文書における備付け行使と同様、その不正作出行為に引き続き(作出が完了すると同時に)供用行為の実行の着手があり、直ちに既遂に達するという場合が多いと思われますがが、例えば、電磁的記録の作出後、これに対するアクセスの禁止措置を解除することによってはじめて電子計算機による人の事務処理に用いられるような仕組みになっているような場合には、禁止措置が解除されてはじめて既遂に達することとなります。