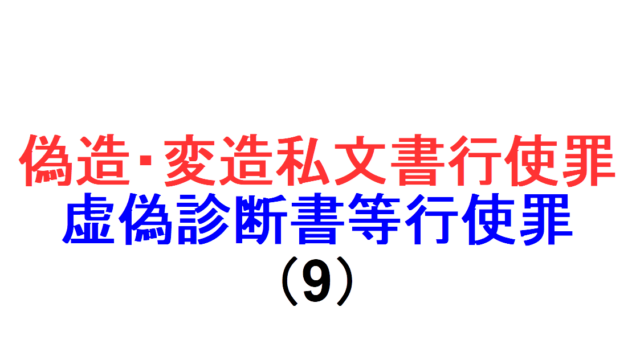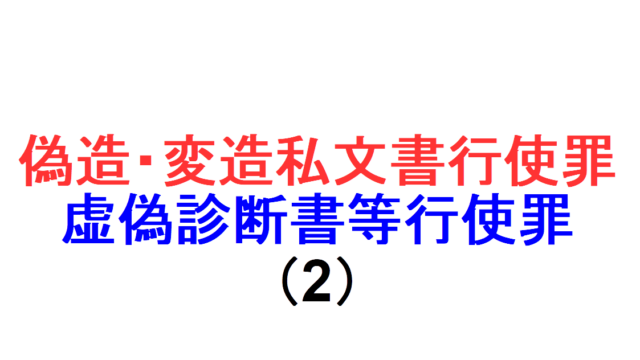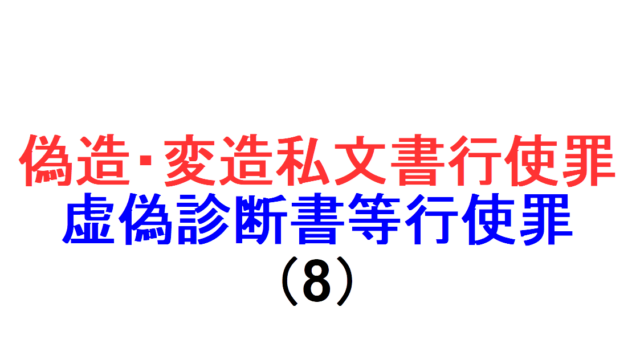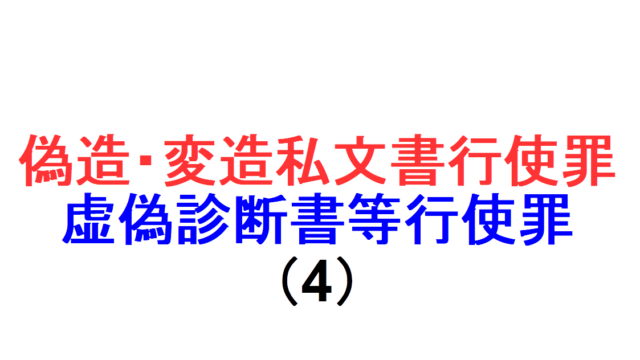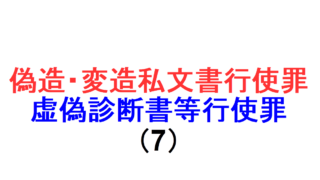偽造私文書等行使罪(6)~他罪との関係①「本罪と①私文書偽造罪、②偽造公文書行使罪との関係」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、刑法161条の罪(偽造有印私文書行使罪、変造有印私文書行使罪、偽造無印私文書行使罪、変造無印私文書行使罪、虚偽診断書行使罪、虚偽検案書行使罪、虚偽死亡証書行使罪)を「本罪」といって説明します。
他罪との関係
本罪と
の関係を説明します。
① 私文書偽造罪との関係
1⃣ 私文書を偽造した上でこれを行使したときは、私文書偽造罪と本罪との牽連犯(刑法54条1項後段)に当たります。
実際の裁判では判決において、刑法54条1項の「重い刑」を選定する際には、行使罪の刑の方が偽造罪よりも犯情が重い(刑法10条3項)と取り扱うのが通例となっています。
2⃣ 特異な事例として、白紙委任状数通(5通)を順次偽造し、その一部(2通)を一括行使して詐欺の手段に供したものの、残り(3通)は行使しなかった場合には、2通の行使行為と未行使の3通の偽造行為との間に牽連関係があるものとは認められず、これらは併合罪になるとした裁判例があります。
東京高裁判決(昭和33年3月20日)
裁判所は、
- 論旨(※弁護人の主張)は、原判決は法令の適用に誤りがあって、その誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を免れない、というのである
- 原判決は罪となるべき事実中に被告人らがT名義の白紙委件状5通を順次作成偽造し、右偽造にかかる委任状のうち2通をその他の文書と共に一括行使した旨認定し、爾余の委任状3通については何ら行使の事案を認めていなこと、したがって右委任状3通が現実には詐欺の手段として用いられなかったことは、まことに所論(※弁護人の主張)のとおりである
- されば、右委任状3通は本件詐欺の予備として作成偽造されたが、いまだ現実には行使されなかったものであり、かつ前記偽造にかかる2通の委任状の行使といまだ行使されない右3通の委任状の偽造との間には牽連の関係があるものとは認め難いところであるから、原判決は、法令の適用に当っては、原判決説示のごとく、「偽造公文書並びに偽造私文書のそれぞれ一括行使の点は1個の行為にして数個の罪名に触れる場合で、公文書偽造と同行使、私文書偽造と同行使並びに右両者と詐欺との間には順次手段結果の関係があるから、刑法第54条第1項前段、後段、第10条により最も重い偽造公文書行使罪の刑に従う」ほか、前記偽造にかかる委任状のうち行使しなかった3通の各私文書偽造とともに、それぞれ累犯加重をした上、以上は、併合罪の関係にあるものとして刑法第45条前段を適用すべきであったことは、所論のとおりであって、この点に関する原判決の擬律は、結局前記偽造にかかる委任状のうち行使しなかった3通についても、その余の2通とともに、その偽造の点はその行使若しくは詐欺との間に牽連関係にたつものとしているものであって、失当といわなければならない
- しかしながら、右の擬律を非難し併合罪をもって論すべき数罪が成立すると主張するのは、すなわち、被告人の不利益に帰すべき論旨であって、適法な控訴理由とはなし難いところであるから、結局弁護人の主張は採用し難い
- ひっきょう、論旨は理由がない
と判示しました。
② 偽造公文書行使罪との関係
複数の偽造私文書を一括行使した場合は観念的競合(刑法第54条第1項前段)に当たります(詳しくは前回の記事参照)。
そして、偽造私文書と偽造公文書を一括行使した場合も、同様に観念的競合となります。
偽造に係る印鑑証明書と金円借用証書を同時に行使した場合には、偽造公文書行使罪と私文書偽造行使罪とは観念的競合となるとした以下の判例があります。
大審院判決(明治45年6月25日)
裁判所は、
- 偽造に係る印鑑証明書及び金円借用証書を同時に行使したるときは、すなわち1個の所為にして数個の罪名に触れるものなれば、刑法第54条第1項前段を適用すべきものとす
と判示しました。
③ 公正証書原本不実記載・不実記載公正証書原本行使罪等との関係
1⃣ 公正証書作成の代理委任状を偽造・行使し(私文書偽造罪・偽造私文書行使罪)、公証人をして公正証書の原本に不実の記載をさせ、これを行使したときは(公正証書原本不実記載・不実記載公正証書原本行使罪)、委任状の偽造・行使は公正証書原本不実記載・同行使の手段となるので、「私文書偽造罪・偽造私文書行使罪」と「公正証書原本不実記載・不実記載公正証書原本行使罪」とは牽連犯の関係に立ちます。
この点を判示したの以下の判例です。
大審院判決(明治42年2月5日)
裁判所は、
- 公正証書作成の代理委任状を偽造し、公証人をして公正証書を作成せしめ、これを行使したる場合には、該委任状の偽造行為は、公正証書偽造行使の所為の手段にほかならざれば、刑法第54条(※牽連犯の規定)を適用処断すべきものとす
- 従って、右2個の所為を個々独立するものとし、同法第47条(※併合罪の規定)を適用したる判決は不正なり
と判示しました。
2⃣ 同様に、他人の名義を冒用して自動車運転免許証下付願及び履歴書を偽造行使し、運転手試験を受けて合格し、当該吏員をして名義人を運転手とする不実の内容を自動車運転手免許証に記載させ、その下付を受けてこれを行使したという事案において、私文書の偽造・行使罪と免状不実記載・同行使罪は互いに手段結果の関係にあり、牽連犯になるとした判例があります。
大審院判決(昭和5年3月27日)
裁判所は、
- 他人の名義を冒用して自動車運転手免許証下付願及び履歴書を偽造行使し、運転手試験を受け、これに合格し、当該吏員をして名義人を運転手とする不実の記載を自動車運転手免許証に為さしめ、その下付を受け、これを行使したる場合においては、免許証下付願及び履歴書の偽造行使罪と、免状に不実の記載を為さしめこれを行使したる罪との間には、互いに手段結果の関係あるものとす
と判示しました。