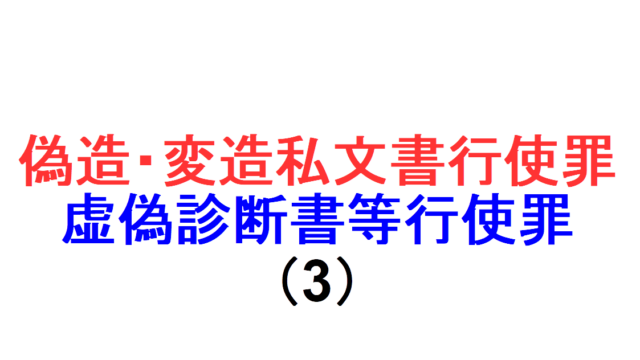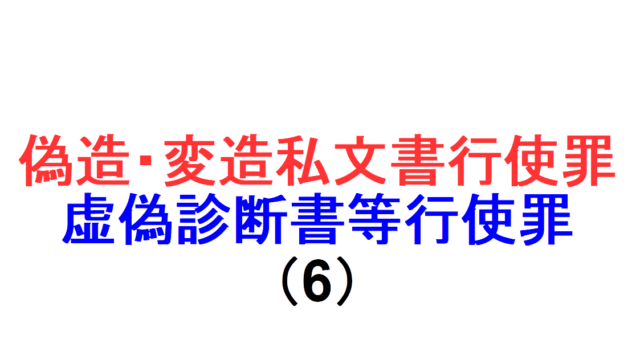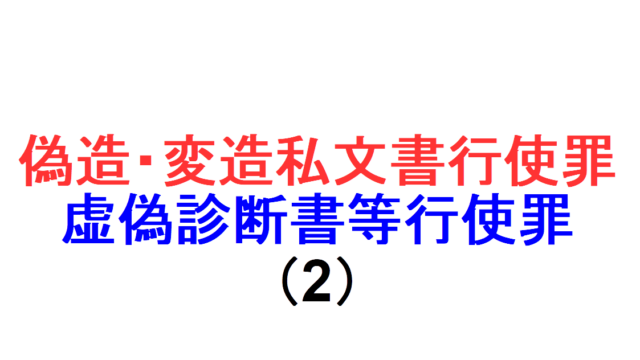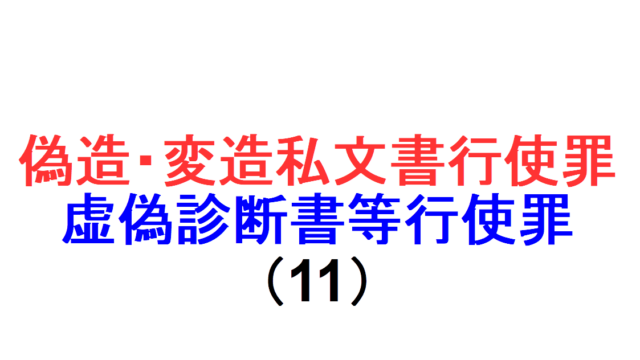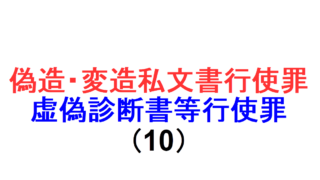偽造私文書等行使罪(9)~他罪との関係④「本罪と①横領罪、②窃盗罪との関係」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、刑法161条の罪(偽造有印私文書行使罪、変造有印私文書行使罪、偽造無印私文書行使罪、変造無印私文書行使罪、虚偽診断書行使罪、虚偽検案書行使罪、虚偽死亡証書行使罪)を「本罪」といって説明します。
他罪との関係
本罪と
との関係を説明します。
① 横領罪との関係
1⃣ 私文書の変造及び行使罪と横領罪との間に因果関係があるときは、これらは牽連犯になる旨判示した裁判例があります。
大審院判決(明治42年8月31日)
裁判所は、
と判示しました。
2⃣ 他人所有の株券を占有する者が、ほしいままにこれを自己の債務の担保に供するため、同株券の名義書換えに関する所有者名義の委任状及び株式処分承諾書を偽造し、これら文書とともに株券を担保として自己の債権者に交付したときは、株券の横領罪と本罪とは観念的競合に当たるとした判例があります。
大審院判決(昭和7年4月11日)
裁判所は、
- 他人所有の株券を占有する者が、自己の債務の担保に供するため、その株券の名義書換えについて、委託者の委任状及び株式処分承諾書を偽造し、その文書と共に株券を担保として債権者に交付したときは、偽造の段階から株券の不法領得の意思を発現したものであって、株券の横領と両文書の偽造行使とは観念的競合となる
としました。
② 窃盗罪との関係
通信事務員として郵便物の区分に従事する者が、為替証書在中の郵便物を窃取した上、同証書に受取人氏名を偽署するなどして偽造した文書を郵便局に提出行使した場合、文書偽造とその行使との間には手段結果の関係があるので牽連犯となるが、「文書偽造罪・偽造文書行使罪」と「窃盗罪」との間には牽連関係がないから併合罪になるとした判例があります。
大審院判決(大正7年4月24日)
裁判官は、
- 被告が通信事務員として郵便物の区分に従事中、為替証書在中の郵便物を窃取し、なお為替証書に受取人の氏名を偽署し、名下に偽造印を押捺し、これを郵便局に提出行使したるときは、該文書偽造とその行使との間には手段結果の関係あるをもって刑法第54条後段、第10条を適用すべきものなりといえども、これらの罪と如上窃盗罪との間には牽連関係を存せず、全然独立する犯罪なるをもって併合罪として処断すべきものとす
と判示しました。